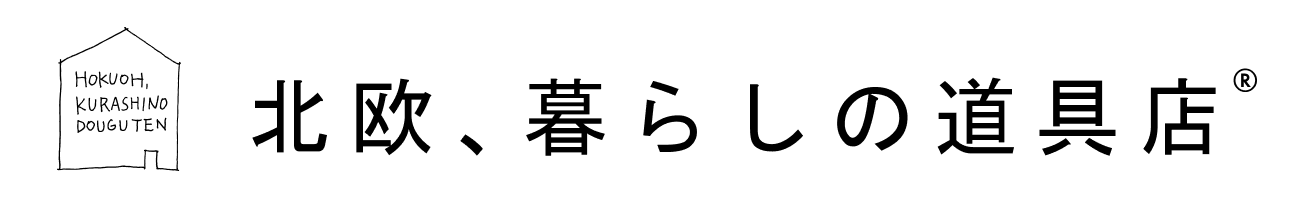本が好きです。でも、「読書」と呼べるほどの本を読んでいるかと言われると……ちょっと自信がありません。
あるとき子どもと訪ねた図書館で、大好きだった『ズッコケ三人組』シリーズ(那須正幹著)を手に取りました。個性豊かなわんぱく男子3人が、冒険したり失敗したり、ときにタイムスリップしたりする児童文学のロングセラーです。児童書ということもあってすいすい読み進められ、あっという間に読了。ひさしぶりに物語の世界に入り込む楽しさを思い出しました。
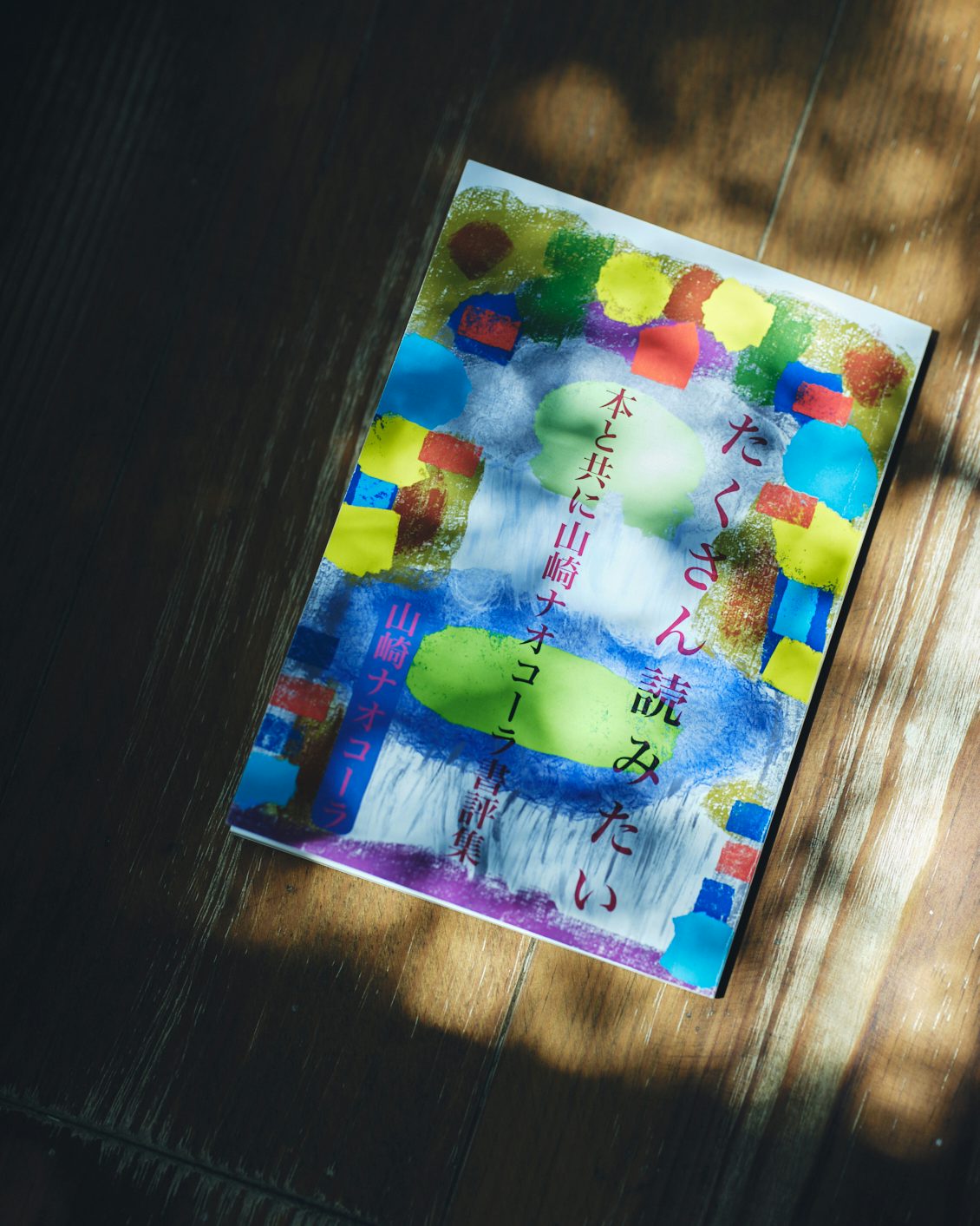 ▲『たくさん読みたい 本と共に山崎ナオコーラ書評集』(ソーダ書房)
▲『たくさん読みたい 本と共に山崎ナオコーラ書評集』(ソーダ書房)
本ってやっぱりいいなあ。そう思っていたときに出会ったのが、作家の山崎ナオコーラさんがつくった書評集です。『たくさん読みたい』と題したZINE(個人制作の小冊子)には、古典名作からミステリー、海外の翻訳もの、エッセイなどジャンルもさまざまに紹介され、ページをめくるごとに読んでみたい本がどんどん増えていきます。
なによりおもしろかったのは、本の感想の端々に、山崎さん自身の生活が見えることでした。子どもとの生活、夫婦の会話、仕事、そして社会のこと。
山崎さんの生活の中に、読書はどんなふうに根ざしているのでしょうか。これまでに読んだ思い出深い本をまんなかに、お話をうかがいました。
しつけも教訓もない、アリスの世界のおもしろさ

26歳で作家としてデビューした山崎さん。子ども時代はどんな本を読み、これまでどんなふうに読書と生活をともにしてきたのでしょう。
山崎さん:
「子どものころは人前で話すことがすごく苦手で、幼稚園でも小学校でも友だちを作れなかったんです。学校では一言もしゃべらない。そんな時期は10代に入ってからも続きました。だから、本の中が唯一の場所だったのかもしれません。親が2週間おきぐらいに図書館に連れて行ってくれていました。
衝撃的だったのが小4のときに読んだ『不思議の国のアリス』です。それまでに読んでいた本は、『いい子になりましょう』『お友だちにはやさしく』と、いわゆる教訓めいたものがありましたが、アリスの世界は意味のわからない言葉遊びばかり。『本ってこんなのでもいいんだ』と思ったのを覚えています」
本は誰かと語り合うものではなく、ひとりで味わい楽しむもの。そう感じながら、学生時代は手に取りやすい文庫コーナーでタイトルや装丁を頼りに選び、その後も10代、20代とぞんぶんに読書を楽しんできた山崎さん。
けれども、子どもとの暮らしが始まるとそうもいかなくなりました。
子育ては今しかないストーリーを読んでいる

山崎さんは9歳と5歳のふたりの子どもと暮らしています。仕事と生活、両方が溶け合う生活のなかで、読書の時間はどう作っているのでしょうか。
山崎さん:
「今はまだ、ぐっと没入して一冊を読み切るような読書は難しいです。家事の合間の5分、病院の待ち時間の10分、たくさんしおりを挟みながら、生活の中に読書を折り込むように読んでいます。
でもそれが、すごく面白いんです。同じように子育て中の作家の友人と、仕事が思うように進められないと話していたときに、『でも、育児そのものも文学だよね』と言われてハッとしました。
子どもとの会話や成長していく過程もストーリーだと思えば、育児だってひとつの長い物語を読んでいるようなものです。
読書は、生活というストーリーがあるところに、また別のストーリーが入り込んでいく感覚です。忙しい生活の中でパッと読んで、忙しいいまの自分の中だからこその感じ方、受け取り方を味わう。一冊をじっくり読み込むだけが読書ではなく、これもいましかできない、読書のひとつのかたちだと思っています」
子どもと過ごす時間も、読書に似ている?

山崎さん:
「読書って、行為としては紙の上の黒いかたちを目で追っているだけ。でもそれを味わっているとパッと思考が飛んで、いま見えているものと違う感覚が湧きます。それがおもしろいんです。
そう思うと、子どもの遊びに付き合いながら山の稜線を目で辿っている時間も、わたしにとっては本を読んでいるときと同じような感覚になれると気づきました。
塀のでこぼこをたどりながら、段落が下がっている部分みたいだと感じたり、蜂の動きを目で追ったり。そうしているうちに、頭の中にあった考えや悩み、日々考えていたことの方向性が変わっていきます。この感覚は、読書に似ていると思うようになりました」

山崎さん:
「それに読書のスタイルも、ずいぶん自由になりましたよね。『本』という形ばかりを追う必要はないし、もっと多様でいいのだと思います。電子書籍だって、10年、20年前は邪道だ、本は紙でこそ読むべきだ、なんて言われていましたが、すっかり浸透しましたし、今は音声で聞くオーディオブックも『読書』と捉えるようになってきました。
もっと言えば、SNSに流れてくる本の引用文を目で追うことも、読書と呼べるのかもしれません」
読む順番も飛ばし読みも、「わたし」主体の自由でいい

さらに、読書は著書の主張や考えにこだわらずとも、読者、つまり読み手のわたしたち一人ひとりが主体で決めていけばいいというのが山崎さんの思いです。
山崎さん:
「真面目な方ほど、国語の授業のように『作者の意図を読み解く』読書をしなくちゃと思っているかもしれません。
でも同じ本でも読み手の環境やタイミングで感じ方、受け取り方は変わるし、それが当然だと思います。
たとえば、わたしの好きな『源氏物語』。学生時代は、平安当時の生活様式とは、結婚とは……というふうに、時代背景を学び、当時はこういうものだったという勉強ありきの読み方でした。でも令和のいま、現代人が読むと違和感があるのは当たり前です。むしろ、現代に生きる自分が読むならこういう解釈だな、自分だったらこうは思えないなど『わたし』を大切にした読み方をしたいです」
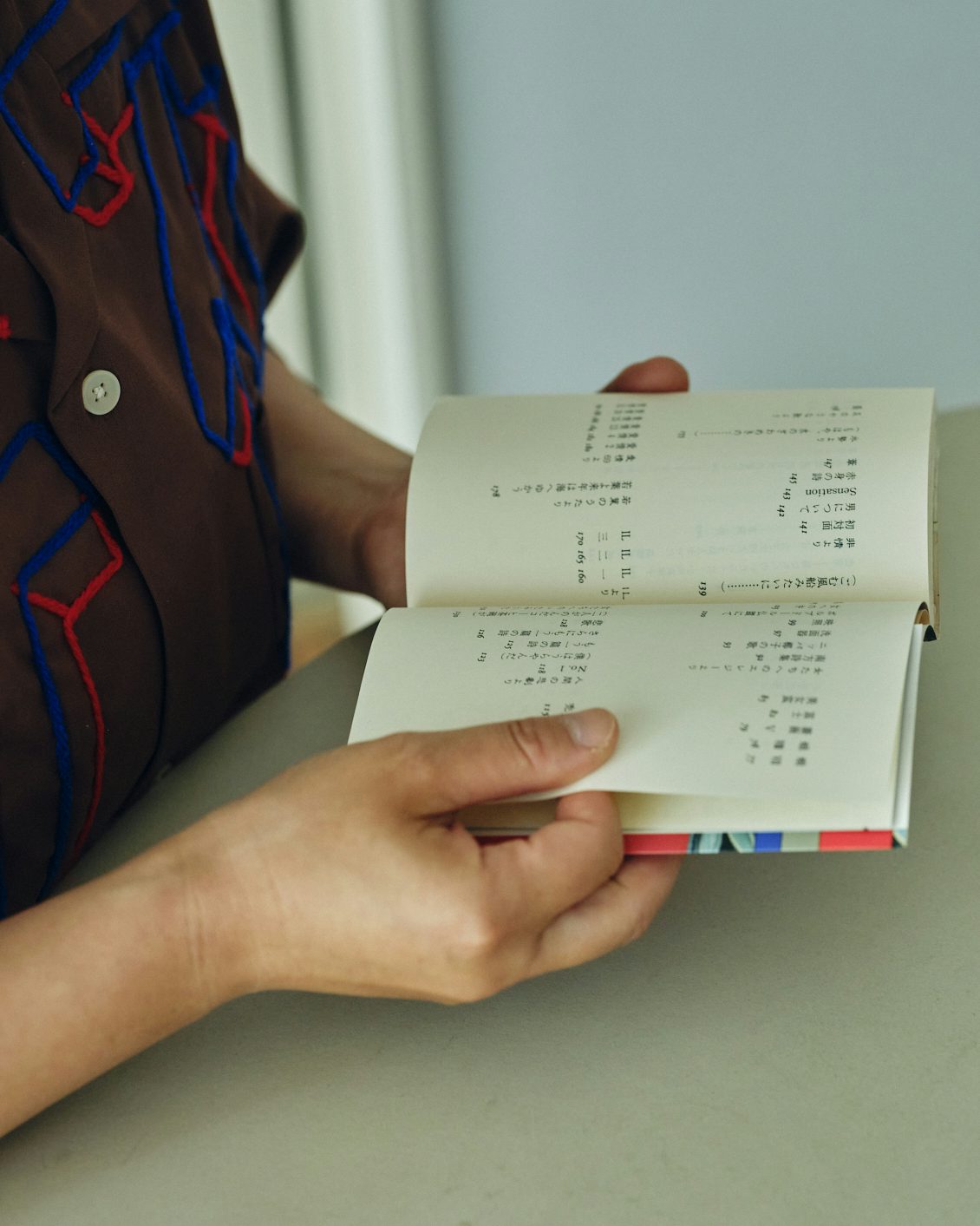
山崎さん:
「読む順番も、読者が決めていいと思います。ラストから読んでもいいし、飛ばし読みでもいい。それこそ『源氏物語』なんて、何十帖もあるので好きなところだけ繰り返し読む人もたくさんいます。現代小説だって同じでいいですよね。
もちろん、一言一句を大切に、わからない言葉は辞書を引いて……と読むのが好きな人もいますし、それも自由です。
けれど、それだけが正しい読書ではないし、どう読むかは読者が決めていいことだと思います。気軽に読むほうが、結果的に本を手に取る機会も読む量も、増えていきそうですよね。
きっちり読むことにこだわるよりも、本をきっかけに何か考え事が始まるほうが大切だと思います」

山崎さん:
「そもそも、言葉は同じものを共有できる道具ではありません。『クッキー』という言葉ひとつをとっても、読みながら完全に同じものを浮かべる人は少ないはず。
だから本を読んだときに、みんなが同じものを思い浮かべなくてもいいし、作者の意図をすべて汲み取ろうとしなくてもいい。自分の読み解き方や受け取り方で自由に読んで大丈夫。少なくとも、わたしはそう思っています」

飛ばし読みでもいいし、受け取り方も自由でいい。そう知れただけで、読書のハードルがすとんと下がり、読んでみたい本が増えていくのを感じます。
この後は、山崎さんがこれまでに読んで印象的だった本を教えていただきました。
どんな本が登場するのか、続きはどうぞ後編で。
【写真】土田 凌
もくじ


山崎ナオコーラ
作家。1978年生まれ。性別非公開。國學院大學文学部日本文学科卒業。2004年、会社員をしながら書いた「人のセックスを笑うな」で第41回文藝賞を受賞しデビュー。「源氏物語」を現代解釈で説くエッセイ「ミライの源氏物語」で第33回(2023年度)Bunkamuraドゥマゴ文学賞受賞。近著にゆるSF長編小説「あきらめる」。児童文学家協会会員。目標は「誰にでもわかる言葉で誰にも書けない小説を書きたい」。
感想を送る