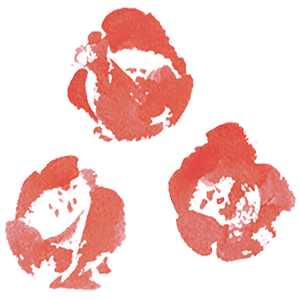サルディーニャ島で働く若者の俳句
「夕暮れに 黄金舞うよな 赤蜻蛉」
高山源樹さんが少し恥ずかしそうに自作の俳句を詠むと、僕を含む車中の5人から「おー!」という声が上がった。
その車はアジアや中南米、アフリカなどで乗り合いバスに使われていそうな大きなバンで、前の座席にはハンドルを握る木工作家の高山英樹さん、息子の源樹(げんき)さん、妻の純子さんが並んで座っている。その後ろの席に、ライターである僕と編集担当の二本柳さん、写真家の鍵岡さんが腰かけていて、さらに後方には広い荷台があった。

車は、宇都宮駅に向かっていた。益子にあるセルフビルドのご自宅で取材を終えた後、「宇都宮まで送りますよ」という英樹さんの言葉に甘えさせてもらったのだ。その道中、源樹さんが「最近、俳句を作った」という話になり、その流れからの「赤蜻蛉(あかとんぼ)」だった。
源樹さんは17歳、高校二年生の時にひとりでイタリアを旅した時、イタリアのモノづくりやイタリア人の気質に惹かれて、高校卒業後、イタリアに渡った。それから言語を学び、さまざまな出会いを経て、23歳の現在は地中海に浮かぶサルディーニャ島のブティックで働いている。
 ▲左から英樹さん、息子の源樹さん、妻の純子さん
▲左から英樹さん、息子の源樹さん、妻の純子さん
そのブティックはユニークで、観光客が島から姿を消す寒い時期はインドのゴアで洋服を作っている。その間、源樹さんは益子の実家に戻って日本を満喫する。
取材に訪れた日は、イタリア人の友人たちを連れて行った沖縄旅行から戻ったタイミングで、親子3人が益子に揃っていた。
子どもには「かっこつけて」生きてほしい

源樹さんの母方の曽祖父(純子さんの祖父)は俳句の研究者として大学の教授を務めていたということもあり、純子さんも源樹さんも子どもの頃から俳句に親しんできた。印象的な風景を俳句にして詠むのは日常の一コマで、その習慣が今も続いているのだ。
髪の毛を肩まで伸ばし、流ちょうにイタリア語を操り、日常的に俳句を詠む若者はそういない。手先も器用で、益子の家には自分で作った木製の椅子が置かれている。
 ▲源樹さんが自作した「勉強に集中せざるを得ない」椅子。座ると机に向かい前かがみになるよう斜めになっている
▲源樹さんが自作した「勉強に集中せざるを得ない」椅子。座ると机に向かい前かがみになるよう斜めになっている
源樹さんのことを「(自分の)バージョンアップ!」と嬉しそうに話す英樹さん。その隣で母親の純子さんは朗らかに笑っている。
「子どもは親の感性を超えるもの。源樹には『かっこつけろよ』と言い続けてきました。
勉強しろと言ったことはないし、成績表を気にしたことはないけど、唯一他者を攻撃する言葉は禁止してきた。そんなの『粋(いき)』じゃないでしょ。粋であるかどうかが僕たちの判断基準なんだ」
益子から宇都宮までの約1時間は、まるで旅の途中のようだった。高山家がバンで世界を巡っている家族、僕らはその途中で知り合ってバンに乗せてもらった旅人のような感覚といえばわかってもらえるだろうか。
英樹さんの原点も、バンだった。
ひとり旅で見た、常識とルールの外側

1985年、メキシコのメリダ。アメリカのマイアミからユカタン半島の西端の町に飛んだ英樹さんは、空港に着いて唖然とした。空港が小さく寂れていて、マイアミの賑わいとはあまりに対照的だったからだ。
この時、21歳。石川県の能登で生まれ、文化服装学院卒業後、東京で服飾関係の仕事をしていた英樹さんは、友人の勧めもあって初めての海外旅行に出かけた。ニューヨークから中西部を経てマイアミにたどり着き、「ここからビュンと飛んだらメキシコなんだ!」と思い立った勢いで航空券を買った。
メリダの空港から町なかに向かおうと、乗り合いのバンに乗った。そこで、初めての光景を目にした。運転手がレーサー気取りでアクセル全開、飛ばしに飛ばして目の前の車やバイクをどんどん追い抜かしていく。
そこにはアメリカという先進国で感じた「常識」や「ルール」は存在しなかった。

最初はあまりのスピードに驚き、冷や汗をかいていた高山さんも、次第にワクワクしてきた。安全を守るベルトのないジェットコースターに乗っているような気分だった。
メキシコを旅している間、その高揚が途切れることはなかった。夜、お酒を飲みに行くと、たくさんの人が話しかけてくる。みな、よく来てくれた! と歓迎し、メキシコのお酒で乾杯する。それから言葉を交わし、打ち解け、気持ちよく酔って帰ろうとすると、その場にいた人たちが酒代を支払ってくれるということが何度もあった。
そして、良い旅を! と爽やかに別れる。この時から「自分も粋でありたい」と強く思うようになった。
そうか、もっと自由に生きていいんだ

東京やアメリカには存在しない混沌と猥雑、そしてそこに生きる人々の熱量。都会でのどことなくよそよそしい暮らしになんとなく違和感を抱いていた英樹さんには、むしろ居心地がよかった。
メキシコの隣国、グアテマラに入ると再び目を疑った。そこでは、人々が薪を背負って暮らしていたのだ。もはや昔話の世界で、同じ時代を生きているとは思えなかった。でも、貧しいとか、かわいそうという感情はなかった。先進国ほどモノがないからこそ、人々の暮らしは創意工夫の宝庫だったし、東京やアメリカで出会う人たちよりも、グアテマラの人々のほうが笑顔にあふれていたからだ。
ある日、バスに乗っている時に路上に倒れている人を目撃した。え、大丈夫!? と心配したら、単に昼寝をしている人だった。「あ、路上で昼寝してもいいんだ」と思うと、胸がすく思いがした。
アメリカから始まりグアテマラで終わった4カ月にわたる旅の間、現代人としての思考や価値観が揺さぶれる体験を何度もした。そのうちに、人生が開けた気がした。
「なんだよ、こんな世界があったなんて、もっと早く教えてよって感じだった(笑)。そっか、自由に生きていいんだ、だったら俺もそうしょう!ってね」
「得しようと思わなければいいんだよ」

それからは、東京で仕事をして、お金が貯まったら旅に出るという生活になった。中米やインド、ヨーロッパにも足を運んだ。旅先では、お金のある、なしにかかわらず、「自分が楽しいと思うこと」に没頭している人たちが大勢いて、みな幸せそうだった。彼らは常識にとらわれず、自分の手で自分らしい暮らしを模索していた。
そのうち、自分もそういう生き方を実践したいという思いが募った。誰かが考えたシステムの上で生きるのではなく、生活そのものを自ら作り上げたい……。
その頃に出会ったのが、純子さんだ。純子さんは「自分の知っていることは本当に少し。ほかの部分にすっごい面白いことがあるかもしれないと思っている」と話す、好奇心の塊のような人。
そんな純子さんだから、東京にいながら少し浮世離れした雰囲気の高山さんに惹かれたのかもしれない。

純子さんには忘れられない思い出がある。ふたりでインドネシアを旅行した時、海外ではよくある「ぼったくり」に遭ってしまった。それから、ほかの人に対しても警戒心を抱くようになってしまった。
その時、英樹さんに「引きずってたら旅がもったいないよ。こちらが得しようとしたら、もっと上手の人がいるから騙されるのは当たり前。得しようと思わなければいいんだよ」と言われたのだ。
予想もしなかった言葉が、純子さんの胸に刺さった。やがてふたりは結婚した。

(つづく)
【写真】鍵岡龍門
もくじ


高山英樹
益子在住の木工作家。石川県出身。文化服飾学院を卒業後都内で舞台衣装や布のオブジェを制作。のちに、北米や中米、アジア、ヨーロッパなどを旅しながら、国内で内装や家具の制作を手がけるように。2002年に益子へ移住し、現在は「暮らし家」として、国内外で作品を発表するほか、ものづくりのワークショップなど幅広く活躍する。

川内イオ
1979年生まれ。大学卒業後の2002年、新卒で広告代理店に就職するも9ヶ月で退職し、03年よりフリーライターとして活動開始。06年にバルセロナに移住し、主にスペインサッカーを取材。10年に帰国後、デジタルサッカー誌、ビジネス誌の編集部を経て現在フリーランスエディター&ライター&イベントコーディネーター。ジャンルを問わず「規格外の稀な人」を追う稀人ハンターとして活動している。稀人を取材することで仕事や生き方の多様性を世に伝えることをテーマとする。
感想を送る