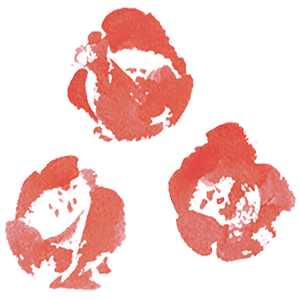高校時代、およそ真面目な生徒として通っていたが、遅刻だけはかなり多かった。
特に2年生の時はひどく、担任の先生には朝が苦手な子なのだと思われていたと思う。
だけど本当は、むしろ朝型だった。寝坊したことはほとんどなく、毎日定刻には朝食も食べ終わり、準備も済んでいた。
それなのになかなか家を出る気にならず、よくぐずぐずと家で本を読んでいた。「もう今から家を出ても間に合わないな」という時間になると、ようやく行く気になる。母は、私が遅刻しているなんて思いもしなかっただろう。いつも悠々と出ていくものだから。
遅刻していく日は、通学路に生徒が誰もいなくて静かだった。代わりに、ぽつぽつと大人が数人歩いている。仕事に向かうのか、散歩をしているのか、よくわからない人たち。
私はそんな人たちの中を、ウォークマンで音楽を聴きながらのろのろと歩いた。
イヤホンから流れ込んでくる音楽は、たいていは都会の街で作られているであろうもので、「こことは違う場所」のものに思えた。そういう遠くで鳴っている音楽を聴きながら歩いていると、なんとなくその道が「こことは違う場所」に繋がっている気がして、心が軽くなったものだ。
「世界は広いよ」
あの頃はそう言われても、全然ピンと来なかった。
家と学校くらいしか、自分には「世界」というものがない。
それ以外の「世界」は全部想像上のものでしかなかったから、どのようにその広い世界へ飛び出せばいいのか見当もつかず、私はただただ定刻外の道を歩くのだった。
§
最近、週1でバスケットをしている。
滋賀のスポーツ施設にバスケットコートがあるのだけど、そこまで車で30分弱。土日の午前中から、ドライブがてら体を動かすのは気持ちがいい。
コートは1時間あたり、ひとり300円で借りられる。10名まで使うことができるコートにはいろんな人が来るので、2つのリングを見知らぬ人たちと譲り合いながら使っている。
この間行った時には、高校生が6人くらいいた。
きっとみんなバスケ部員なのだろう。似たような練習着を着ていて、マイボールも持っている。シュート練習や1on1に励む練習風景に、元バスケ部の私は懐かしい気持ちになった。
一緒に連れてきた10歳と5歳の息子たちは、お兄ちゃんたちに気圧されてコートの隅でもじもじしている。「おいでよ」と呼びかけても、恥ずかしいのかなかなか来ない。
仕方がないので、私だけシュート練習を始めることにした。私だってやりにくくないわけではないけれど、昔、体育館で男子バスケ部員と混じって練習をしていたことを思い出しつつ、淡々とシュートを打ち続けた。
その時、ひとりの高校生のボールがこっち飛んできた。取って投げ返すと、持ち主は「あざっす」と小さい声で言い、綺麗なフォームでまたシュートを打った。
彼らにとっては、36歳の子持ちの女性なんて、ずいぶん違う世界の人のように見えるのだろうなとふと思った。もちろん、私にとっても男子高校生たちは違う世界の人だけれど、私にも高校生だった時代はあるから、なんとなく想像はできる。
でも、その逆はどうだろう。
高校生だった私が、かつて定刻外の通学路で出会った大人たちのように、彼らにとって今の私は、よくわからない大人に見えているのかもしれない。
そのとき唐突に「遠くに来たなぁ」と思った。
気づけば今の私は、通学路を歩いていた頃の私とすれ違う側の大人だ。仏頂面でイヤホンを耳に突っ込んだ若者を見て、微笑ましく思う側の。
10分ほど経つと、ようやく息子たちがボールを持っておずおずとコートに入ってきた。
さっそくボールが飛んできて、長男がそれを取って高校生に返す。
「ありがとう!」
お兄ちゃんにそう言われた長男は、どことなく誇らしそうな顔だった。
§
帰りの車の中で、高校時代によく聴いていたアルバムをかけた。スピッツの『三日月ロック』というアルバムだ。
リリース年を見ると2002年とあり、
「20年前!」
と、思わず声をあげてしまう。子供たちが「どうしたの?」と言うので、
「私が高校生の時に聴いていた曲だよ」
と教えてあげた。ちょっと大きめの音にして、アクセルを踏む。
音楽が流れ始めると、一気にあの頃の感覚がよみがえって戸惑った。
教科書の入った重たいリュックサック、紺色のプリーツスカート、ボロボロになるまで履いたアディダスのスニーカー。
どこにだって行ける、なんだってできる、と周りの大人は言うけれど、自分では全然そう思えなかったあの頃。
それでも、音楽を聴きながら歩いていると、自分が映画の登場人物になったみたいで、どこか遠くへ行けそうな気がした。
君と遊ぶ 誰もいない市街地 目と目が合うたび笑う
夜を駆けていく 今は撃たないで 遠くの灯りの方へ駆けていく
スピッツ『夜を駆ける』
「いい曲だねぇ」
と、私はつぶやく。子供たちに言ったのではなく、高校生の頃の私に。
すると、助手席にあの頃の私が座っているような気持ちになった。まるで、高校生だった頃の私と一緒にドライブをしているような。
大丈夫。明るい方へと歩き続けていれば、自然と世界は広がっていくよ。
そう心の中で呼びかけ、私は鼻歌を歌った。

“ あの頃よく聴いていた曲口ずさむ隣にいるのはあの頃の自分 ”
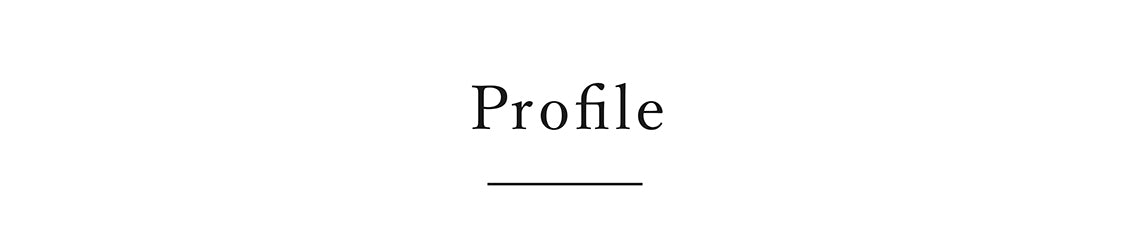
 1985年広島生まれ。小説家。京都在住。小説、短歌、エッセイなどの文芸作品や、インタビュー記事を執筆する。著書に歌画集『100年後あなたもわたしもいない日に』、インタビュー集『経営者の孤独。』、小説『戦争と五人の女』がある。
1985年広島生まれ。小説家。京都在住。小説、短歌、エッセイなどの文芸作品や、インタビュー記事を執筆する。著書に歌画集『100年後あなたもわたしもいない日に』、インタビュー集『経営者の孤独。』、小説『戦争と五人の女』がある。
 1981年神奈川県生まれ。東京造形大学卒。千葉県在住。35歳の時、グラフィックデザイナーから写真家へ転身。日常や旅先で写真撮影をする傍ら、雑誌や広告などの撮影を行う。
1981年神奈川県生まれ。東京造形大学卒。千葉県在住。35歳の時、グラフィックデザイナーから写真家へ転身。日常や旅先で写真撮影をする傍ら、雑誌や広告などの撮影を行う。
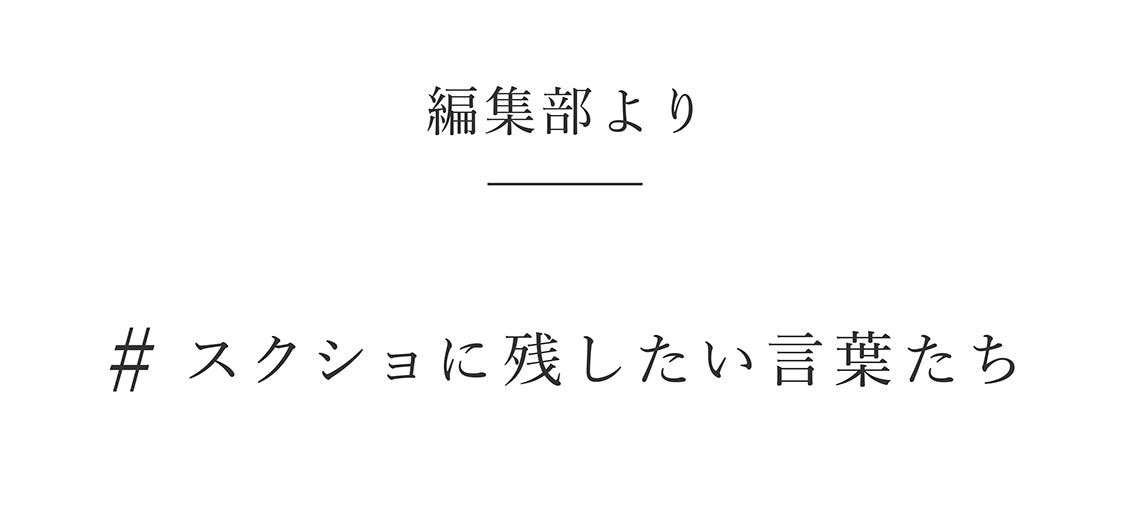
私たちの日々には、どんな言葉が溢れているでしょう。美しい景色をそっとカメラにおさめるように。ハッとする言葉を手帳に書き留めるように。この連載で「大切な言葉」に出会えたら、それをスマホのスクリーンショットに残してみませんか。
感想を送る