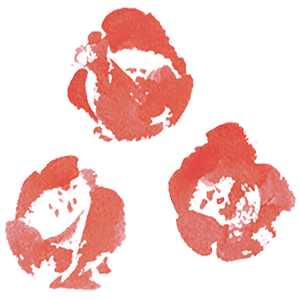電車を待っているときや寝入る時など、日常のなんでもない瞬間に、何年も前の些細なもやもやを、不意に思い出すことがある。なんであのとき「ノー」といえなかったんだろう。このとき、気持ちを伝えなかったんだろう。きっとあの人は今も私のことを誤解しているんだろうな……。
わざわざ、「じつはあのとき悲しかったんです」と口にするほどでもない、とるにたりないこと。なのに、なんだか忘れられないできごと。やるせない感情。わだかまりというほどでもない心のしこり。
つくづく、日々は喜怒哀楽より、言葉にできない感情のほうが多いなあと思う。
この連載では、そんな名指せない感情についてさまざまな方とお話をしている。
あなたの日々の中にも言葉にならないことはありますか? それとどんなふうに付き合っていますか、と。小さな生きづらさや心のすれ違いにくよくよする自分を、いったん肯定したい、それもまた自分であり、そのままの自分でいいと伝えられたらいいなと思っている。

暮らしの内側、もっといえば心の内側のこと

第二回目のお相手は、料理家の飛田和緒さんだ。
彼女のレシピはよく知っているし、海のそばでゆったり暮らしているのも、種々の媒体で垣間見ている。しかし、そういえばご自身のことをあまり知らないなと思った。
飛田さんとは同い年で、お嬢さんは私の娘より五歳下。互いに巣立ちはすぐそこだ。
ふだん、どんな事を考えておられるのか。
ここまでどんなふうに暮らしてきたのか。
彼女にあえて「切ない」という感情について尋ねたら、どんな答えが返ってくるだろう。暮らしの内側、もっといえば心の内側に、興味をつのらせていた。
対談の依頼をすると、拙著『信州おばあちゃんのおいしいお茶うけ』ほか、いくつか持ってくださっていたという。そう、実家は高校時代から、私の故郷と同じ長野なのである。
長野でも続けていたバレエとの、別れと再会のお話も。
海の見える自邸で、日が暮れるまでたっぷり伺った。
日々は言葉にできないことばかり

第二回 飛田 和緒さん
東京都生まれ。高校3年間を長野で過ごし、山の幸や保存食のおいしさに開眼する。現在は神奈川県の海辺の町に、レーシングドライバーの夫と高校生の娘の3人で暮らす。近所の直売所の野菜や漁師の店の魚などで、シンプルでおいしい食事をつくるのが日課。気負わずつくれる、素材の旨味を生かしたレシピが人気の料理家。日々のことを自身の言葉で綴ったエッセイ本『おとなになってはみたけれど』を2021年に上梓。
Instagram @hida_kazuo
17年前、東京から海の見える街へ

丘の上の一軒家。リビングの窓いっぱいに空。遠くに静かな海が見える。
飛田和緒さんが4カ月の長女を抱え、三浦半島に越したのは17年前だ。それまで都心で忙しく働き、夜は友だちを招いては楽しく過ごす日々だったという。
── 仕事が忙しくなり始めた頃だと思うのですが、東京から卒業するというのは、勇気のいることだったのでは。
飛田 うーん、そこまでも考えていなかったんですよ。東京が嫌っていうのでもなくてね……。なんとなく落ち着かなくなった。あまりにも仕事も生活も忙しくて、ざわざわとしたっていうんでしょうか、人がひっきりなしに出入りして、夜も来客があって。
── 楽しいんだけれど、せわしなかった。
飛田 そうなんです。もてなしたり、みんなと食べるのは大好きなので、つい遅くまでお酒を飲んじゃったり。不規則な生活で体調がすぐれず、点滴を打つこともあって、ちょっとそういう生活から距離をおきたいなと。どうせ引っ越すなら海が見える所がいい、少し東京から離れたいって、それほど深く考えずに決めました。
── お連れ合いは、そのときなんと。
飛田 反対でしたね。そんな遠くに行って和緒の仕事は大丈夫か、友達は来てくれるかなって。だから私が、もうぐいぐいと。
飛田さんの夫も、友人や仕事仲間が多い。実際、もてなしたりもてなされたりの日々から距離ができ、少しお付き合いは減ったが、今は海でのバーベキューや小旅行気分で友人が来てくれる。ちょうどいいバランスらしい。
ちなみに、今年はお嬢さんの受験で、家での集まりは控えめだ。

── インスタやエッセイを拝見すると、本当にお嬢さんとの時間を大事にされていて、進学などで離れたら寂しくなると、今から心配じゃないですか?
飛田 いえ、むしろ1日でも早くこの家を出て自立しなさい、と娘には言っています。そうしないと、あなたダメ人間になっちゃうわよって(笑)。
── ダメ人間ってそんな(笑)。
飛田 でも、私も18歳で長野の実家を出ましたしね。高齢で生んだ一人娘で、だからこそこの環境でぬくぬくしているのはよくないなと。そばにいると私もつい手助けや口を出してしまいがちなので。早く娘を送り出して、その後の夫婦ふたりの新しい生活、自分の次の人生を楽しみたいのです。
息子が独立して3年も経つのに、いまだ小さな喪失感が消えない私は、さばさばと語る飛田さんがひどく眩しく見えた。点滴を打つほど忙しかった日々からスパッと環境を変え、高齢出産で誕生した待望の娘とも、ベストな距離を冷静に俯瞰する。じつは仕事についても、いい本は作り続けたいが、要望がなくなったらこだわらず、着付けをやってみたいのだと目を輝かせる。
「それで打って出ようという気持ちは全然なくて、近所の人に頼まれたらやってあげられるくらいの着付け師さんになれたら素敵だなあって」。
独特の執着の手放し方を、印象深く思った。
「ノー」といえなかった

そもそも飛田さんの料理家としての出発点は、どこにあったのか。目指していた料理家像はあったのだろうか。
飛田 いえ、こういう料理家になりたいとかロールモデルというものは、なかったんです。仕事をご一緒する方々から「やりませんか」と言われたことに、必死で応えてきた。波にまかせてあっちこっち、探り探りやってきたようなものです。
バレリーナを目指し、20歳まで真剣に打ち込んだ。「もう、おしまいにしてもいいんじゃないか」という父の一言で踏ん切りが付き、短大卒業後は一般企業に就職、人事部で働いた。まだパソコンではなくワープロと格闘する時代だった。
料理は子どもの頃から好きで、長野ではとりわけ野菜料理や保存食の味わいに魅了された。
また、上京から結婚後まで暮らした洗足池界隈には当時、コンビニや24時間スーパーがなかった。その代わり商店街が充実していたので、豆腐や旬の野菜で日々の惣菜をおいしく仕上げることに熱中した。
同い年だからわかる。バブルの終わりかけだが、世の中はまだイタ飯やフレンチにキラキラ光があたっていた。その頃、飛田さんはせっせと、切り干し大根の煮物やきんぴらを追究していたのである。
24歳で結婚。家庭に入り、来客の多い自宅で料理を知人たちに振る舞う。たまたま文筆家の仕事を手伝った縁で、料理ページの仕事が始まった。

飛田 仕事を始めた頃、編集部に営業に行くのですが、ブックレット一つ持っていなくて。あとから「こういうときは試食の料理を持ってくるものよ」と聞いて恥ずかしくなりました。
── 私にも苦い思い出があります。営業のとき、「なんでもできるって言うのは、何でも浅くしかできないって言ってるようなものだよ」と言われて、大きく見せようとした自分が恥ずかしかったです。飛田さんが、それでも続けてこられたのはどうしてだと思いますか?
飛田 この方とお仕事をしたいと思える出会いが、続いたから。仕事を教えてくれる編集者やカメラマン、スタイリストに恵まれた。本当にそれに尽きます。その人達が、いつも私に合っているものを提案してくださる。そしたらもう、頑張っちゃいますよね。
── 人に恵まれたと。
飛田 はい。あと良かったことがあるとすれば、「やりませんか」と言われたら必ずのったこと。できるかどうかわからなくても、どうしようかなと考える前にのったんです。
── 失敗や、迷ったり悩んだりすることはありましたか。
飛田 ありましたねぇ……。得意じゃないことを受けてしまった時なんかは、ああ申し訳ないことをしたなと、心底思いました。たとえば私は、きちんと測って作らなきゃいけないお菓子は苦手なんです。それって必ず料理にも出る。自信のない料理になってしまうんですね。「できません」と言えるまでに、2、3年かかりました。
誰かの台所仕事に役立ってくれれば

── 料理本『常備菜』は、飛田さんが好きなことを続けてこられた一つの集大成だなと思いました。料理本大賞を受賞されて、たくさんの方に読まれ続けていますが、誕生までに、そういう試行錯誤の時間があったんですね。
飛田 常備菜は、仕事を始めた頃からずっとやりたいことでした。でも当時の料理本は、“おもてなし”のごちそうが主流。ホームパーティしましょうとか。どなたに話しても、「わざわざきんぴらなんて、本でやることないよ」と。その後、居酒屋、カフェ飯ブームが来て、やっとこのテーマを扱える空気になったのです。
読者や料理教室の生徒の多くは、自分の料理に対して不安があると語る。これでいいのか、つねに自信がないと。
「だから私の仕事は、できてますよーと背中を押す役割。私のやってきたことを聞いたり見たりして、その方の台所仕事に役立ってくれればそれでいい」。
声をかけられる限りは全力でがんばるが、がむしゃらに料理の仕事を続けたいと思っていないのは、冒頭の着付け師のくだりでも触れた。
『常備菜』のあと、日々の惣菜にスポットが当たり、だれもかれもがテーマとして扱うようになった。
次々と新しい料理家や料理本が出るなかで、東京と距離をとりながら、自分を遠くから俯瞰しているような冷静さは、どこからくるのか。私は考えあぐねていた。そう言うと、飛田さんは幼い記憶をさかのぼり始めた。
人生は努力してもままならないことがあると知った日

飛田 人間関係、夢。人生は努力してもままならないことがあると、私はバレエから学んだのかもしれませんね。
── どういうことでしょう。
飛田 本当に真剣に上を目指していたので。バレエってお金もかかるし、女性ばかりで、上下関係も厳しい。ままならないことだらけなんですよね。どんなにがんばっても、手足が長くて容姿のいい人、顔が小さくておうちが裕福な人には追いつけないの。
── 家も関係あるんですか?
飛田 同じくらいの実力なら、チケットをたくさんさばける家の子が役につける。お稽古ごとと、プロダンサーの線引きがあやふやだった。そういう時代でした。え?って思うこともたくさんあったけど、私は好きという気持ちだけでやってきた。そもそもバレエって、華やかに見えますが、ただひたすら同じ稽古を繰り返す、地味な世界なんです。稽古は苦しさしかない。
── それを20歳まで。
飛田 はい。それで、努力しても報われないことがあるんだなと、自分で悟りました。そろそろいいんじゃないかと父に言われた翌日、勧められた就職の面接に行ってました。
── 20歳にとって、それは大きな気づきでしたね。私なんかよりずっと早くに、人間の本質を悟っている。
飛田 でも今振り返れば、あのころはまだはっきりとはわかってなくて。人生にはままならないことってあるよなあと、はっきりわかってきたのは、料理の仕事を始めて、30歳も過ぎてからかもしれません。
── 振り返って初めて、そういうことだったかと気づく。人生は、そんなことだらけですよね。
飛田 もうひとつ、今思えば、バレエにひと区切りをつけた頃、入れ替わるように、夫のレーサーという夢が自分の夢にもなった。彼が強い気持ちでやっていたので、私も応援したいと思いました。私のことを、自分にあまり執着がないと言ってくださるのだとすれば、そのことも大きいです。
── 今も現役でご活躍されていますが、応援という気持ちは、その頃からずっと変わらず?
飛田 はい。夫がいたから、仕事も育児もやれたというのもありますし、応援はしたいですね。
再びのバレエ教室

人生の機微を教えられたバレエから長らく遠ざかっていたが、4年前から、近所の初心者バレエ教室に通い始めたと言うので驚いた。
飛田 ジムもウォーキングも走るのも嫌い。でも体力をつけたいなと思っていた時、たまたま近所に、昔のバレエ友達が稽古場を開いて。おいでおいでって言うんで、何十年ぶりに通うことにしました。でも昔できてた基本のジャンプができなくてショックでね。
── そういうもんですか。昔すごく嗜んでいても。
飛田 そうなの、基本のジャンプってホラ、こういうの。
彼女は笑いながらすっくと立ち上がり、リビングでポーズを取り、跳んでみせた。それが音もしないしなやかな舞いのようで、目を奪われた。編集者、カメラマンと私の3人で思わず「わあっ」とため息が漏れる。
飛田 できないのはショックだったんだけど、教室は楽しくて。ああ私、クラシック音楽が流れているところで体を動かすのが好きかもしれないって思いましたね。夏は暑くて、ゆでダコみたいにしてやってます。汗かいて、全身運動で気持ちがいいの。これは続けようって思っています。
人生の黄昏時に入っていく

いつしか、窓の向こうの空はオレンジとグレーが混じり合っていた。
飛田さんの口からは、最後まで「切ない」という言葉が出なかった。意識して言わないのではなく、自然体で、出なかったのだと思う。
愛する娘には、一日でも早く独立してほしい。娘と一緒に旅をしたり、娘のひとり暮らしの部屋を訪ねたり。そんなことを早くしてみたい。やがてくる夫とふたり新しい日々が楽しみなの、と語る口調が朗らかで、こちらまで気持ちが明るくなった。
同時に、だからこそ私には、胸に迫るものもあった。人生にはままならないことがたくさんあると、10代からわかっていた人だからこそ。
40歳になったばかりだという写真家・メグミさんが、帰りの車でポツリと言った。
おふたりの話を聞けば聞くほど、私、なんだか切なくなって、撮りながら、うっときてしまいました。後半、飛田さんのお宅の窓から夕焼けが見えて、そのせいもあったのかな……。
メグミさんの言葉に、飛田さんと私の年齢はこれから、人生の黄昏時に入るんだなとふと思った。飛田さんは、人生の機微を教えてくれたバレエともう一度仲良くなっている。猫のように、あんなにしなやかに美しくジャンプしながら。
彼女は意識してないだろうけれど、人はそれぞれ自分なりのやり方で切なさを消化しながら人生を巡っているのだと思う。家族、友達、仕事やかつての仲間。誰かと支え合いながら。


長野県生まれ。編集プロダクションを経て1995年独立。著書に『男と女の台所』『ただしい暮らし、なんてなかった。』(平凡社)、『届かなかった手紙』(角川書店)、『あの人の宝物』(誠文堂新光社)、『新米母は各駅停車でだんだん本物の母になっていく』(大和書房)ほか。最新刊は『それでも食べて生きてゆく 東京の台所』(毎日新聞出版)。インスタグラムは@oodaira1027
大平さんのHP「暮らしの柄」
https://kurashi-no-gara.com
撮影:メグミ
感想を送る