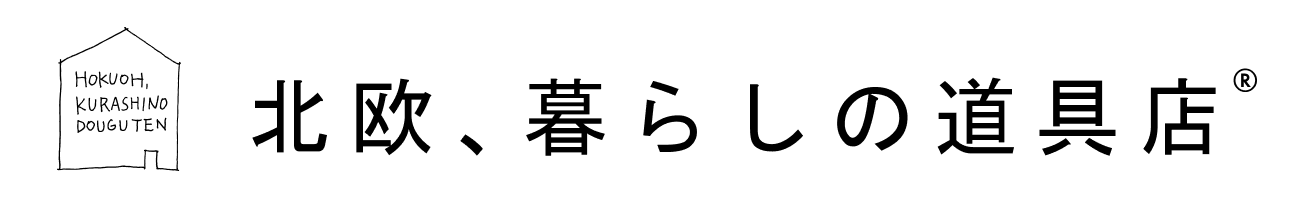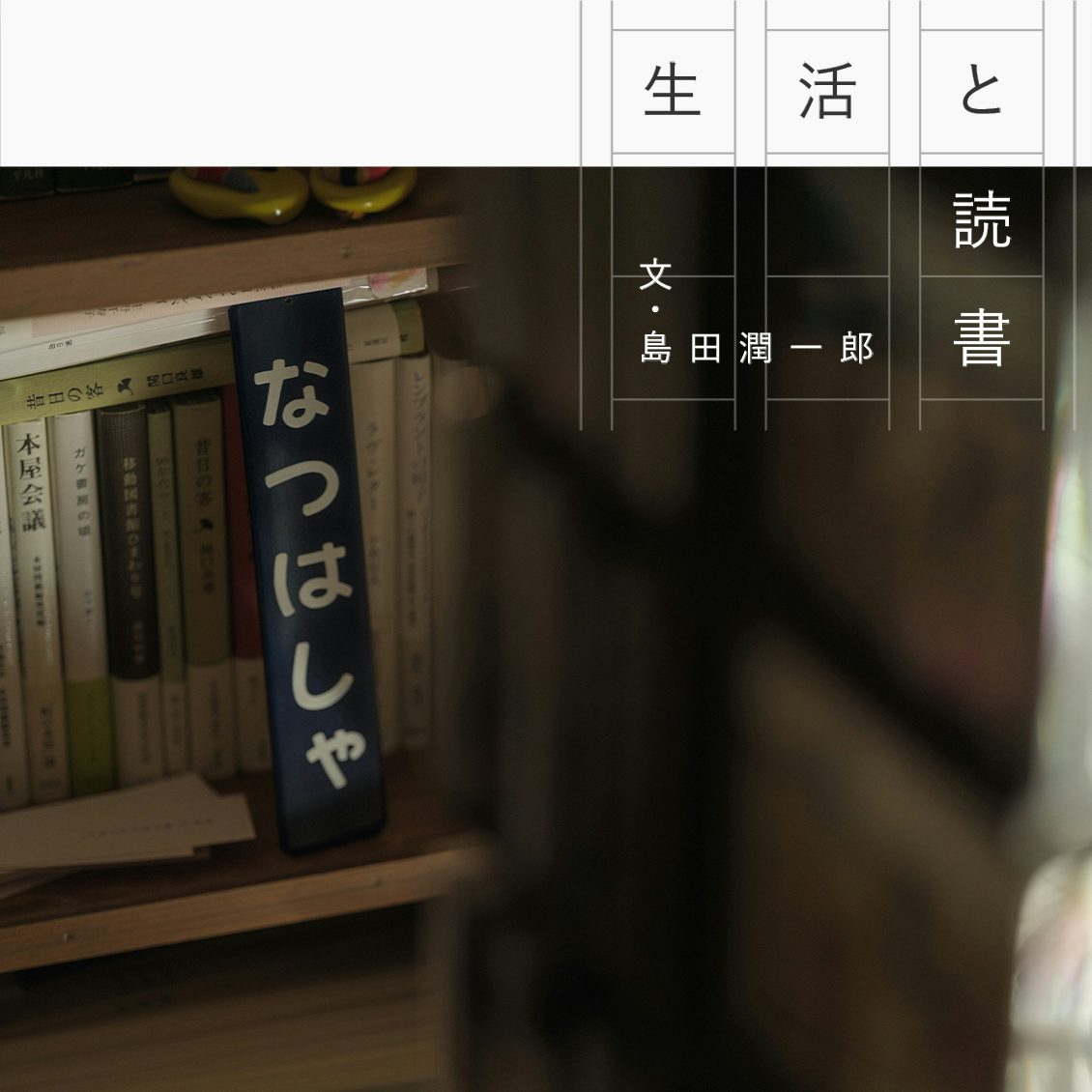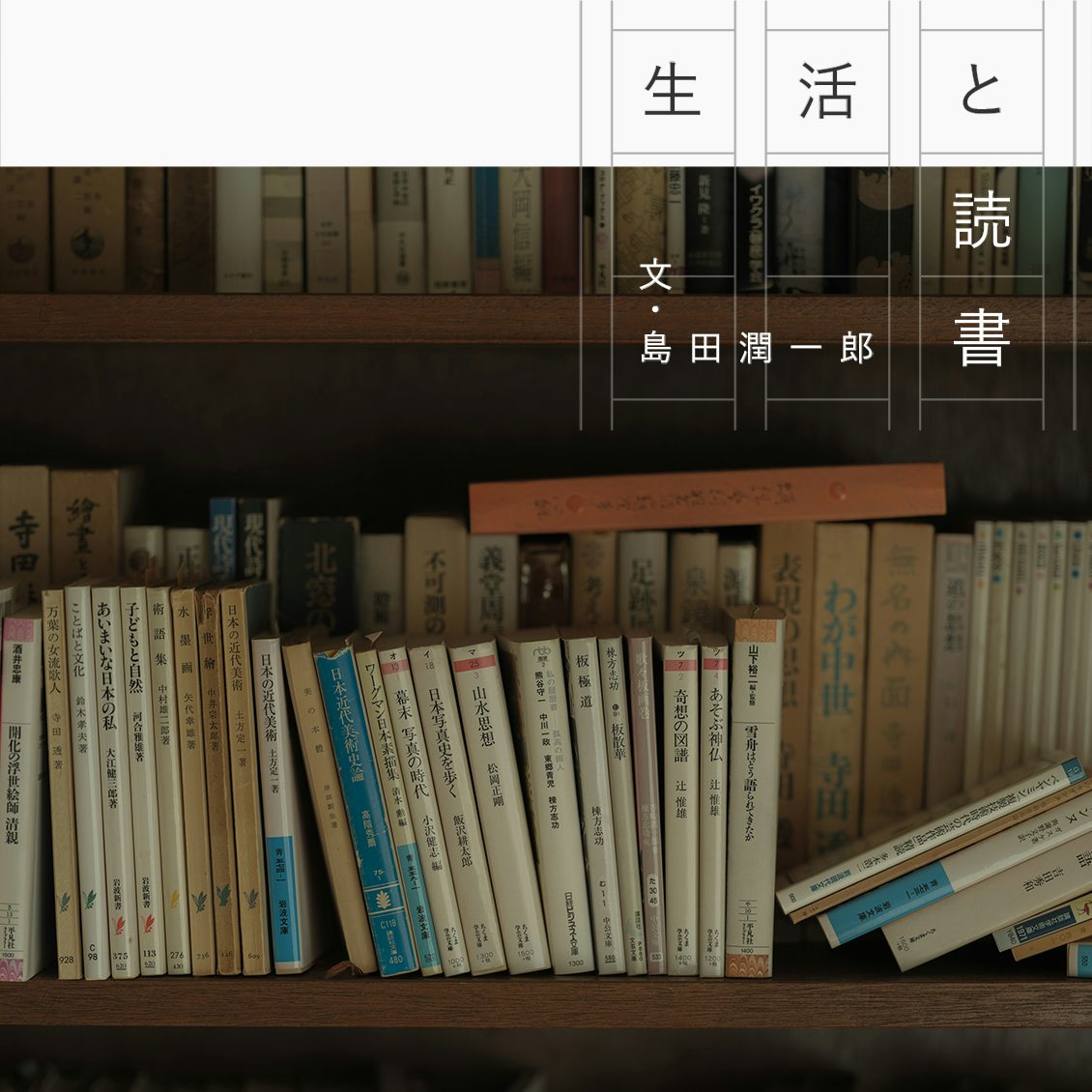夏葉社・島田潤一郎さんによる、「読書」がテーマのエッセイ。ページをめくるたび、自由や静けさ、ここではない別の世界を感じたり、もしくは物語の断片に人生を重ねたり、忘れられない記憶を呼び起こしたり。そんなたいせつな本や、言葉について綴ります。月一更新でお届け予定です
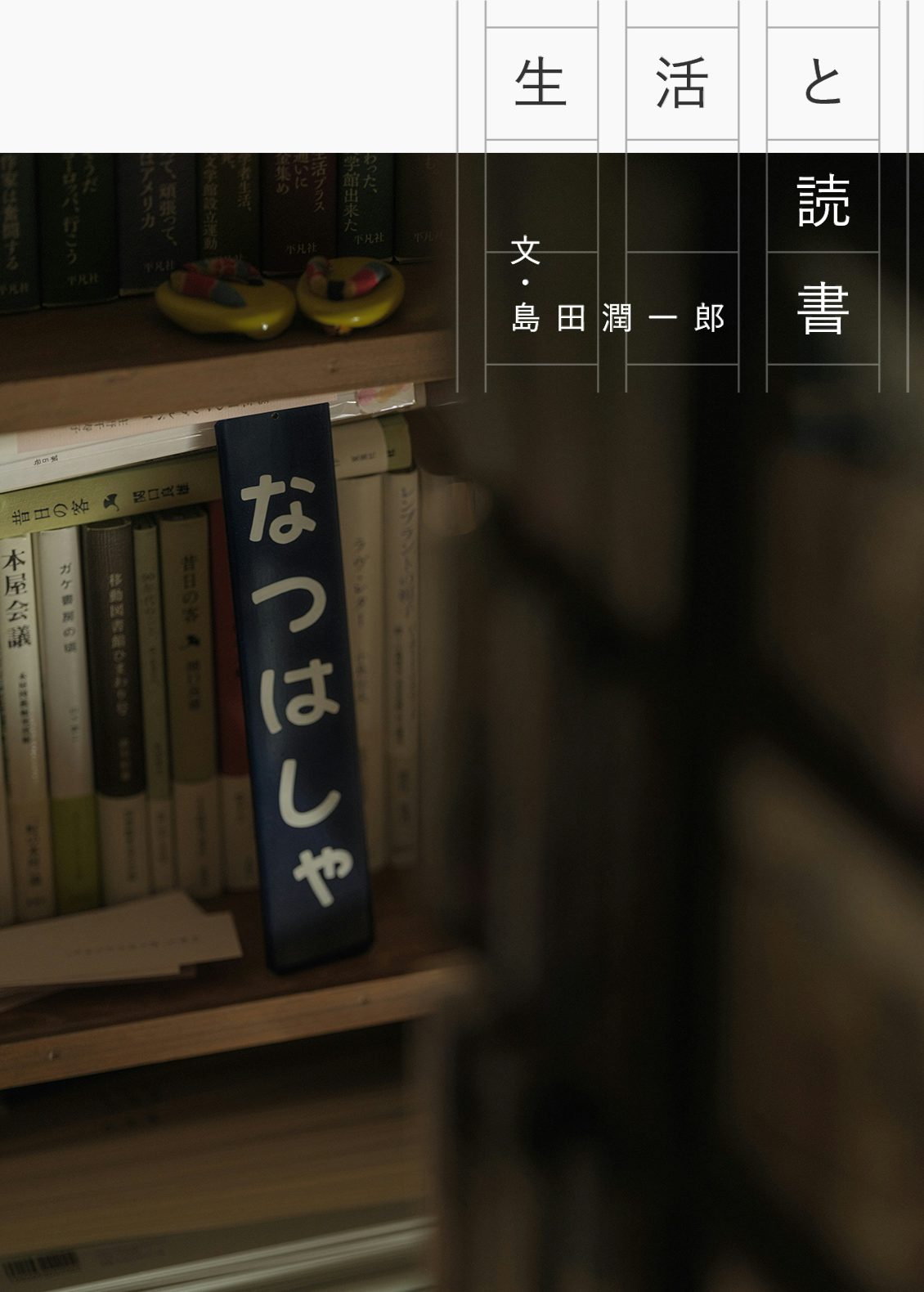
一冊の本が人生を救ってくれるということがあるのか、ぼくにはわかりません。ぼくはそうした経験をしたことがありませんし、ぼくのまわりにも、そのようなひとはいません。
でも、ヒントを与えてくれる本というのは驚くほどたくさんあり、そのなかのひとつの言葉、ひとつのフレーズが、暗く沈んだこころにあたたかな光をあたえます。
ぼくの場合は、若林一美先生の本のなかで紹介されていた一編の詩が、自分の進む道を照らす燈火となりました。
それはイギリスの神学者、ヘンリー・スコット・ホランドという神学者が残した詩で、
死はなんでもないものです。
私はただ
となりの部屋にそっと移っただけ
という印象的な3行からはじまります。
当時、ぼくは親しかった従兄を事故で亡くしたばかりで、この詩を何度も読み返し、息子をなくしたばかりの、ぼくの叔父と叔母にもプリントアウトして送りました。
いまの仕事に結びつくなにかを探ろうとすれば、このたった43行の詩を、本を片手で開きながらパソコンに打ち込んでいたときの充実した気持ち、そして、ワードで、なんとかこの詩を美しく見せたいと工夫していたときのことを思い出します。
ぼくは本こそ好きですが、自分で編集したり、本をつくったりしてみたいと思ったことは、それまで一度も考えたことはありませんでした。それはプロの仕事であり、自分は生涯、一読者でいたいと考えていたのです。
そうした気持ちが変わったのは、たんじゅんに、転職活動がうまくいかなかったからです。
ぼくが仕事を探していた2008年はリーマン・ショックの年であり、従兄が急逝した年でもありました。
当時の大学生の就職率を見ると、そこまで下振れはしていませんが(2009年3月卒業者で95.7%、前年より1.2%ダウン)、転職活動をしていたぼくのような30代の人間にとっては、強く不景気を感じさせる一年でした。
毎日、転職サイトを閲覧し、51社の中途採用に応募しましたが、面接の段階まで進めたのはわずか9社。
月額16万円の営業の正社員の仕事に応募し、書類で落ちたとき、もう転職活動はあきらめようと思いました。
すくなくとも、「正社員」という形で社会のなかに居場所を確保することはできないのだから、なにかほかの生き方を探すしかない、と自分なりに結論づけたのです。
§
そのころ、時代は大きく変わりつつありました。
2008年はアップルがiPhoneを発売した年でもあり、この便利な機器の登場によって、ひととひとのコミュニケーションも、町の姿も変わりはじめようとしていました。
もちろん、当時のぼくはそんなことを知りようもないですから、東京の自宅と、郷里の高知県の室戸と、そして行きつけのいくつかの本屋さんの三つの場所をぐるぐるとまわっていました。
ぼくは1976年生まれで、バブルが崩壊したといわれる91年のころは中学生です。浮かれていた時代の雰囲気はテレビをとおして知っていますが、そうした時代の恩恵を受けたことは、おそらくなかったように思います。
大学卒業のころは就職氷河期、そして転職をしようとしたらリーマン・ショックでした。
そうした長い下り坂の20年のなかで、支持されるカルチャーもだいぶ変わっていったような気がします。
ぼくがわかるのはせいぜい本のまわりだけですが、たとえば、ぼくが大学生のころ、プロレタリア文学を読むひとはひとりもいませんでした。私小説を読むひとも極端にすくなかったように思います。
そうした、貧しさとか、搾取とかいったモチーフにリアリティを感じたことはありませんでしたし、もっといえば、ダサいなあぐらいに思っていました。
でも、ぼくが職を求めて右往左往していたこの年、小林多喜二の『蟹工船』がブームとなり、年末には東京の日比谷公園に「年越し派遣村」ができました。
このころから(もっと前かもしれませんが)、本というものはひとびとの切実な願いを受け止める「なにか」に変わっていったように思います。
ぼくもまた、そんな時代のなかで、本をつくり、出版社をつくろうと思いはじめます。
つくろうとしたのは、あの一編の詩の本でした。


『さよならのあとで』
ヘンリー・スコット・ホランド 著、 高橋和枝 絵 夏葉社
このヘンリー・スコット・ホランドの詩が掲載されていたのは、若林一美先生の『自殺した子どもの親たち』(青弓社)という本です。そのようにして愛息を失ったお父さまがご自身の手で詩を訳されていました。ぼくは家族と突然別れなければならなくなったひとたちに、この詩を届けたいと思い、夏葉社という出版社を立ち上げました。2009年9月のことです。
文/島田潤一郎
1976年、高知県生まれ。東京育ち。日本大学商学部会計学科卒業。アルバイトや派遣社員をしながら小説家を目指していたが、2009年に出版社「夏葉社」をひとりで設立。著書に『あしたから出版社』(ちくま文庫)、『古くてあたらしい仕事』(新潮文庫)、『父と子の絆』(アルテスパブリッシング)、『電車のなかで本を読む』(青春出版社)、『長い読書』(みすず書房)など
https://natsuhasha.com
写真/鍵岡龍門
2006年よりフリーフォトグラファー活動を開始。印象に寄り添うような写真を得意とし、雑誌や広告をはじめ、多数の媒体で活躍。場所とひと、物とひとを主題として撮影をする。