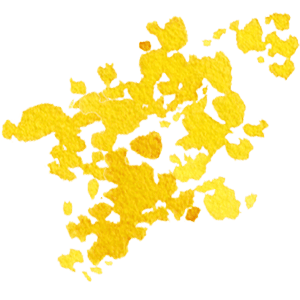「この歳になって」とか、「もうこんな歳なのに」とか、いつからか口にしてしまって、自分をなぐさめてみたり、だましてしまったりすることがあります。
確かに年齢を理由にできないことはあり得ます。けれども、50歳半ばを迎える一田憲子さんは新しい試みを続け、以前よりも強い精力さえ感じさせるのです。
いったい何が転機になったのでしょう。それを聞くうちに、「この歳になって」を口にするのは、なんだか損をしているような気持ちになってきました。
30代を駆け抜け、40代で味わう挫折、そして50代の再出発。
そこには、心の奥底に眠る「自信」に気づけた、大切な「振り返り」があったのです。
「四十にして惑う」のは当たり前?

一田さんが20代で飛び込んだ、ライターや編集者としての仕事。その向き合い方は、年代によって移り変わってきたといいます。
一田さん:
「29歳で独立して、30代は書くという好きな仕事はしていたけれども、毎日が不安で、がむしゃらな修行の日々。40歳を過ぎて、『暮らしのおへそ』を立ち上げてからは、少しずつ自分の好きなことが書けるようになってきました。
だから、私にとっては“書くという仕事”も、30代と40代では全く違うんですよ」
これまで、当店でも『40歳の、前とあと。』という連載で、取材を重ねてきた一田さん。まさに、本人にもその前後を意識する瞬間がありました。
一田さん:
「孔子の言葉で『四十にして惑わず』と聞くけれど、惑うんですよ、ぜんぜん!(笑)
その惑いの原因は、足を止めて考えられるようになったからだと思うんです。考える暇もなく走ってきた日々に、ふっと考える余裕ができるのが、40歳ごろ。
だから、惑ってしまうというより、惑えるようになった年代。連載でお話を聞いたみなさんも、同じような感覚を持たれていましたね」
出版社から泣きながら帰った、あの日

『暮らしのおへそ』をはじめ、好きな「暮らし」をテーマにした執筆を仕事の中心に据えられるようになり、数年が経ちました。初めての自著も出せ、ようやくこれから、というとき。
……ところが、ある依頼によって、一田さんは文章や姿勢、さらには性格にまで、新たな「問い」を突きつけられることになるのです。
一田さん:
「初めての本を刊行してしばらくたったとき、久しぶりに出版社から著書のご依頼をいただいたんです。取材も進めて、書きはじめたものを編集者に見てもらったら、『一田さん、取材じゃなくて、分析で書いてください』って。
私はずっと、取材で聞いてきたことが伝わるように書いてきました。でも、編集者からは『それを噛みくだいて、自分の言葉として出さないと、著者としての本にはなりません』とダメ出しされてしまったんです。
取材の文章は書ける。けれど、自分の文章を書くことが、できていなかったんです。結局、その本はお蔵入り。それが決まったときは、出版社から泣きながら帰って……」
30代で磨いた文章、40代で形になってきた仕事をぐるりと返されるような体験。次なるステージへ行きたいと考えていたはずの46歳で味わった挫折に、一田さんは「これまで自らの意見をちゃんと伝えてこなかった」と思い返します。
それは原稿に限りませんでした。「私はこう思う」と言い切ることへのためらい。
いつも、「あの人もこの人も言っているから、私はこう思います」や、「私はこう思いますけれど、こんな考えもあるかもしれません」と、予防線を張っていたことに気づくのです。
「私なんて」の口癖を、乗り越えられた変化

一田さんにとっての予防線は、自分を守る鎧でした。
一田さん:
「たとえば、『暮らしのおへそ』が刷りあがったときも、『いいよね!』と話し合うスタッフたちを横目に、私は『もうちょっとできたはず』みたいに、マイナスなことを考えているくらい。
でも、後ろ向きなことを言うのは、傷つきたくなかったからなんですよ。もし、そこで私も『いいよね!』と言い合って、売れ行きが芳しくないと傷ついてしまう。そうならないための予行演習として、マイナスなことを言って予防線を張っていたんです。
悲観主義で、いつも不安ばかり。もともとポジティブになれない性格でしたしね」
「私なんて」という口癖も、そのひとつ。長らく無意識にあった行動たちを、一田さんは挫折をきっかけに振り返り始めます。
それを変える後押しとなったのは、ふと見つめ直した「年齢」でした。
一田さん:
「50歳って、すごく重い年齢で。80歳まで生きるとしたら、あと30年しかないことに愕然としたんです。そもそも80歳まで働けないかもしれないじゃないですか。
たったそれだけの時間しかないのに、『私なんて』と言ってる場合じゃない!って思ったんですよ。それは、とっても大きな変化でした。
その瞬間に、これまでのいろんなことが結びついて、50歳から後の行動に表れてきたんです。自分発信で言うことの練習をしなくちゃ、とも思えるようになって、ウェブサイトを立ち上げようとも決められました」
2016年11月、一田憲子さんは編集長として「外の音、内の香(そとのね、うちのか)」を公開。
うまく運営できるのか自信はないままでしたが、「お金を稼ぐ仕組みがわかってから……なんて考えていたら、何年先になるのかわからない。立ち上げて、走りながら考えるしかない!」と踏み切ったのです。
言葉には出せないけれど、実は自信が眠っていた

「外の音、内の香」の立ち上げは、一田さんにはっきりと気持ちの変化をもたらしました。編集長は自分で、作るのも自分。これまでのように雑誌から依頼を受ける仕事ではなく、どこまでも主役の舞台です。
ずっと自信がなかった、自分の文章を書く日々。記事を作るごとに、一田さんにはさまざまなことを「自分の言葉」で語れるようになっていく感覚が積もっていきます。やがて、出版社から泣き帰ったあの日を乗り越える一冊も、世に出すことができました。
一田さん:
「日々の暮らしをそのまま書いたのが『丁寧に暮らしている暇はないけれど。』です。
自分の暮らしを書くのだから、合っているか、間違っているか、誰かに何かを言われるか……なんて気にしていたら、モヤっとした書き方にしかなりません。腹をくくって、『私はこうです!』と伝えられた、初めての本になったと思います」
この経験もあり、一田さんは心の奥底で眠っていた、まだ見ぬ私に出会います。
一田さん:
「言葉には出せないけれど、私は案外、心のいちばん奥では『私はきっとやれる』と信じていたのかもしれない、と。
それが傷つくのが嫌だから、いろいろな布石を置いてきました。でも、『外の音、内の香』のように、自ら一歩踏み出したことに加えて、今までやってきたことをさかのぼっても、『その時々で、私はがんばってきた』と思えたんです」
常に、今の私にいちばん興味がある

50歳を超え、振り返って気づけた、ほんとうの自分の姿。その瞬間ごとにはわからなかった出来事の一つひとつが点となり、今になって線につながったような心象でしょうか。
「でも、出来事の時系列もあやふやですし、計画してここまで来られたわけではちっともないですよ」と一田さんは笑います。
ただ、お話を聞くと、立ち止まって振り返ることの大切さを、ひしひしと感じます。それは一田さんが取材を続けた「40歳の区切り」だけでなく、きっと、いくつのときにも。
一田さん:
「私は常に、今の私に、いちばん興味があるんです。だから、振り返るときには、私が今こうなっているのは、過去にこういうことがあったからだ、と考えます。
足下を確認するために、これまでをたどる感じです。その過程が理解できると、今についてわかることが増えますから。
振り返りがあって今があるんじゃなくて、今があるから振り返れるんですよね」
新しい発見をしたら、振り返られる

では、振り返るきっかけは、いつ持つべきなのでしょうか(いえ、ここで『べき』なんて言わずに、いつでもが好機なのだとは思いますけれど)。
一田さんは、取材で膝を打つ瞬間だといいます。
一田さん:
「取材で誰かにお会いすると、『はぁー!そうか!』って感じることがあります。その瞬間に、今までモヤモヤしていたこととの違いに気づける。そこから過去をたどれば、違いが起きてしまった理由も考えられるはずです。
だから、振り返るときって、新しい発見をしたときなんだと思います」
一田さんにとって大切な「発見」の瞬間。記事後編では、それを鍵に、お話をさらに聞きました。おしゃれの達人から知った「失敗の大切さ」や、ライター塾を始めてわかったこと。さらに「暮らし」から発見するための習慣まで……。
「終わったらごはんにしましょう!」という一田さんのうれしいお誘いに、ぐう、と鳴りそうなお腹をがまんしていたのは、ここだけのひみつです。ごはんは、最後に。
(つづく)
【写真】中川正子
もくじ


ライター 一田憲子
編集者、ライター フリーライターとして女性誌や単行本の執筆などで活躍。「暮らしのおへそ」「大人になったら着たい服」(共に主婦と生活社)では企画から編集、執筆までを手がける。全国を飛び回り、著名人から一般人まで、多くの取材を行っている。ウェブサイト「外の音、内の香」http://ichidanoriko.com/

ライター 長谷川賢人
1986年生まれの編集者/ライター。