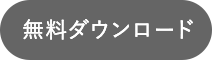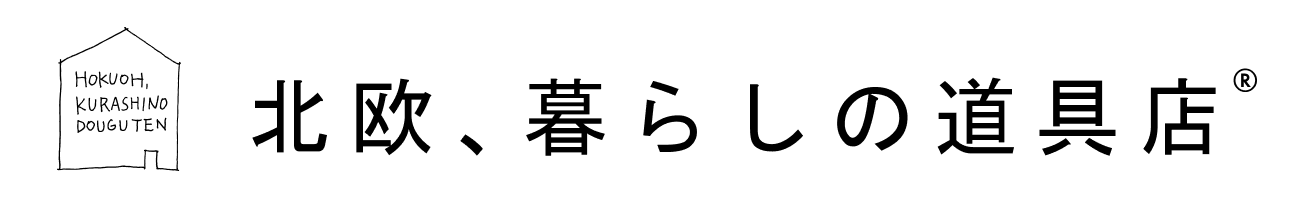かつお節や昆布、煮干しを使ってだしをとる暮らしに憧れます。一杯のお味噌汁からたつ湯気、思わずお腹が空いてくるような、やさしくて温かい、”家庭料理” の香り。
そのおいしさはもちろん、料理に手をかけ、時間をかけることは “丁寧な暮らし” の象徴のようで、だから憧れるのかもしれません。
でも、現実の日々は「今日のごはんをどうまかなうか」で精一杯。できるだけ手早く、お腹が満たせる料理を優先していると、だしをとることは、まだ理想。今の暮らしではなかなかハードルが高いことに感じていました。
一杯のお味噌汁から、手軽にだしがとれたら

それでも、たとえば一杯のお味噌汁から、だしのある暮らしをはじめてみたい。そんなときに知ったのが、鰹節屋・だし屋としておなじみの「ヤマキ」が作る、鍋に入れて煮出すだけの「だしパック」。
原材料は「かつお、いわし煮干、昆布」のみ。余計なものが入らない、本格的なだしパックです。
ただ気になるのは、日々の料理で使いこなせるかどうか。市販のだしの素や液体だしのように、入れるだけで料理が出来上がる手軽さに比べると、調味されていないシンプルな「だし」を使って料理の味を決めることにハードルを感じる方もいるかもしれません。
暮らしへの取り入れ方を教わりに、今回は料理家のスズキエミさんを訪ねました。
(この記事は、ヤマキ「だしパック」の提供でお届けする広告コンテンツです)
毎日の料理を楽にしたくて、だしをとり始めました

素材の味を生かした、シンプルでしみじみおいしい家庭料理を作るスズキさん。夫と中学2年生の息子の3人で暮らしています。
スズキさんの日々の料理のベースにあるのは、昆布とにぼしの合わせだし。ただ、だしをとり始めた理由は意外にも「日々の料理を楽にするため」だったとか。
スズキさん:
「10年前、息子が保育園に通い始めたのを機にだしをとるようになりました。朝が慌ただしくなって、朝のメニューを『味噌汁とごはん』に固定することに。品数を減らすぶん、満足感のある味にしたいと考えたのがきっかけです」
朝起きて、白湯を沸かして飲む10分の間に昆布とにぼしのだしをとる。そんな習慣がルーティンになって早10年、今も朝はごはんに味噌汁が定番だといいます。

今回使ってみていただいた、「鰹節屋のだしパック」。いつものだと比べていかがでしたか?
スズキさん:
「まず、香りが豊かで驚きました。火にかけて数分で、かつおのいい香りが広がって。普段のわが家のだしよりもだいぶリッチな香りなので、学校から帰ってきた息子が『今日はごちそうなの?』と聞いてきたほどです」
 ▲3種のかつお節、こんぶ、いわし煮干が入ったパックの中身。かつお節は、うま味の強い「氷温®熟成法かつお節」、燻した香りの強い荒節、まろやかな香りの荒節の3種類を使用
▲3種のかつお節、こんぶ、いわし煮干が入ったパックの中身。かつお節は、うま味の強い「氷温®熟成法かつお節」、燻した香りの強い荒節、まろやかな香りの荒節の3種類を使用
老舗かつお節屋として創業したヤマキが、こだわりのかつお節3種をブレンドして作っただしパック。家庭で、誰でも手軽に本格的なだしがとれるよう、配合にも試行錯誤を重ねています。
一番の特徴は、原材料のシンプルさ。「かつおぶし、いわし煮干、こんぶ」のみ。子どもから大人まで安心して日々食べられるよう、余計な調味料は加えず、100%天然素材にこだわって作られています。
使って実感した「続けたくなる」理由
 ▲1袋、8パック入りで486円(税込)。1パックで1家族分(3〜4人)の味噌汁が作れます
▲1袋、8パック入りで486円(税込)。1パックで1家族分(3〜4人)の味噌汁が作れます
スズキさん:
「それに、なにより手軽でした。鍋に入れて煮出すだけ、というのは格段に楽ですね。市販のだしの素や液体だしと同じくらい気軽に使えて、これなら忙しい方でも、日々の料理に組み込みやすいのではないでしょうか。
これまでは、朝に昆布を水に浸し、煮干の下処理をして1日分のだしをとっていましたが、だしパックならその手間がいらないので、料理をするタイミングで毎食ごとにだしをとるように。その都度、いい香りが楽しめます。
香りのいいだしをとるには、手間や時間はもちろん、使う素材もいいものでなければならないので、案外コストもかかるもの。総じて考えると、むしろこのだしパックはとてもリーズナブルだと感じました」

スズキさん:
「何より反応がよかったのは食べざかりの息子。だしの風味が豊かだと、普段と味付けの具合は変わらなくても、料理の食べごたえが増すようです。
だしパック自体に調味がされていないので、料理の塩分も、家族好みの味に調整できる余白があっていいですね」
調味がされてないから、色々な料理に使える汎用性があるとスズキさん。そこで今回は、味噌汁以外にだしパックを活用するおすすめのレシピを伺いました。
旬の野菜を漬け込むだけ。
手軽な常備菜「野菜のだし浸し」

材料(2〜3人分)
「鰹節屋のだしパック」…1袋
水…300ml(熱湯150ml、水150ml)
塩…小さじ1
油…大さじ1
【好みの野菜(全体で500gほど)】
※今回の場合
にんじん…小1本
玉ねぎ…1/2個
小松菜などの青菜…1/3束
トマト…5〜6粒
を使用しています。
作り方
1.27cmx16cmの耐熱の保存容器にだしパックを入れ、熱湯150mlを注ぎ、塩を入れてかき混ぜる。10分ほどおいてだし汁がでてきたら、残りの水150mlを注ぎ、全体になじませる。

スズキさん:
「はじめに熱い湯でだしを抽出してから、水を加えてだし汁の温度を下げます。焼き立て熱々の野菜を冷たいだし汁に漬けることで、だしが浸透しやすくなります」
2.にんじんは縦6等分に切り、玉ねぎは1cm厚さの輪切り、小松菜は茎と葉で2等分に切る。
3.フライパンに油を中弱火で熱し、火が通りにくいにんじん、小松菜の茎、玉ねぎ、小松菜の葉の順に、焦げ目がつくまでじっくり焼きつける。

スズキさん:
「野菜は焼くときに『できるだけ触らない』ことが大切です。動かさないで焼きつけると、余計な水分が出ず、ぎゅっと味が締まります。
それから、火を通しすぎないのもコツ。にんじんなら箸が通る程度、柔らかくしすぎず食感が残るうちに火からあげると、瑞々しい仕上がりになります」

火が通ったものから順に、熱いうちに②の液に浸す。冷蔵で半日程度置いて味が染みれば、できあがり。
 ▲生野菜はそのまま漬けるのがおすすめ。トマトはさっと湯むきすると、食感がよくなります
▲生野菜はそのまま漬けるのがおすすめ。トマトはさっと湯むきすると、食感がよくなります
スズキさん:
「かつお節の香りがとても豊かなので、調味は塩のみでOK。焼いた野菜のコクが加われば、シンプルなのにしっかり食べごたえのあるおかずになります。
野菜は基本的になんでもOK。『焼き』だけでなく、ゆで野菜や、生で食べられる野菜ならそのまま漬けてもおいしいです」
「鰹節屋のだしパック」の詳細はこちら「だし」は、日々の料理をラクにするもの

できあがった焼き浸しの、しみじみおいしいこと。だしパックの煮出し汁に漬けておくだけなのに、なんだかとても丁寧に作られた料理をいただいているような、心も満たされる安心感がありました。
スズキさん:
「『だし』のよさって、そういうところだと思います。手が込んだ料理ではなくても、ほっとする味わいになる。だから私は「だし」って面倒なものではなくて、むしろ日々の料理をラクにしてくれるものだと思うんです。
毎日の料理は、いかに無理なく続けられるかが大事。わが家も夕食は、ごはんと汁物にメイン1品が基本です。でも、そこにだしが効いているだけで、しっかり満足感があります。
それに、だしがふわりと香る瞬間って幸せですよね。かつおの香りが台所に漂っていると、それだけで料理をするのが楽しくなるように感じます」
 ▲春雨とねぎで作った中華スープも、ベースはだしで
▲春雨とねぎで作った中華スープも、ベースはだしで
和食に限らず、使い方は自由。スズキさんも中華スープや洋風のポタージュ、ジャンルにとらわれずいろいろな料理のベースに同じだしを使っています。
スズキさん:
「仕上げにごま油やオリーブオイルを加えれば、それだけで中華風、洋風に変わります。
味のない『だし』を使うと、調味を自分でしなければならず不安だという方もいるかもしれませんが、完璧な味付けに仕上げなくてもいいと私は思っています。
お皿によそって食べるときに、多少薄ければ塩を足す。卓上調味でそれぞれの好みに調整できればいい。そのくらいおおらかなのが、日々の料理だと私は思います」

取材時、キッチンにお邪魔するとふわりと漂っただしの香り。それだけで場の空気がふんわりまるくなり、なんだかお腹が空いてきて、スズキさんのいう「だし」の魅力が、実感できました。
「だしをとる」ということに漠然とした憧れをもつことは、知らず知らずに、料理への見方を狭めていたのかもしれません。だしはハードルの高い素材ではなくて、むしろ肩の力を抜いてくれるもの。ぴたりと正確な味を作るより、大切なのは自分や家族がほっとできる味を作ること。
まずはこのだしパックから、「だし」に頼って力を抜いてみようかな。スズキさんの温かい味噌汁をいただきながら、そう思いました。
「鰹節屋のだしパック」の詳細はこちら▼よろしければアンケートのご協力をお願いいたします。
【写真】上原未嗣


コマツエミ
料理家 / 「anco」店主。夫と中学生の息子との3人暮らし。素材の持ち味を生かし、日本の四季を身近に感じられるようなごはん作りを提案する。今年、都内であんことコーヒーのお店「anco」をオープン。
Instagram: anco.tokyo
感想を送る