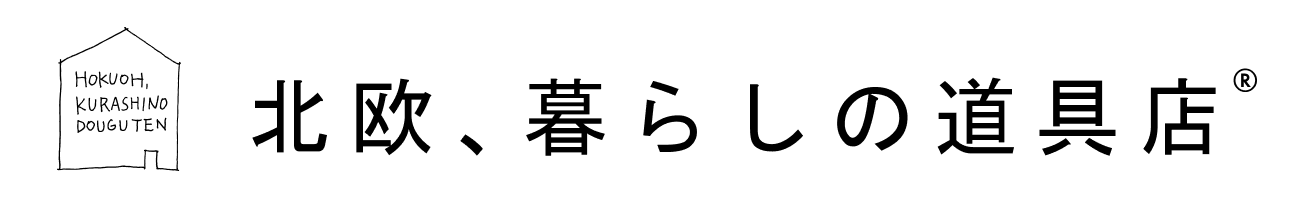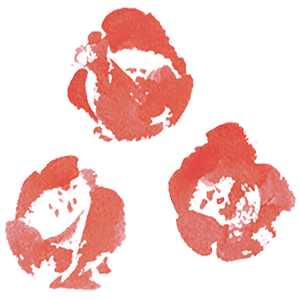もうすぐ梅雨がやってきますね。
これまで使っていた折りたたみ傘が少し古くなってきたので、雨の季節に向けて新調することにしました。
迎えたのは、オリジナルの折りたたみ傘。
同じく当店で取り扱いのある「BLUNDSTONE」のローカットブーツと合わせて、雨の日の頼れる存在になっているこの傘について、今日はご紹介したいと思います。
雨の日の景色が明るくなりました


まず惹かれたのは、雨の日の気分も晴れやかにしてくれそうなこの柄。
空から差し込む光の線をイメージしているという、オリジナルのテキスタイルがなんともかわいくて。
届いてみると実物はなんだかより素敵。じっくり見つめたあと、次の雨を楽しみにスタンバイさせていました。


初めて使った日、窓ガラスに映る自分の姿をふと見ると、暗い色でまとまりがちな雨の日の装いに、明るい色が差し込んでいい感じ。
洋服やバッグなど、身につけるものはどうしてもワードローブに合うか?を考えてしまいますが、折りたたみ傘はどちらかというと、スマホケースやエコバッグを選ぶときみたいに自由な気持ちで、好きなデザインを選べて、気負いなく使えるのが楽しいです。


それから、当たり前のことかもしれませんが、この傘を使い始めてから気づいたことがあります。
それは傘の色や柄って、差しているとき中ずっと、視界のすみで “見ている” んだなということ。
無意識にでもお気に入りのデザインが目に入っていると気分も上向きになりますし、曇り空に溶け込むやさしいグレーと差し色のレモンイエローは、傘の中もふわっと明るくしてくれるんです。
今まで遮光用に内側が黒く加工されたものを使っていたので、なんだか雨の日の景色が前よりも明るくなったような気がして、嬉しくなりました。


日傘としても使ってみたのですが、傘の中を明るくしてくれる分、晴雨兼用ではあるものの、やや眩しいときもありました。
最近のきびしい夏の日差しの中では眩しさを感じるかもしれませんが、紫外線は90%以上カットしてくれるので安心です。


わずかコーヒー1杯分の重さ。軽いのに広々です


さて、見た目の話ばかりしてしまいましたが、使い心地のよさについてもお伝えしたいです。
まずはこの軽さ。わずか220gと、長時間さしていても手が疲れず、持ち運びにも負担のない軽やかさです。
風もあるような大雨の日にはまだ使ったことがないのですが、芯がしっかりしているので、今のところ頼りなさを感じることもありません。


それでいて、開いた時の直径は97cmと、折りたたみ傘としては広々した大きさ。
通勤中、PCが入ったリュックが濡れないかどうか?も気になるポイントなのですが、少し後ろめに持てばきちんとカバーしてくれました。




▲仕舞うときは下に向かって捻るようにして巻くときれいに畳めました
ざっくりしまって、スッと取り出せます


それからもう一つ、便利なのがこのカバー。写真のように、スナップボタンを外すと口の広いバッグのような形になるんです。
折りたたみ傘って実は本体と同じくらい、カバーの仕様が使い心地に関わってくると思うのですが、これは仕舞いやすくてかさばらないのでとても重宝しています。


例えば、駅やショッピングセンターなど、人が多く入り口で立ち止まれない時。
傘を閉じたら、ひとまず広げたカバーにザクっと入れて。そのあと周りに人が少なくなったタイミングで落ち着いて仕舞えます。
荷物が多い日や、傘をしまったらすぐICカードを出して……と手元がバタつく瞬間、こんなふうにワンクッションおける場所があると助かるんです。
それから一度閉じてすぐにまた使う時も、取り出しがスムーズ。
持ち手があり手首にかけられるので、スマホやお財布を取り出したいときも手が空いて便利です。


カバーは防水素材ではありませんが、個人的には多少の雨であれば、水が染みてくるのもあまり気になりません。
取り出しやすく、もし雨が染みても中身が濡れないよう、私はリュックの外ポケットを定位置にしています。


この傘、使っていると何人かのスタッフに「私も愛用しています」と声をかけられました。
天気がイマイチでも、気分は上向きでいるための “雨の日の味方” として、私もこの傘と一緒に梅雨を乗り切りたいと思います。
感想を送る