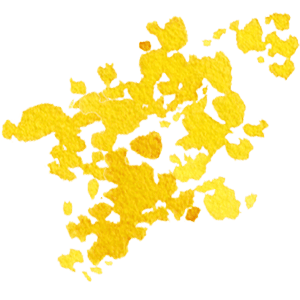文 スタッフ長谷川、写真 クラシコム
文 スタッフ長谷川、写真 クラシコム
編集者・ライターの一田憲子さんによる、特別な勉強会。
残暑がすぎ、クラシコムのオフィスも秋の涼しさに包まれた、ある夜のこと。オフィスの片隅に設けた「特設ステージ」は、静かな熱気でいっぱいでした。
企画から編集までを手がける情報誌『暮らしのおへそ』をはじめ、数々の女性誌を中心に活躍される編集者・ライターの一田憲子さんにお願いして、私たちのために「編集勉強会」を開いていただいたのです。
一田さんは、当店の特集「フィットする暮らしのつくり方」にご登場くださり、また店長佐藤を『暮らしのおへそ』の18号で取り上げていただくなど、以前より親交がありました。
日々「読みもの」をお届けしている私たちは、悩んだり試したりの連続です。どうすれば読みやすくて面白いのか、お客さまに共感していただけるのか……もっと良いものをつくるためのヒントを一田さんから伺える機会に、そわそわと夜を迎えました。
取材やインタビューのコツに、「編集のチカラ/言葉のチカラが上がる練習方法」まで。仕事だけでなく、上司と部下の間柄だったり、家族との会話だったり、誰かに何かを伝えるときに応用できそうです。
当日の様子と教わったことを今日と明日の2日にかけて、まとめていきます。
オフィスの一角でも、イベントっぽさを。
当日は、クラシコムのオフィスをアレンジしてステージに。「空気がカタいと一田さんが(私たちも!)話しにくいかな?」と軽食やお酒も用意して、リラックスした雰囲気をつくるようにしました。

ソファのすぐそばに大きな花を置いてみたら、「どこかで見たことある…“徹子の部屋”みたい!」なんて、アレコレ言い合ってサイズを微調整。
普段からオフィスで使っている家具ばかりですが、ソファの置き方や照明の当たり具合を工夫して、「トークイベントっぽさ」が演出できたかなと思います。
一田さんでも、40歳までは無我夢中。
一田憲子さんが編集者・ライターとして独立されたのは29歳のとき。関西の大学を卒業後、商社勤務を経て、東京の編集プロダクションへ。仕事に慣れてきた頃に「好きなジャンルの仕事がしたい」と、主婦と生活社『美しい部屋』の編集部にアポなし電話。提案した企画が実を結び、暮らしやライフスタイルの記事を手掛けるようになります。ただ、最初は書き直しばかりだったとか……。
一田憲子さん:
「当時は原稿用紙に手書きで、終電のギリギリまで直して、その場で編集長がチェック。見せて、直して、くたくたになって帰るみたいな日々でした。そのときに『写真で見えることなんて書くな! 見えないところを書くのがライターだ』とも教わりましたね。
フリーになったのは29歳のとき。でも、40歳手前までは無我夢中でした。それでも続けてきたのは、書くことが好きだったから。『あぁ、これが書きたかったんだよな』って思える原稿が仕上がった時の快感に助けられていました。ライターは書くだけでなく“人に会う”のも仕事だから、それも楽しかったですしね」
その後、『オレンジページ』『LEE』『メイプル』などでも仕事をするようになり、その活躍は現在までつながっていきます(このお話は一田憲子さんの著書『「私らしく」働くこと』で深く語られていますね)。

店長佐藤が『暮らしのおへそ』を手にした日のこと。
ある時、一田さんは引っ越しという環境の変化があったのに、自らの習慣をうまくチェンジできないもどかしさを感じます。「もしかしたら、人の暮らしは習慣の積み重ねからできているのかも。習慣をひとつ変えてみたら、人生も暮らしも変わるかな?」と考え、その体験をもとに『暮らしのおへそ』の企画がスタート。
店長佐藤は、第1号を手にした時のことをよく覚えているのだとか。

店長佐藤:
「当時、暮らしに関する本をよく読んでいたんですが驚きました。女優の夏木マリさん、当時は主婦枠で内田彩乃さん、そしてバレリーナの草刈民代さんまでを“おへそ”という編集で束ねるなんて!」
一田憲子さん:
「どんな人でも、帰ったら何かをするとか、シャワーをいつ浴びるとか、暮らしの習慣はそれぞれ持っていますよね。だから、習慣から生き方を探るなら、企画は無限大だなって思ったんですよ。それに、その習慣を読者が取り入れられたりもしますよね。女優になれと言われたら難しいけれど、女優さんがやっている習慣なら真似できる。それを足がかりにして、明日や生き方が変わるかもしれないですから」
『暮らしのおへそ』はシリーズ化し、創刊10周年を迎えます。現在でも発刊するたびに反省会をして、特集のバランスや記事のつくり方などを見直しているそう。その丁寧な制作スタイルが、長年愛されている秘訣なのかもしれませんね。
暮らしの中から生まれた「はてな」が企画になる。
ここで、スタッフ津田が「『暮らしのおへそ』では企画や編集の会議をどのように進めていますか」と質問。津田は「北欧、暮らしの道具店」の読みもの企画の全般を見ている立場だけに、他の編集部のやり方や、長く愛される雑誌の企画術が知りたいようでした。

すると、「企画会議はしていないんですよ」と一田さん。会議らしい会議よりも、「仕事の話をするつもりも全然ないくらい、何かのついでに話すとアイデアが出ることが多い」のだそう。
一田憲子さん:
「ネタのためにネタを出すと限界があるんです。それよりも、暮らしの中から生まれた“はてな”をいかに引っ張りだすか、ですね。
私も若い頃は本屋さんに行ったり、出来たばかりのお店を訪れたり、ネタ探しはしていましたよ。でも、ネタっていう観点だけで物事や日々を見ていると、だんだん疲れて消耗しちゃう。そこに感動があれば、どんなに忙しい時でも疲れないんですよね」
これには津田も「ネタがないって探すんじゃなくて、まずは毎日をしっかり、感動することで満たせばいいんだ」と納得したようです。
「良い体験や経験」こそが、 文章を磨いてくれる。
この「感動を大切にした体験や経験」は企画だけでなく、文章の磨き方にまでつながっています。
スタッフ青木や店長佐藤が「筆が進まないときに自分といかに向き合いますか。自分の文章がいつも似てしまっていると感じることはありませんか」と聞くと、一田さんも「ぴったりくる一言」を絞り出すために苦労していると答えてくれました。

一田憲子さん:
「筆が進まないときもありますよ。私は『暮らしのおへそ』の取材をしたら、設計図もつくらず、何も考えずにゼロから書くんですね。効率は悪いんですけど、“文章を書いている私”が、文章を書きながら気づけることがあるんです。『この人の真実を、言葉を編み出しながら探す』という感じです。
自分らしい文章って、ありますよね。私も若い頃は『このインタビュワーさん上手だな』と文章を抜き出して、写してみたりしたこともあった。でも、机の上のことだけをいじって変えるのは、難しいかもしれません。自分のボキャブラリーは限られているし、文章の組み立て方の変化は小手先で終わっちゃう。
それを変えるには、体験や経験が大切だと思います。私も『暮らしのおへそ』で良い文章が書けるときは、相手がいいことを言ってくれたとき。相手の力によって、良い文章が引き出されているんですよね。
ということは、良い出会いをしたり、良い体験をすることによって、文章は磨かれるんですよ。“自分の心が動くことを探す”のが、良い文章を書くことにつながる感じかな」
読者が深く共感してくれるのは、“すこん”があったとき。
一田さんは今でも「この良い体験を言葉で伝えるには」と悩み、部屋中をうろうろしたり、ソファに深く腰掛けてみたりしながら探すのだそう。
一田憲子さん:
「これだという言葉が出た、その爽快感たるや! 多分に、感覚を言葉にするっていう作業なんですよ。
読者がより深く共感してくれるのは、文章で理論的に説明されるよりも、気持ちに“すこん”と降りてきたとき。だから、その感覚を探しています。
抽象的にしか言えないのですけれど、それは単語のときも、文章のときもあります。『なんとかが、ガチガチする』と書いたとしますよね。ふつうなら拙い文章として、文章の誤りなどをチェックする校閲さんに直されてしまうような表現でも、私にとっては『あれは、ガチガチ、なんだ!』と思えば、押し通したりもします。あのときの感覚を、どうにか言葉にしたいんですよね」

クラシコムには、20代から40代までのスタッフがいますが、一田さんの文章を、『暮らしのおへそ』を、みんなが共感しながら読んでいる理由はここにあるのかもしれません。悩みの果てに生まれた言葉によって、一田さんの感覚を体験できて、“すこん”と感じられているからなのでしょう。
特別な勉強会、まだまだ続きます。
 |
「私らしく」働くこと~自分らしく生きる「仕事のカタチ」のつくり方~,一田憲子,マイナビ,2015-07-16 |
 |
暮らしのおへそ vol.20 (私のカントリー別冊) ,主婦と生活社,2015-08-29 |