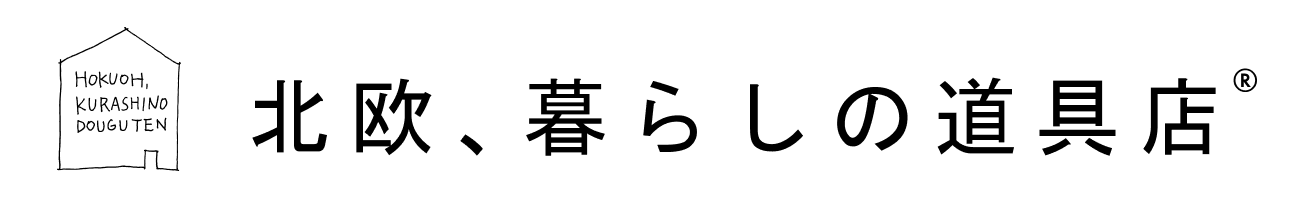ふつうなのに、何度見ても飽きがこない。使うたびに、表情が変わって見える。いい器は、そういう魅力があるような気がします。
この読み物は、食器棚と器を訪ね歩く連載です。どんな家にもあるけど、どこにも同じものはない。そんな食器棚と器と収納を見せてもらいながら、おしゃべりしたことを、小さなコラムにしてお届けします。
今回は、神奈川県の自然豊かな場所で、器をつくりながら暮らす、小川麻美(おがわ・あさみ)さんにお会いしてきました。
器をつくる人、小川麻美さんの食器棚

夏の日差しにきらめく湖畔を眺めて、車で山道を走っていく。小川さんの住まいは、緑も畑も多い、のどかな山すその町にあります。自宅と工房を兼ねた平屋に、夫、小学2年生の息子、猫2匹とともに暮らしています。
小川さん:
「裏山があって自然のなかで遊べるような地域で育ったこともあり、都内で一人暮らしの時から、いつかこういう環境で暮らしたいと思っていました。
ここは夫の仕事場からすぐなんですよ。木工の工房で働いていて、この家のキッチンや収納、ダイニングテーブル、玄関扉などは夫の勤め先で制作してもらいました。
キッチン背面の食器棚は、入居後1〜2年かけて動線や物量を把握したうえで、電子レンジや保存食材も収納できるようにつくってもらいました」

薄いグレーにペイントしたオープン棚は、上から、マグカップやタンブラー、取り皿と碗もの、鉢もの、そして主菜やワンプレートに使える大皿と、形やサイズが似ているものを重ねて、きゅっとコンパクトに収納されています。
棚の高さや奥行きは、 "せっかく自分たちでつくるなら" と、手持ちのものを見渡せるサイズにこだわりました。
小川さん:
「私の工房はキッチンのすぐ隣にあり、お昼もここで作って食べているので、基本的には一日三食、自炊になります。ゆっくり台所に立つ時間がない日もあるし、器の収納は、出し入れしやすくストレスがあまりないように考えました」
器を買ったら、いつもの風景が違って見えた

小川さんは20代のころから、母と器を見に行くことが好きで、骨董品や作家ものを扱っている店にも出入りしていました。
小川さん:
「一つ買うごとに、日常の景色が変わっていくと言いますか。お気に入りのカップが一つあるだけで、お茶を飲む時も、何かが違うんですよね。
使って、洗って、棚に戻す、という一連の行為が、愛おしく感じられて、なんてことない料理も器のおかげで『おお…!』となる。台所に立つのが楽しみになりました。
当時は一人暮らしだったんですけど、あれこれ悩んで買った器は、食器棚から手にした時の歓びも格別だし、食卓の景色がこんなにも変わるのかと、言葉にならない感動を覚えました」
佇まいのいい、シンプルな料理が映える器

食器棚にある自作の器たちを見せてもらうと、土の表情が豊かで、どっしりした雰囲気。手にすると、想像よりも軽く、すんなり馴染みます。おおらかで寛容、という言葉が浮かびました。
聞くと、日々のごはんは「普通のおかずとご飯と味噌汁が多い」とのこと。
小川さん:
「家族は簡単なごはんのほうがいいみたいで、色々おかずがあるよりも、ワンプレートでさっと食べられるものを好みます。
そうめんや中華麺の上に、蒸し鶏をほぐして、きゅうりの細切りや焼き茄子をのせたり、肉味噌をのせて和え麺にしたり。カオマンガイも、家族みんなが好きでよく作ります。
毎日のことなので、買ってきたお寿司を出す日もあれば、庭の畑でたくさん採れた野菜を使わなきゃという日もあるけど、器があればなんとかなる。楕円形や四角い皿は、食卓にリズムを生み出すので、我が家では重宝しています」
何十年間、ずっと見ていても飽きないもの

私、碗が好きなんです、と手にしたのは、ざらりとした質感のなかに力強さと繊細さを感じる器。
小川さん:
「これなんて、いくら見ていても飽きないくらい。20代の時、西荻窪の魯山という器の店(現在は閉店)によく通っていて、そこで見つけたものです。
形がまんまるではなくて、ちょっといびつなところに惹かれて、かっこいいなぁと。色むらも、欠けも、なんとも言えない良い表情をしていますよね」
 ▲20代のころに魯山(現在は閉店)で買った田鶴濱守人さんの作品。碗は具沢山の汁物や小丼として、浅鉢はカレーやチャーハンをよく盛った。「和洋中、何でもよく似合うんですよ」
▲20代のころに魯山(現在は閉店)で買った田鶴濱守人さんの作品。碗は具沢山の汁物や小丼として、浅鉢はカレーやチャーハンをよく盛った。「和洋中、何でもよく似合うんですよ」
小川さん:
「じつは浅鉢は、買った日の帰り道でどこかにぶつけたようで割れてしまって……。半べそをかきながら、魯山の店主の大嶌さんに相談して、漆で継いで修理してもらいました。ショックでしたけど、それも思い出です」
「これってどういう焼き方をしているんだろう?」
 ▲思い入れのある器について尋ねたら、陶芸を始めた時期の作品を見せてくださった。いずれも穴窯での焼き締め。
▲思い入れのある器について尋ねたら、陶芸を始めた時期の作品を見せてくださった。いずれも穴窯での焼き締め。
器好きが高じて、会社員のかたわら陶芸教室に通うようになった小川さん。32歳のとき、勤め先が廃業することになり、そのタイミングで陶芸家として独立しました。
小川さん:
「先ほどの碗の雰囲気もそうですが、渋くて味わいのある焼きの器に惹かれることが多く、自分でも取り組んでみたいと思い、陶芸教室の先生に相談して、炭化焼成をやるようになりました。
先生は、木工や溶接のお仕事を経て、陶芸も独学され、ものづくりの人生を歩んでこられた方でした。独立するための具体的なアドバイスをもらったり、この家に併設して窯小屋を建ててくださったり、本当にお世話になりましたね。
よく覚えているのは、まだ陶芸を始めたばかりの頃、先生やお仲間さんで作った穴窯での窯焚きに何度か参加させてもらいました。5日間かけて薪をくべて焼き上げるのですが、火を絶やさないように、先生や他の生徒さんたちと寝ずの番をして。
そうして窯出しした焼き締めの器たちは、土と炎と薪の灰が織りなす豊かな表情がそれぞれにあり、やきものって面白い!と魅せられました」
ものづくりは、自分と向き合うこと
 ▲ご自宅の庭には緑がたっぷり。家しごとや作陶の合間にコーヒーと焼き菓子でひと息入れることも。
▲ご自宅の庭には緑がたっぷり。家しごとや作陶の合間にコーヒーと焼き菓子でひと息入れることも。
使い手としても、作り手としても、器と向き合ってきた小川さんに、 "いい器" ってどんなものだと思いますか?と、聞いてみました。
小川さん:
「『器をつくる人は料理をしないとダメだ』と、魯山の大嶌さんから口すっぱく言われました。最初は見た目から入ったとしても、日々の生活のなかで、実際に料理をして、盛り付けて使ってみることが大事なんですよね。
初めて作品を見てもらった時には、『きちっと揃えるのはつまらないんじゃない? 好きにひいたらいいよ』って。気持ちが楽になりました。私は、製品のような器をつくりたいのではなく、自分らしいやきものでよいのだと。
ものをつくる人としての姿勢、自分と向き合うとはどういうことか、大嶌さんと出会って、そんなことも考えるようになりましたね。陶芸は、掴めるようで掴めないから、きっと一生続けていけるんだと思います」
 ▲猫のごはん入れも小川さんがつくった。「生活のなかであったらいいなと思うものは、できるだけ自分たちの手でつくりたいんです」
▲猫のごはん入れも小川さんがつくった。「生活のなかであったらいいなと思うものは、できるだけ自分たちの手でつくりたいんです」
使い手にとって寛容で、おおらかに料理を受け止めてくれる器。いびつさや、色むらも、飽きずに味わいだと思える器。小川さんの食器棚にあるものは、たしかに、そういう顔をしていました。
器というのは一つひとつ、つくった人、使う人、両方の人柄と生活が、少しずつ混じり合った表情になっていくのかもしれません。
それでは次回の更新も、どうぞお楽しみに。
【写真】木村文平
※記事に登場したアイテムは、全て私物です。過去に購入したものを紹介しているので、現在手に入らないものもございます。どうぞご理解、ご了承いただけると幸いです。
連載のバックナンバーはこちら


小川 麻美
会社勤めをしながら通った陶芸教室から、好きが高じて陶芸家に。現在、相模原の里山に暮らしながら日用の器を中心に制作。
Instagram: @asami.o_utsuwa
感想を送る