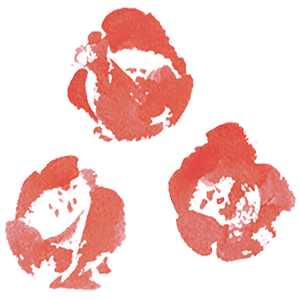X月X日
先日、かかりつけのお医者さんに本を貰った。一目見て思わず、「あ、これ、前から読みたかったんです」とお礼を云った。その本のタイトルは『将棋の子』(大崎善生)である。昔から、何故か将棋に関する本が好きなのだ。自分は将棋が弱いどころか、小学校以来指してもいない。今となっては駒の動かし方も覚束ないというのに。
奨励会とは日本将棋連盟の組織の一つで、棋士になるための修行の場であり、同時に淘汰の場でもある。全国から集まったプロを志す将棋の天才少年たちは奨励会に入会して、そこで初めて自分が天才でも何でもなく、将棋棋士を目指すごく普通の人間の一人であることを知る。(略)一度、天才の集団に入ってしまえば、どんなに優れていたとしてもごく平凡な存在となってしまうのだ。
『将棋の子』
だが、このような事情は将棋に限ったことではない。スポーツも音楽も絵画も、いや、学校の勉強でも、優れた才能を持つ者同士の競争の場において起きることは同じだろう。ただ、将棋には勝ち負けがある。また、奨励会はプロへの唯一の道であり、かつ一定の年齢までに棋士になれなければ門が閉ざされるという点に独特の厳しさがある。十代の若者たちが己のすべてを賭けて挑まなければならない。もちろん未来は誰にもわからない。でも、その道を選んでしまったら、もう後戻りはできないのだ。
29歳を過ぎたころ、苦しみは飽和点に達しようとしていた。自分が夢を捨てさせられる日は刻一刻と迫っていた。
奨励会をやめたその先には、どす黒いコールタールの海が広がっている。そこに一人放り出された俺は、もがき苦しみながらその海を泳ぎ始めなくてはならないのではないか。
恐怖と焦りばかりがつのり、三段リーグの成績は一向に上らない。もうすぐ30歳になる自分がもし、この世界から放り出されたら、いったいどんなことをして生活すればいいのだろうか。10代後半から30歳に至るまで、将棋しかしてこなかった自分に、何か他にできることはあるのだろうか。
『将棋の子』
この本をくれたお医者さんは、私と違って将棋が強い。少年時代には県の代表になったこともあるらしい。つまり、天才の一人である。実際に奨励会に入る道も考えたことがあって、「だから、この本を純粋には楽しめないんです。胸が痛くなってしまって」とのことだった。
お医者さんとして成功しているのだから、傍目には幸福な人生に思われる。でも、もしもあの時、将棋のプロを目指していたらどうだったろう、と想像する日があるんじゃないか。今頃、羽生九段や藤井五冠と盤上で火花を散らしていたのか、それとも棋士にはなれなかったのか。その答えは永遠にわからないのだけれど。
一方、将棋のことなど何も知らず、純粋な一読者に過ぎない私はもっと残酷だ。天才の活躍も読みたいけど、それと同じくらい天才の挫折も味わってみたい。紙一重の才能が同じように努力を重ねたのに、天国と地獄に道が分かれる。その運命の明暗を見たい。これは凡人の楽しみだ。だって、自分には天国はもちろん地獄へ行く資格もないのだ。そんな私の目には、彼らの悪戦苦闘が輝いて見える。

X月X日
将棋繋がりで、『風果つる街』(夢枕獏)を再読した。
あるプロ棋士は、子供の頃から、雀の数を数えるのが得意であったという。
電線に、雀がとまっている。
十羽、二十羽という数ではない。
三ケタの数の雀である。
(略)
そのやり方というのはこうだ。
まず、宙に雀が舞った瞬間に、その一瞬の光景を頭の中に焼きつける。きっちり記憶してしまうのだ。
その後、その記憶の映像に映っている雀の数を、ひとつずつ頭の中で数えてゆくのである。
写真を撮って、その写真に映っている雀の数を数えるのと同じだという。
話を聴けば、なるほどと思う。
なるほどと思うが、誰にでもできることではない。
天才的な記憶力があって初めてできるのである。
大なり小なり、そういった天才の子供ばかりが、奨励会には、日本全国から集まってくるのである。
奨励会で、その天才ぶりを比べるのだ。
『風果つる街』
夢枕獏は格闘技小説で有名だが、そこで鍛えられた描写力が盤上の闘いにも存分に発揮されている。やはり両者には共通するものがあるのだろうか。そういえば漫画家の柴田ヨクサルも、バトルものである『エアマスター』の後に『ハチワンダイバー』という将棋漫画を描いていた。
「兄貴はずるかったな。おれに将棋の味を覚えさせておいて、自分は将棋はほどほどで東大に入学したんだからな」
宇津木は、アスファルトの上に赤い唾を吐いた。
「知ってるかい……」
宇津木は言った。
「何をだ?」
「みこみのない弟子に、師匠が引導をわたす時だよ」
「知らんな」
「ある日、いきなりね、おい一番やろうかと先生が弟子に声をかけるのさ。平手でだよ。こんなことはめったにない。緊張してね、将棋を指すと、こちらが先生に勝っちまうんだよ……」
宇津木は、さぐるように、文吉を見た。
「……こちらが喜びかけると、先生が言うのさ。強くなったなあ、宇津木、おれに勝てるくらいなら、もうおれに教えることはないなってね……」
それが、師の別れの挨拶だったというのである。
『風果つる街』
厳しいなあ。兄弟といえば、谷川浩司十七世名人のお兄さんである谷川俊昭氏も、アマチュアの強豪として東大の将棋部などで活躍したらしい。まあ、こちらは『風果つる街』の宇津木とは違って、弟も挫折することなくプロに進み、ついには永世名人を襲位するまでに大成したからよかったけど。
『将棋の子』にも、こんなシーンがあった。
そのとき、がらっと寿司屋の入口が開いた。
「あっ」と奨励会員の誰かが言った。その瞬間、今まで大騒ぎをしていた全員が一斉に静まり返ってしまった。あまりの雰囲気の急変に驚き、私も振り返って入り口を見た。
そこには、長身痩躯の青年の姿があった。当時21歳の名人、谷川浩司であった。
新聞社の担当記者と現れた谷川は軽く我々に目礼すると、遠く離れたカウンターの席に腰を下した。
今まで大騒ぎをしていた連中は誰も声を発しなくなっていた。私は私で初めてこの目で見た、この世界だけが持つ名人というものへの畏怖の念の重さに言葉を失ってしまった。
谷川よりも年上の奨励会員はその場に何人もいた。その逃げ場のない現実が誰をも寡黙にさせていた。
「出ようか」と関口は言った。関口には彼らの心情が痛いほどにわかるのであろう。谷川がきてしまった以上はそこにいるほとんどの者はその場所にいるわけにはいかないのである。
『将棋の子』
天才たちの天国と地獄、その運命の明暗を見たい、とは書いたものの、実際にその場にいたら、無関係なはずの自分まで凍りついてしまいそうだ。


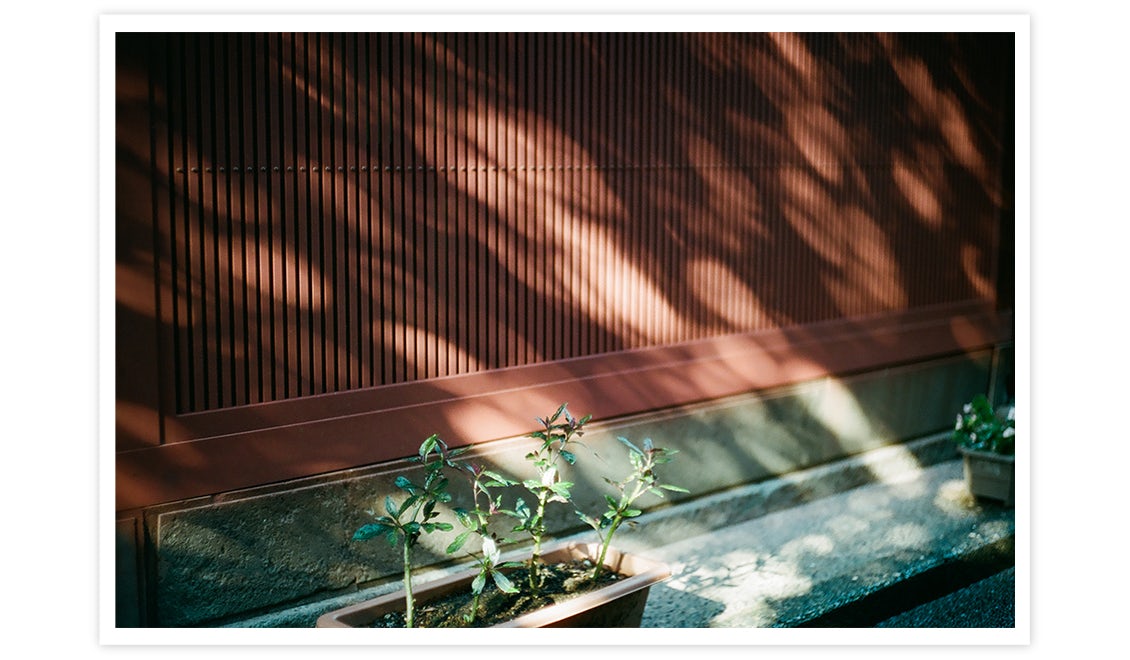

 1962年北海道生まれ。歌人。1990年歌集『シンジケート』でデビュー。詩歌、評論、エッセイ、絵本、翻訳など幅広いジャンルで活躍中。著書に『本当はちがうんだ日記』『世界音痴』『君がいない夜のごはん』他。
1962年北海道生まれ。歌人。1990年歌集『シンジケート』でデビュー。詩歌、評論、エッセイ、絵本、翻訳など幅広いジャンルで活躍中。著書に『本当はちがうんだ日記』『世界音痴』『君がいない夜のごはん』他。
 1981年神奈川県生まれ。東京造形大学卒。千葉県在住。35歳の時、グラフィックデザイナーから写真家へ転身。日常や旅先で写真撮影をする傍ら、雑誌や広告などの撮影を行う。
1981年神奈川県生まれ。東京造形大学卒。千葉県在住。35歳の時、グラフィックデザイナーから写真家へ転身。日常や旅先で写真撮影をする傍ら、雑誌や広告などの撮影を行う。
感想を送る