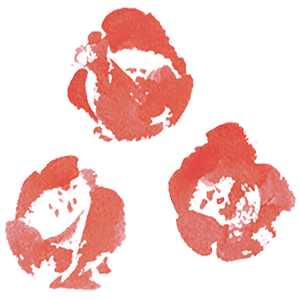X月X日
前々回、「たんぽぽ娘」(ロバート・F・ヤング、伊藤典夫訳)について、「一作だけが突出して有名な作家がいるけど、ロバート・F・ヤングもそうかもしれない。この短編には、それだけの特別感がある」と書いた。「おとといは兎を見たわ、きのうは鹿、今日はあなた」というフレーズとともに、その魅力には忘れがたいものがある。
「一作だけが突出して有名」な短編の例として、他に思いつくのは例えば大坪砂男の「天狗」である。手元の『『このミス』が選ぶ! オールタイム・ベスト短編ミステリー 黒』の解説には、「『天狗』は、アンソロジーに過去十三回も採録された名作中の名作である」(千街晶之)と記されている。
私も昔からずっと気になりながら、手に取る機会を逸し続けてきたのだが、やっと読めた。結局、存在を知ってから実際に読了するまでに四十年ほどもかかってしまった。「天狗」はいろいろな意味で予想を超えた作品だった。「名作中の名作」は、こんなふうに始まる。
黄昏の町はずれで行き逢う女は
そうだ、黄昏の女──巾を被ってわざと見向きもしないで、足早に通る女はどれもこれも喬子の変装に相違ない。背が高いのも低いのも。肥ったのも痩せたのも!
「天狗」
思わず引き込まれる。モノローグのテンションがあまりに異様なのだ。全体を読むと、さらにびっくりしてしまう。犯罪の動機やトリックも破格だが、その根源にあって、すべてを支配しているのは、「そうだ、黄昏の女──巾を被ってわざと見向きもしないで、足早に通る女はどれもこれも喬子の変装に相違ない。背が高いのも低いのも。肥ったのも痩せたのも!」という強迫観念めいた思い込みの強さである。
語り手の脳内の嵐がやばい。こんな人に目を付けられたら、たまったもんじゃない。特異な文体から、びりびりと危うさが伝わってくる。その意味で、「天狗」はミステリーでありつつ、いわゆる純文学の小説や散文詩に近いとも云える。そういえば、「天狗」の被害者はいつも詩集を携えていた。タイトルは『堕天使』だ。

X月X日
『推理文壇戦後史Ⅰ』(山村正夫)の中に、「名作『天狗』誕生のいきさつ」という項目があった。
ところで、「天狗」は、戦後発表された数多くの短篇のうちでも、いまなお屈指の名作といわれているが、大坪氏の死後、奇妙な噂が立った。あれは、徳子未亡人の代作ではなかったかというのである。(略)まぎれもなく氏の創作だったのである。これは故人の名誉のためにも、敢えてはっきりしておいた方がいいと思う。
なんでも、「天狗」は、大坪氏の疎開先の近所に精神異常の男が住んでいて、それをモデルにしたものだということだった。あるとき徳子未亡人と男女同権を論じたことから諍いが起り、夫婦喧嘩の後の気まずい空気のなかで、大坪氏は大きな辞典を枕に天上を睨んでひっくりかえっていた。ところがとつじょガバッとはね起きて机に向かったかと思うと、夢中で原稿の執筆に取りかかった。そして一気呵成に書き上げたのが、「天狗」だったというのである。
『推理文壇戦後史Ⅰ』
「精神異常」「男女同権」「夫婦喧嘩」、そこから生まれたものが、あのとんでもない物語とは。実にさまざまな伝説に彩られた「名作」なのだった。
X月X日
「天狗」について「語り手の脳内の嵐がやばい」と書いたが、実のところ、そんな作品はすべて面白いとも云える。例えば、『崖の館』(佐々木丸美)。「天狗」の世界に吹き荒れているのが強迫観念の嵐だとすれば、こちらは思春期の嵐である。
「早く警察を、それからお医者さんも呼ばなくては」。私の顔を見て棹ちゃんは静かに首を振った。そしてポツンと言った。「電話線が切られているの」
外はまた吹雪いて来た。
『崖の館』
吹雪に閉ざされた館の中で六人の「いとこ」たちが互いを疑い合い、かばい合い、憎み合い、愛し合いながら真犯人を捜そうとする。物語の語り手は探偵役の少女であり、事件の手掛かりとなる日記を残した最初の被害者も少女である。早熟な文学少女の頭の中が流れ出したような言葉たちが、思春期特有の心の嵐を生み出している。
私はその人を恨むまい。手鏡を砕きドレスを切り裂き小鳥を凍死させたとしても。それがあまりある才能を発散させる奇抜な遊びであれば許したいと思う。私の恐怖心がまわりの人を困惑させ一定の緊迫を保つことでその異常な心理がおさまるのなら私は喜んで生贄になろう。
『崖の館』
「手鏡を砕きドレスを切り裂き小鳥を凍死させたとしても」って凄い。「私は喜んで生贄になろう」の危ういテンションに怯みながらも惹かれてしまう。千波、棹子、涼子、海にちなんだ名前の「いとこ」たちの中に一人だけ、それとは無縁の由莉がいる。そんな細部にも甘美な不穏さがある。

X月X日
インターネットで「神々の遊び」を見た。お笑いコンビのモンスターエンジンによるショートコントである。十年ほど前だろうか、偶然、深夜のテレビで見かけて心を掴まれた。お笑いの世界に疎い私は彼らのコンビ名すら記憶していなかった。にも拘わらず、時々、思い出しては、あの時のコント、神さまのあれ、面白かったなあ、と懐かしんでいた。だが、ふと思いついて検索してみたところ、ヒットしたのである。
久しぶりの「神々の遊び」は素晴らしかった。「私は神だ」でいきなり感動。「私だ」でまた感動。「お前だったのか」でさらに感動。ワンパターンのやり取りが、どうしてこんなに面白いのだろう。不思議だ。心の奥に眠っている何かを刺激されるのか。何度も繰り返して見てしまった。

 1962年北海道生まれ。歌人。1990年歌集『シンジケート』でデビュー。詩歌、評論、エッセイ、絵本、翻訳など幅広いジャンルで活躍中。著書に『本当はちがうんだ日記』『世界音痴』『君がいない夜のごはん』他。
1962年北海道生まれ。歌人。1990年歌集『シンジケート』でデビュー。詩歌、評論、エッセイ、絵本、翻訳など幅広いジャンルで活躍中。著書に『本当はちがうんだ日記』『世界音痴』『君がいない夜のごはん』他。
 1981年神奈川県生まれ。東京造形大学卒。千葉県在住。35歳の時、グラフィックデザイナーから写真家へ転身。日常や旅先で写真撮影をする傍ら、雑誌や広告などの撮影を行う。
1981年神奈川県生まれ。東京造形大学卒。千葉県在住。35歳の時、グラフィックデザイナーから写真家へ転身。日常や旅先で写真撮影をする傍ら、雑誌や広告などの撮影を行う。
感想を送る