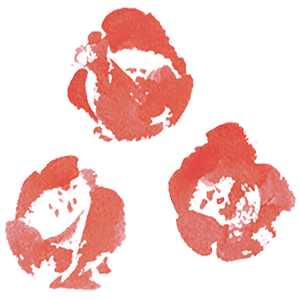「たとえばせつないとか、寂しいとか、孤独とか。否定するような悪い感情なんだろうか。それも含めて人生で、むしろ尊い、慈しみたい感情ではないか。そんなところを企画の出発点にしています」。
どの窓からも緑の木々しか見えない。森にいるような開放感あふれる写真家・川内倫子さんの千葉の自邸で、私は対談の意図を話しだした。
静かな眼差しで「ええ、はいはい」とうなずく川内さん。
対談の依頼に、すぐ快諾いただいたと聞いた。だから思わず、最初に尋ねた。── どうしてお引き受けくださったのでしょう?
「孤独や言葉にできないというのは、心あたりのある感情。つねに自分の核にある本質的なテーマだなと思ったからです。写真の話じゃないようでじつは写真の話とも重なりそうです」。
日々は言葉にできないことばかり

第五回 川内倫子さん
写真家。1972年滋賀県に生まれる。2002年『うたたね』『花火』の2冊で第27回木村伊兵衛写真賞を受賞。ほか主な著作は『AILA』、『the eyes, the ears,』、『Cui Cui』、『Illuminance』、『あめつち』など。2009年にICP(International Center of Photography)主催の第25回インフィニティ賞芸術部門受賞、2013年に芸術選奨文部科学大臣新人賞(2012年度)を受賞。国内外で数多くの個展を開く。東京オペラシティ アートギャラリーおよび滋賀県立美術館で、10年ぶりとなる個展『M/E 球体の上、無限の連なり』を開催した(会期終了)。
「あの子を笑顔にさせたくて」
2022年の年末。川内さんの写真展を訪れると、出口近くにこれまでの写真集すべてを自由に閲覧できる小さなテーブルとイスがあった。私は座り込み、初期の作品から順番に40分ほど夢中で見入った。本当はもっと読んでいたかったが、他の鑑賞者のため渋々退席した。
広いオペラシティにのびのびと展示された作品を見て、感じた。彼女の写真は、1点1点が単独で美しいだけではない。
なんだか、右の写真と左の写真のつながりを考えたくなる。
写真の中の余白はもちろん、作品が並ぶ余白にも、なにかメッセージや意味があるのではと、探りたくなる。
ひとまとまりごとに、言葉にできないものを感じ、ぐっと引き込まれる。
さらに写真から別の特別な感情を抱いたが、それは後述するとしよう。
とにかく、もっと知りたいと、写真展であんなに過去の写真集を眺めたのは初めてだ。

── あの個展が、言葉にならない感情についてお話をしたいと思ったきっかけになります。川内さんにとって、写真で表現するという仕事は、どういう意味を持つのかなというのもお聞きしたくて。
川内 ご覧いただき、ありがとうございます。私はこの仕事をすることで、小さいときに満たされなかったもの、自分の抱えているものについて、補完しているようなところがあります。
── エッセイに少し書かれていた、お父様の事業がうまくいかなくなって、滋賀から大阪に越されたという。そのことに関係しているのでしょうか。
川内 それもあります。4歳のとき、車で親戚の家に遊びに行くと思ってついていったら、いつまで経っても帰らない。「帰らないの?」と聞いたら、「今日からここがおうちだよ」と。前の家にもう戻れないんだという衝撃。家族のムードがなんとも言えず落ちているのが、子ども心にもわかって。その空気とかさなり、あの4歳の衝撃は、今も忘れられません。
── 前のおうちはお気に入りだったんですか。
川内 当時お気に入りだったという自覚はありませんが、やっぱり生まれ育った家は、愛着がありますよね。時間って巻き戻せないし、過去にはいけないんだ、というせつなさを4歳で体験したことは、その後の自分に大きな影響を与えています。
── 小学校を含め、子ども時代はとても孤独だったとも書かれていましたね。
川内 なにか、ずっとしんどかったですね。子どもって残酷ですから。同級生の言葉がいまだに胸に刺さっていたりする……。小学校の先生が、親に私のことを「感受性が強い子だ」と言ったそうなんです。後年、私の仕事をみた母が、「あの言葉は、こういうことだったんだね」と。母の胸にも長く、残っていたんでしょう。
── 山田詠美さんの自伝的小説に、父が会社勤めで子どもの頃引っ越しが多く、同じ社宅の子にいじめられたことがあったと。“奔放な作風”と言われることがあるが、今も自分の心の中にはあのときの、普通のサラリーマン家庭に育ち、友達の言葉に傷ついた小さな女の子がいると書かれていて。それを思い出しました。
川内 そう、私も、あの頃の小さな女の子が心のなかにいます。その子が少しでも笑顔になるように、今、自分の仕事を頑張っているのかもしれません。その子が欲しかったものが今、一つずつ心の内側から出てくるような。
── インナーチャイルドというとあれですが。そんな小さな女の子のことを、はっきり自覚したのはいつですか。
川内 10年くらい前かな。あるインタビューを受けて、自分の幼少期のことを話しているうちに涙が止まらなくなって。自分でも引くほど号泣してしまったんです。そのとき気づきました。しんどかった小さな頃の自分がやっぱりいる。今もどっかり自分の中に居座っているんだって。言葉にしていないだけでうすうす感じていたけれど、その時にはっきりと意識しました。
見えない目のこと

最初は、撮ったものをとにかく吐き出したい、発表するしかないという境地から始まった。しかし、創作を続けていくうちに ── とくに“号泣”からのこの10年で ── 気づきは確信になった。
写真集に仕上げたり、作品展を開くことは、川内さんにとって、あのときの小さな自分を癒す役目も果たしている。
川内 作品を創ることで、自分が癒やされる。それを最終的に、他の人ともシェアできる環境を作れたことが、私にはとてもありがたかった。作品を創って発表するという行為は、自分のメンタルを維持するのに、最高に有効な手段でした。
彼女の創作は独特だ。
撮るときはあまり考えすぎないようにしているという。体の反応をなにより優先する。その時々で反応した、撮りたいものを撮る。
のちにまとめる段階で、「なぜ私は反応したんだろう」と考える。
写真と対話を積み重ね、一冊の写真集や写真展に仕上げる。撮影以上に、この対話の時間が重要だ。まとめ終えたところで、ああそういうことだったんだとあとからテーマが見えてくることもある。
それを読者や鑑賞者と分かち合うというしくみができていることがまた大きい。
写真表現は、彼女が生きていくうえで呼吸のように不可欠。
なおかつ経済的に成り立っているということが、じつはとても重要なのだと思った。
聞きながら、だから私はあのとき心をつかまれたのだと腑に落ちた。
前述の2022年暮れ。『M/E 球体の上 無限の連なり』(オペラシティ)。
ここ10年の活動に焦点を当てた個展で思った。 ── この写真の世界は、私の左目の光に似ている。
私は、生まれつき左目の視力がない。幼い頃3回手術を受けたが矯正できず、今も明度と彩度はわかるが輪郭は曖昧だ。しかし、ぼんやりとしているが、いつもきらきら光がきれいに澄んで映る。
川内さんのおぼろげで透明な光にあふれた写真を見て、同じだ!と膝を打った。見えないのに見える。今までこの見え方をうまく説明できなかった。そもそも左目のことはあまり人に言っていない。
「川内さんの写真みたいに見えるんだよ」。そう言ったらいいんだと、嬉しくなった。
コンプレックスだったものが、晴れやかなものにぐるりと変換された。
同時に、彼女はどうしてこんなにせつなくて、どこか詩的で、きらきら透明に撮れるのか、その答えのかけらがわかったのだ。彼女もまたこの作品に癒やされているからだ、と。
巣立つ日が今からせつない

「そうでしたか。なんだかうれしいですね。似て見えるというのはこれかな」
と興味深そうに、彼女は写真展の図録をぱらぱら探した。
── 見える方の右目も酷使して悪くなる一方なので、私は死ぬまでにというより右目が見えるうちにあと何冊書けるだろうと、今からものすごく焦っています。川内さんはそんな焦りはありますか?
川内 あります、あります。是枝さん(是枝裕和監督)と何度かお仕事でご一緒しまして。是枝さんが50歳の時、「あと何本撮れるんだろう」とおっしゃっていたのが印象的でした。私もそういうふうに思うんだろうか、とそのときは思っていたけど、いざ40代が過ぎたら、自分もあと何回展示ができるんだろうか、残りの人生でなにができるだろうかと焦る気持ちがあります。
── 焦りでいうと、私は育児の場面でもあって。自分が18歳で親元を離れたので、子どもが10歳になったくらいから「一緒にいられるのはあと8年、あと7年」と、心の中でカウントダウンが始まり、10歳までとはせつなさのつのるスピードが全然違いました。
川内 それ、お聞きしたかったんです。私は夫と出会ったのが41歳で、高齢出産の娘がまだ6歳で。子どもが巣立つ日のことを考えると、今からすでに寂しいです。もう怯えながら暮らしています(笑)。
── うちは長男が大学卒業後まもなく、結婚してしまいました。その喪失感が3年経った今もまだ続いています。
川内 3年も。娘さんは?
── 23歳で家にいます。もう結婚なんてしなくていいから、ずっと家に寄生しててくれって思っちゃいます。
川内 子どもをもつことを望んでいたので、日々の些細なことでも、感謝すればするほどなんかもう、本当に一緒にいられる時間は短い、一瞬なんだなあと。生まれて3年も経てば、よちよち歩いていた姿はもう見られないし、2歳のときのおしゃべりは2歳のときだけ。一瞬一瞬を目に焼き付けておきたいなと強く思いますね。
今、初めて味わう人生の実感

子育てと同時期に、川内さんは住み慣れた東京から、自然のそばで暮らしたいと千葉に移り住んだ。だが移住より、子どもがいる生活という人生の変化のほうがずっと大きかったと振り返る。
川内 ひとりの自由さ、孤独のゆたかさってありますよね。かたや子育てでしか得られないこともある。娘がいなければ、早起きもしないだろうし、仕事が好きだから働くだけ働いて、夜も飲みすぎて、早死するタイプだったと思います(笑)。
── 飲みすぎるのは、私が今そうです。子育てが一段落したら、とたんに自由になりすぎて、生活リズムがぐだぐだになりました(笑)。
川が流れ、昼は木々の緑と光にあふれ、夜は月明かりが美しいこの地で、ひとり暮らしの頃は想像もつかなかったママ友、パパ友らと家族ぐるみの付き合いも生まれた。今は、会話のキャッチボールや6歳にしかできない質問のあれやこれやを、心のアルバムに大事に保存している。
川内さんは、しみじみとつぶやく。
「小さいときは生きることが苦痛でしかなかったけれど、人生に楽しい時間ってこんなにあるんだなと実感しています」。
あの頃から詩が自分の中に

川内さんの写真集は、パラパラと繰れない。じーっと一枚一枚手を止めて、見入りたくなる。余韻。文章で言えば、行間のようなものを感じるからだ。
川内 私、小学校4年のとき、詩のチャンピオンだったんです。当時の担任の福田由美先生が、生徒のいいところを見つけてはチャンピオンを決める人で。誰々くんは給食のチャンピオンね、とか、逆上がりのチャンピオンね、とか。
── どんな詩を書いていたんですか。
川内 初めて書いた詩のタイトルが『もしも自分が死んだなら』。福田先生が決めたテーマでクラス全員が同じタイトルで書きました。みんなの前で読んでね。詩の冒頭は「もしも私が死んだなら、みんな泣かないでください」。そこまで読むとみんな笑ったの。確か最後は「みんなが泣いたら、虹が消えてしまうから。虹が消えたら、私は向こう側に、行けなくなってしまうから」。
── 小4でその言葉は……。最後ぐっときますね。
川内 あの頃から、詩が自分の中にあって。写真でも最初から、自分が創るものは詩のようなものでなければと考えてきました。『うたたね』という1冊目の写真集でも、行間を大事にしたくて。見開きの2枚の写真の間になにかあると。130ページほどありますが、写真を組み合わせることによって、写真と写真の間にも文学的な解釈をもたせたい。そこに重きをおいて創り続けています。
それはいわば、言葉にならない言葉。
写真集の余白にも、言葉にならない感情が宿っていたのだ。
写真展で、私は誰にも説明のつかなかった自分の左目の世界に出会い、それまでコンプレックスでしかなかったものが、ささやかにやさしく救われた。
川内さんのなかの小さな子どもも、きっと日々癒やされ、救われ続けているんだろう。
過去は取り戻せないけれど、かつて傷ついた自分を、今生きながら励ましていくことなら誰にもできる。対談は、新鮮な発見に満ちていた。


長野県生まれ。編集プロダクションを経て1995年独立。著書に『男と女の台所』『ただしい暮らし、なんてなかった。』(平凡社)、『届かなかった手紙』(角川書店)、『あの人の宝物』(誠文堂新光社)、『新米母は各駅停車でだんだん本物の母になっていく』(大和書房)ほか。最新刊は『それでも食べて生きてゆく 東京の台所』(毎日新聞出版)。 インスタグラムは@oodaira1027
大平さんのHP「暮らしの柄」
https://kurashi-no-gara.com
撮影:佐々木 孝憲
感想を送る