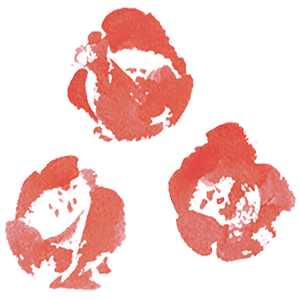小説家の土門蘭さんに『書くこと、暮らすこと』をテーマに、お話をうかがいました。
当店でも短歌とエッセイで綴る連載『57577の宝箱』や、人生の支えになる言葉や生き方を伺うシリーズ『でこぼこ道の常備薬』を執筆する土門さん。昨年12月に公開した「北欧、暮らしの道具店」のドラマ『スーツケース・ジャーニー』では、脚本にも挑まれました。
日々のできごとを心のカメラで細やかに捉え、「感情の良い面」や「豊かな気持ち」を見つけ出し、それを言葉として形にする。読むほど励まされ、時にはふたをしていた自分の気持ちにも出会える文章たち。いったい、こんな文章を書く土門さんは、どんな人なんだろう?
土門さんにとって、いかに「書くこと」は営みの一部になったのでしょう。そして、暮らしの中に「書くこと」を置いてみると、私たちにもどんな良いことがあり得るのでしょう。
そんな問いを胸に、前編は土門さんと「書くこと」の出会いについて。後編では、書くための心がけから、ドラマ脚本のエピソードまで、さまざまお聞きしました。
何かを伝えられる相手がほしかった
一人っ子で、鍵っ子。それが、土門さんが本や言葉と親しむきっかけでした。
土門さん:
「広島で生まれて、はたらく両親は夜遅くまで帰ってきませんでした。だから、テレビを見ているか、マンガや本を読むしかなかったんです。本は、家族ですごせない淋しさや暇な気持ちをまぎらわしてくれるから好きでしたね」
当時のいちばんのお気に入りは児童文学の『小公女』。日本ではテレビアニメ『小公女セーラ』の原作としても知られます。19世紀のイギリス、寄宿学校に住む少女・セーラが両親の訃報や不幸を機に、つらい仕打ちを受けることになっていく……という重いストーリー。土門さんの心をつかんだのは、セーラが肌身離さない人形の「エミリー」でした。
土門さん:
「セーラはつらい環境に心が折れそうになると、エミリーに『今日こんなことがあってね』と話しかけるんです。その描写がすごく好きでした。セーラの置かれた境遇と、淋しく過ごす私の姿が重なるところがありつつ、私も何かを伝えられる存在が欲しかったんです。
エミリーは人形ですから絶対に言葉を返してくれません。つまり、何も言わずに聞いてくれる相手であり、絶対的に安心できる場所みたいなものともいえます。そういうところへの憧れもあったんですね」

土門さんも学校であったことや、友達とうまくいかなかったことなどを、家のぬいぐるみたちに話しかけ始めます。さらに、日記にも心に浮かぶことを書き留めていきました。転機は、小学4年生のとき。風邪で数日休んでから受けた、算数の授業でした。
土門さん:
「面積の勉強で、単位のヘクタールとアールが出てきて。問題はなんとなく解けるけれど、ヘクタールとアールを求める公式がいったい何に使われて、誰が使うのかは、感覚的に全くわからなかったんです。でも、周りは気にも留めていない様子でした。
『あぁ、なんだか私って、いつもこんな感じだな』と思いました。ひとりだけ世界を知覚できていない感じというか。きっと、親と過ごす時間が短い分、自分と世界の関係性がちゃんと構築されていないままで、不安感の強い子どもだったのでしょう。
すごくつらくなってきて、いっそ窓から飛んでしまおうかな、みたいに考えていて……その姿を妄想して、本当に走り出そうとする直前で、ふっと『この気持ちを書こう』と鉛筆を手にしていました」
ノートに記した、「わたし」の結末。書き終えたとき、チャイムが鳴りました。土門さんは「書いたから、私は助かったんだ」と思えたといいます。
土門さん:
「言葉として表現することで、自分と世界がやっとつながって、知覚できた。とても大きな原体験です。それから一人でいる時には、本を読んでいるか、物を書いているか、という毎日になりました」
日記を書き始めた火星人

「書くこと」に出会えた土門さんは、自らを「火星から来たスパイ」という設定に据えて、地球で起きるあれこれを観察し、周囲との関係性を探り始めます。
土門さん:
「仲が良い友達もいて、勉強もふつうにできるし、先生にもよくしてもらっていました。けれど、なぜかずっと不安なままで、いろんなことにうまく馴染めないんです。
私だけが、運動会でどう振る舞ったらよいのか、アスレチックにどう登ったら楽しめるのか、いちいち心が突っかかってしまう。みんなのまねごとをしているだけみたいで……。
だから、頭では違うとわかっていても、私は地球人ではなくて火星人なのかもしれない、と思うほうが納得できました。そうして日記のかたちを借りて、火星の家族に読ませるためのレポートを日々書いていました」
いま振り返れば、それは土門さんにとっての「エミリー」だったのでしょう。この “馴染めない” という感情は、書き手として大切にもなるのですが、それは後ほどのお話。
大人になるにつれ、土門さんは火星人の設定を用いずとも、言葉で世界とつながれるようになりました。そして、土門さんには「書くこと」だけが残ったのです。
「あんたの小論文は面白い。物書きになりんさい」

高校生になった土門さんは、本を読み続け、書き続けていました。少年少女のための文学から純文学へ移り、将来を考えるうちに「作家になり、小説を書きたい」と思い始めます。ただ、その想いを大人へそっと手渡すと、諦めを促すような返事が来てしまう。だから土門さんは、誰にも夢を語らなくなりました。
しかし、それを変えてくれたのも、ある大人の女性からの一言でした。高校3年生で、大学受験の対策として、国語の先生に小論文の書き方を教わっていたときのこと──。
土門さん:
「先生の教えで小論文のコツが掴めてくるうちに、もっと自分の考えも入れ込んでみよう、と楽しくなってきたんです。5回目くらいの指導のとき、先生が『もう言うことはない。あんたの小論文は面白い。将来、物書きになりんさい』とおっしゃって」
ただ、その先生は、こうも言いました。「家の中で、一人でコツコツ書くのは向いてないねぇ。人といっぱいしゃべって、それを文章にしたらいいね」。
進路について、まっすぐに大人から勧められた初めての経験。土門さんもまっすぐに言葉を信じ、大学は文学部の国文学科を選びました。書き続ける日々で、ふと「それが仕事になるのか」を調べてみると、ライターという職を知ります。
土門さん:
「人にお話を聞いて、言葉を書く仕事があるらしい、と。大学の友人にもらった音楽関連のフリーペーパーでボランティアスタッフを募っていたので、経験はないまま会いに行きました。すぐ現場を手伝うことになり、ミュージシャンにインタビューして文章を書くことに」
現場を踏むごとに、もっとうまくなりたい、もっと褒められたい、もっと書けるようになりたい……という思いが高まりました。19歳のとき、アルバイトで貯めたお金を投じて、広告関連の雑誌社が主催する「編集・ライター養成講座」を受講。毎週土曜日に講義を聞き、課題を出すという時間が加わりました。
そこで土門さんは、歩み始めた道の「進み方」を教えてくれる言葉に、また出会います。
消して消して、それでも残った個性が表れる

元新聞記者の講師、故・斎藤喬さんの講義で「自分のお葬式の弔辞を書く」という課題が出ました。難しくもユニークなテーマに意気込み、「大学の男友達に弔辞を読んでもらう」という設定で応えます。すると斎藤さんは「最高の弔辞だった!」と褒めてくれたのです。
土門さん:
「ばぁっと鳥肌が立って。文章を褒められるのが何より嬉しいと、体でわかった瞬間でした。斎藤先生にもっと褒められたくて、ますます書くように。先生は私を “蘭ちゃん” と呼んでずいぶん可愛がってくださいました。
でも、ある時から先生の顔が曇ったんです。『いまの蘭ちゃんの文章は、個性を出そうとしている感じを受ける。個性は消しなさい。消して消して消して、それでも残るのが君の個性なんだよ』と言われました。
あとは、『自分の中から生まれることなんて限界があって、たいしたことはないんだ。君の感性は良いけれど、それだけで勝負をしないように。いろんな人に話を聞いてみなさい。頭の外にある答えにたくさん出会うと、想像もできなかったような文章が書けるよ』とも」
その言葉は、土門さんへ素直に響きました。エッセイなどを通じて書く「自我」と、他者の話を聞いて書く「無我」という、よりよく書くための二つの軸を識り、心に持てた瞬間だったといいます。
土門さんは20歳を迎え、インタビューの機会を増やしていきました。
馴染めないから、書けることがある

やがて、仕事としてインタビューやコピーライティングを手掛け、さらには小説や短歌といった作品を発表するなど、土門さんの「書くこと」は広がっていきます。ただ、昔から今にも変わらずあるのは、かつて “火星人” だった少女が抱いていた「馴染めなさ」でした。
土門さん:
「自分が特別と言いたいわけでは全くないのですが、どこか馴染めていない、少しはじかれている感覚は今も残っています。でも、そんな私だから見えて、書けることもある。
他人には自然と馴染むような物事が、私にとっての刺激や摩擦になるのだと思います。痛みや痒みに近い感覚ですね。馴染めていないからモヤモヤしたり、馴染めていないからこそ感動できたりもする。
そうして心が揺れ動いた瞬間、私の中に言葉が生まれていることがわかってきました。それを捉えると、よい文章になる感じがあって。
そのせいで毎日がつらい時期もありました。嬉しかろうが悲しかろうが、心が動くことって、しんどいですからね。ただ、書き続けるうちに、心が動くことそのものは全く悪いことではないと確かめられたんです」
“心が揺れ動く” のは、ネガティブに聞こえるものです。大人になるにつれて、どこかでそれを避ける気持ちが起きていたようにも感じます。どうやら土門さんの言葉は、それをまっすぐ受け止めて生まれるからこそ、読む人の心まで震わせる力を帯びているのかもしれません。
後編では、土門さんの「書くこと」との向き合い方を、さらに堀ってみました。
【写真】岡安いつ美
もくじ


土門蘭
1985年広島生まれ。小説家。京都在住。小説、短歌、エッセイなどの文芸作品や、インタビュー記事を執筆する。著書に歌画集『100年後あなたもわたしもいない日に』、インタビュー集『経営者の孤独。』、小説『戦争と五人の女』がある。
感想を送る