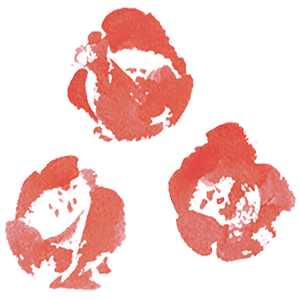レイクサイドの書店
「もし、現代を生きる人がみんな迷子状態であるなら、自分で自分の気持ちいい生き方を作った方がいいですよね。それが作れてハッピーに暮らせたら、この社会でどうやって生きていけばいいのかまったくわからなくて苦しんでいた僕のような人にも、なにか希望を与えられるんじゃないかって思ったんです」
東西に横長な鳥取県の中間に位置する湯梨浜町(ゆりはまちょう)で、書店「汽水空港」を営むモリテツヤさん。なぜ、「みんな迷子状態」と思ったのかは後述するとして、学生時代にこう思って以来、彼は「自分らしくて、気持ちのいい生き方」を模索してきた。そしてある日、“着陸”したのが縁もゆかりもない、湯梨浜町だった。
汽水空港の前には、山陰八景のひとつ、東郷池が広がる。池という名称ながら、淡水と海水が混じる汽水湖で、店名の由来でもある。よく晴れた日には一面が空色に輝き、夕暮れには淡い紫色や橙色が湖面に溶け込む。
僕がこのレイクサイドの書店を知ったのは、2020年の秋ごろだった。家族で鳥取旅行を計画したところ、ノンフィクション作家をしている僕の妻、川内有緒とモリさんがSNSでつながり、妻の著者イベントを開くことになったのだ。
初めて汽水空港を訪ねた時、湖畔に建つ、「本」と看板を掲げた小さな書店を見て、映画に出てきそうな風景だなと思った。モリさんがおもちゃ屋さんの倉庫をDIYでリノベーションしたというお店には、ひとめでこだわり抜いたとわかる新刊と古本が肩を並べていた。

 ▲新刊、古本、そしてZINEも取り扱う汽水空港。今回の取材は現地に行くことは叶わずZoomでお話を伺いました。
▲新刊、古本、そしてZINEも取り扱う汽水空港。今回の取材は現地に行くことは叶わずZoomでお話を伺いました。
スラリと細身、長髪でメガネ姿。どちらかといえばアパレルやレコードショップの店員のように見えるモリさんの頭のなかには、「書店主」にとどまらない独特の世界が広がっている。
「近所の人たちと一緒に、食える公園って名付けて、畑をやってるんですよ。誰でも出入り自由で、勝手に作物を食べていいんです」
現在進行形で開拓されているこの「食える公園」は、モリさんが冒頭に記した想いを実現するための「実験」の一部だ。
そもそも、彼はなぜ書店を始めたのか。なぜ、書店を経営しながら「食える公園」を作るのか。
その物語は、「生きづらさ」から始まる。
小学生の頃に感じた自由と違和感

1986年、北九州市で生まれたモリさん。親の仕事の都合で、インドネシアの首都ジャカルタでの生活が始まったのは10歳の時だった。現地でモリ少年が通い始めた日本人学校は、日本の小学校とは明らかに違う空気が流れていた。
「常夏の気候で、プールして、サッカーして、ただただ楽しいっていう日常でしたね。学校もすごく自由な雰囲気だったんですよ」
モリ少年にとって印象的だったのは、教師の振る舞いだ。今でも忘れられない出来事がある。
ある日、委員会での発表を評価されたある生徒が、表彰されることになった。日本の学校では、堅苦しく賞状が手渡されるのがよく見る風景だろう。でもこの時、生徒に贈られたのは、ボタンがついている変わった帽子だった。
この帽子を考案した教師が、生徒の発表を讃えて、帽子を手渡す。その帽子をかぶった生徒が、少しドキドキした様子でボタンを押す。その瞬間、頭の上で傘がパッと開いた。その姿を見て、生徒も教師も笑い転げながら、拍手を贈った。
「先生たちが、みんな解放されていたんですよね。子どもよりも、先生たちのほうが自由を謳歌していたように思います」
小学校と中学校が一体化したその学校では当時、年に一度、生徒と教師が作文を書き、一冊の分厚い冊子にまとめて配られた。モリ少年が目を奪われたのは、教師たちの作文だった。
「この学校に赴任して1年、すごく自由を感じている」と浮かれた様子の教師もいれば、「ルールを守らない生徒を叱って嫌われるなら、率先して嫌われる」と憤る教師もいた。共通していたのは、個々の正直な内面が記されていたこと。初めて教師をひとりの人間として見たモリ少年は、そこに「自由」の息吹を感じた。
モリさんにとって、日本人学校での生活は「ただただ楽しい」思い出しかない。しかし、学校の外に出ると、そこには歴然とした「格差」が存在した。町を歩けば、日本人は誰もが「金持ち」扱いを受けた。路上では、自分と変わらない年齢の子どもが商売をしていた。その様子を見て、モリ少年の胸のうちに「なんだこのシステムは?」という違和感の種が芽生えた。
トンチンカンなことを繰り返す日々
モリ家は、2年間ジャカルタで過ごした後に帰国。千葉の幕張で、新生活が始まった。地元の小学校6年生に編入したモリ少年は、中学校に上がってすぐ、生きづらさを感じるようになった。
中学校では、先輩には敬語で話し、指示をされれば従うのが当たり前だった。そのコミュニケーションが、どうしようもなく苦手だった。
「指示をされた時、内容がよくわかっていなくても聞き返せないんです。聞き返すと苛立たせちゃうから、とりあえずハイって言う。それから、今先輩が言ってたのはこういうことかな?ああいうことかな?と想像するんだけど、的外れなことが多くて、怒られる。気持ちは素直なのに、行動がいつもトンチンカンみたいなことが中学校時代くらいから起こり始めました」
それは高校生になっても変わらず、アルバイト先でも指示通りにできずに叱責され、居場所がなくなって辞めるということが続いた。
モリさんが通った商業高校は、卒業後に就職する生徒が多かった。しかし、「こんな自分になんの仕事ができる?」と不安が募ったモリさんは、就職を遅らせたい一心で大学に進学した。
バンド活動に明け暮れて

大学に入学するとすぐに、友人から誘われてバンドを始めた。「音楽で食べていきたい」というメンバーと平日は練習、週末はライブに明け暮れていたが、ひとり「楽しければいい」と思っていたモリさんは次第に疲弊し始めた。
「僕らがライブをする時は、自分たちでチケットを買って売っていました。当然そんなに売れないから、バイト代がチケット代に吸収されていく。ライブが終わったら、ライブハウスの人や出演者と酒を飲んだりするんですけど、それも苦痛で。次のライブのために、ライブハウスの支配人に気に入られようとか、出演者同士の繋がりを作ろうとか、このシステムはなんなんだよ!って」
バンド活動で埋め尽くされた学生生活に疑問を抱き始めていた時、ある雑誌が企画したアイスランドがテーマのイベントに足を運んだ。会場では、同国のバンドのライブ映像が流された。
そのライブの会場は森のなかで、観客は子連れも多く、ピクニックをしたり、寝そべったりしながら、心地よさそうに音楽に浸っていた。モリさんは目からウロコが落ちるようだった。
「僕の周りには、30代、40代でアルバイトをしながら、必死に『プロのミュージシャン』を目指している人もいました。でも、この自由な感じのライブを観た時に、音楽で稼ぐのがミュージシャンっていうことじゃなくて、音楽を楽しみながら演奏する人だってそう名乗っていいし、会社員をやりながら時々ライブをして安らかな生活が送れるなら、それでいいやと思えたんです」
この日、「ミュージシャン」という肩書きへのこだわり、そして「ミュージシャンはこういうもの」「ミュージシャンになるためにはこうしなきゃいけない」という狭い考えから解き放たれた森さん。
時を同じくして、ほかのメンバーも疲労を感じ、活動休止することになった。この時すでに大学3年生になり、社会に出るまでのタイムリミットに焦りながらも、自分になにができるのか、なにがやりたいのかわからかったモリさんは、書店巡りをするようになった。
現代を生きるみんなが迷子なんじゃ?

転機となったのは、下北沢の書店「気流舎」との出会い。カウンターカルチャーの専門書店で、書棚には一般の書店でなかなか目にする機会がないパーマカルチャー、哲学、思想、DIYなどの本が並んでいた。初めて訪ねた時、モリさんが手に取ったのは『就職しないで生きるには』。著者のレイモンド・マンゴーが、シアトルで小さな本屋を開くところから始まるこの本は、就職を恐れていたモリさんの心をグワッと鷲づかみした。
ピンとくるものがあって気流舎に通い始めたモリさんに、とてつもない影響を与えた本がもう一冊ある。スウェーデンの言語学者が書いた、『懐かしい未来 ラダックから学ぶ』。ヒマラヤの麓にあるラダックという地域で素朴に生きてきた人たちが、資本主義と近代化の波に翻弄される様子を描いた作品だ。
例えば、貨幣経済が浸透すると、男は都市部に出て稼がないといけなくなる。女性は、それまで担ってきた家事や育児に収入が伴わないため、それらに価値がないと思い始めてしまう。
また、欧米の文化やファッションを知ったことで、自分たちの伝統的な歌や踊り、服装に恥ずかしさを感じるようになっていた。

大学4年生の夏、就職活動がうまくいかず、この先どうすればいいんだろうと思い悩んでいた時にこの本を読んだモリさんは、ハッとした。
ジャカルタの路上で働いていた、少年。アルバイトですら長続きしないのに、大学を出たら、就職しなければ生きていけないと思い込んでいた固定観念。ミュージシャンという肩書きや、わかりやすい成功に囚われていた自分。
もしかして、資本主義と近代化によっていつの間にか「当たり前」になっていたレールに乗せられ、その上で競争させられていたのでは?
振り返れば、モリさんはずっと「この社会のなかで、どうやって生きていけばいいのか」が見いだせなかった。ラダックの人たちも、同じように迷い、怯え、苦しんでいるように感じた。
「もしかして、これは自分だけの問題じゃなくて、現代を生きるみんなが迷子なんじゃ?」
そう閃いた時、冒頭の言葉が浮かんだのだ。
「僕が、自分らしくて気持ちのいい生き方を見つけることができたら、同じように悩んできた人たちの希望になるはずだ」
そう確信したモリさんは、決意した。
「本屋になろう」
(つづく)
【写真】加藤 晴康
もくじ


モリ テツヤ
1986年北九州生まれ。インドネシアと千葉で過ごす。2011年に鳥取へ漂着。2015年から汽水空港という本屋を運営するほか、汽水空港ターミナル2と名付けた畑を「食える公園」として、訪れる人全てに実りを開放している。農耕、建築、執筆、焼き芋の販売、本の売買等、さまざまな活動を行う。
感想を送る