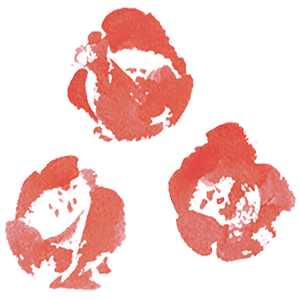数カ月後にパンデミックが起こることなど予想だにしなかった2019年10月、三浦直之さんと、本サイトで対談した。
そのとき彼が発した「名指せない感情」という言葉が、肯定の響きをまといながら、ずっと私の心の奥にはり付いていた。
喜怒哀楽からこぼれ落ちた感情の価値について、もっと考えたい。
この連載は、あのひと言が企画の種になっている。
そう話すと、三浦さんは「わ、そうだったんですね。嬉しいです」と控えめな笑みを見せた。
「4年経ちますが、ご自分や表現することへの想いなど、何か変化はありますか」
「すごい……本当に、たくさん変わった気がしますね」
あいかわらずのものすごい読書量。持参していただいた最近読んでいる本を、どれ一つ知らなくて恥ずかしくなった。
ゆたかな語彙からなめらかに生まれる言葉の数々に、私はついさっきの「たくさん」を、聞き流してしまった。対談を終えた時、ああ本当にたくさんのことが変わったんだ彼も私もと、いろんな意味で胸がいっぱいになった。
日々は言葉にできないことばかり

第十一回
宮城県出身。ロロ主宰。劇作家。演出家。2009年、主宰としてロロを立ち上げ、全作品の脚本・演出を担当する。自身の摂取してきた様々なカルチャーへの純粋な思いをパッチワークのように紡ぎ合わせ、様々な「出会い」の瞬間を物語化している。そのほか脚本提供、歌詞提供、ワークショップ講師など、演劇の枠にとらわれず幅広く活動中。2019年脚本を担当したNHKよるドラ『腐女子、うっかりゲイに告(コク)る。』で第16回コンフィデンスアワード・ドラマ賞脚本賞を受賞。次回公演は『オムニバス・ストーリーズ・プロジェクト(カタログ版)』(東京芸術祭 2023)を予定。
「呑気でありたい」
── 以前お目にかかったときからの変化について、聞かせてください。
三浦 ひとつは自分の年齢と、自分の書く言葉が、ちょっと折り合いがつかなくなってきたというのがあります。まだ、試行錯誤を繰り返しています。
── 今、おいくつに。
三浦 36です。30代なってからそう感じることが増えて。なんだか悩んだまま30代が終わりそうな感じもするんですけど(笑)。今、けっこうなかなか、あんまり書けなくなってて。
── 書けないときって、先輩たちはどうやって乗り越えたんだろうって、調べたりしますよね。
三浦 そう、スランプになった作家のインタビューを探して読んだり。角田光代さんが、正確な表現は忘れましたが、「30代半ばで自分の年齢と自分の文章が合わなくなってきた」というお話をされてて。それを洋服に例えていたんです。20代から同じ服をずっと着続けていると、ある時ふと「あれ、似合わなくなった?」と感じるみたいなことがある。それが自分の文章にも起きた、と。
── 角田さん、服の例えが秀逸! 本当に、あるあるですね。
三浦 すごく刺さりましたね。僕もそういう時期なんだろうなと。ひょっとすると、このまま「あれも似合わない、これも似合わない」と迷いながら30代は終わっていくのかもという気さえします(笑)
── 悩みがなくならないかもしれない、と。
三浦 それで周りに迷惑かけてしまうのは申し訳ないけど、僕は「なんか書けないんだよね」みたいなことを、呑気に言える人間でありたいと思っています。そのことに深刻にならないように。だから、こういう場でも、「今書けなくて」って言うようにしてるんです。
深刻にはならないように

── 深刻に考えないのはどうしてですか? 出口が見えなくなるとわかるから?
三浦 それもあるけど、なんだろうな、書く行為を神聖なことにしたくないっていうのかな。もう少しざっくばらんに、ラフにとらえたい。
── 私も時々、1行目は書けても2行目が全然書けないことがあって。色々考えだして、迷路に入って、連載10年は続けられたけど、11年目は無理な気さえしてくる。劇作家のスランプと私とでは、抱えている責任が全然違うんでしょうが、ちょっとだけ呑気でいたいっていうの、わかります。今2行目が書けないから原稿から離れて、お茶でも飲むかとか。その後、どうにか書けるんだけれど、このちょっとした恐怖感と私は一生隣り合わせで生きていくのかなというのは、また別の恐怖としてあります。
三浦 もうひとつ、これは僕の個人的主観なんですけど、とくに男性は歳を重ねていくと、弱音を吐きにくくなるなあと。それで孤独をつのらせている人もいるんじゃないでしょうか。僕自身も、やっぱりどんどん周りに弱音吐きづらくなってるし、演出家はどうしても引っ張ってく立場だから、とくに言いづらい。
── だからって弱音を自分の中に溜め込むんじゃなくて、もっと呑気でいたいと。
三浦 はい。呑気に弱音を吐いて、聞く人も別にそんなに深刻に受けとめなくてよくて、お互いにうまく聞き流したりして。弱音を吐くことのハードルを下げておきたいって思います。
── 弱音のハードルを下げるって、誰も言ってくれなかった発想ですね。確かに、人それぞれのいろんな理由や事情で、弱さを出しづらい社会かもしれない。
三浦 たぶん、弱音を吐かないという美学のようなものは、昔はもっと根強かったと思います。だからこそ、積極的に弱音を吐いて、そういうものを脱いでいくことをしていきたいです。
たくさんのことが変わった

── 劇団との向き合い方は変わりましたか。あの頃、チケットが即ソールドアウトという時代でしたが、コロナ禍に突入しました。
三浦 今よりあのときは、もう少し明るいビジョンを持っていた感じはしますね。『四角い二つのさみしい窓』という、ひとつ自分の中で大きな目標にしてた作品をやって。それから、長く続く『いつだって可笑しいほど誰もが誰か愛し愛されて第三高等学校シリーズ』を終わりにして。次に新しい何かを探そうと、わくわくしていた。以来、コロナを含め、自分の価値観が大きく変わることが続きました。
── 4年前の対談では、失恋のお話も出ていましたよ。
三浦 ははっ。ここでその話したんだ僕。この前、教えている大学の学生から「もう失恋から立ち直ったんですか」って聞かれて、「なんでそれ知ってんの!?」って(笑)
── 学生さんがこのサイトを読んでくれてたとしたら嬉しいです。その後のコロナ禍は、演劇界には試練だったのでは。
三浦 動員も厳しかったですが、演劇界隈はハラスメントのニュースをすごく聞くようになりました。どういうクリエーションの空間をつくれば、誰もおとしめられずに、ゆたかな稽古場ができるのかと悩んだ。自分が演出家として誰かを傷つける振る舞いはしたくない。それまで自分がやってきたことの反省もありますし、色々とすごく考えるようになりました。
── 稽古もマスクを付けて、距離をとって、コロナになるかもという緊張感でストレスもありますよね。
三浦 僕はそれまで、演劇のいちばんの魅力は、人と人が集まることだと思ってたんです。稽古で俳優やスタッフが集まり、時間をかけて一歩ずつ先に進む。劇場で、俳優と観客が出会う。人の集まる場所を作るのが演劇だと。リアルで人と会うことがすごく大事だと思っていたので、それが難しくなっていったとき、最初すごく抵抗がありました。
── それは大きな体験ですね。演劇のあり方を考え直さなきゃいけないから。
三浦 でもひとりでいる時間が増えて、むしろ今は人に会うのが億劫になっていて、その自分にも、うまくバランスが取れなくなっています。人ってこんなに慣れて、こんなに忘れるんだということもショックでした。今はもう「人と人が集まることってこんなに尊いんだ」と思ったことすら忘れかけている。あのマスクを着けてた頃の感覚も。いつの間にか慣れてしまうことに対する怖さを感じますね。
しかし、コロナによって大きな気づきもあったという。
当初は、演劇の配信に抵抗があった。ライブ感がなければ意味ない。だが、そうも言っていられない状況下でいざ試みると、育児のために劇場に行けなかった人や様々な事情で足を運べなかった人の存在に気づく。
三浦さんは、最近読んだ芥川賞受賞作の『ハンチバック』でも、さらに想いを深めた。
主人公は寝たきりで、健常者を前提とした読書文化の特権性に対する怒りを呪詛のように吐き出す場面がある。
「自分がいかにそういうことに無頓着だったか、思い知らされました。劇場に来るってものすごくハードルが高い。移動して、劇場に来て、ある程度するチケット代を払うことができて。そうできない人たちもいる。コロナは、劇場が大事だ、集まりが大事だ、なんて言える自分の無知に気づくきっかけになりました」
聞きながら私は、友達と食事に行くか行かないか、取材はオンラインか対面か、コロナ禍の毎日が大小の選択の連続だった苦しさを、もう忘れかけている自分に驚いた。
繊細な目で自分の内側を見つめる三浦さんによって、幾多の記憶をすくい取る。
感動のリハビリをしたい

── 最初に、ご自分の年齢と書く言葉の距離に悩んでいるというお話がありましたが、今はどんなふうに折り合いをつけている最中なんでしょうか。
三浦 悩み中です。僕の創作の初期衝動は、何か書きたいことがあるというよりかは、10代の頃にいろんなものを読んですごく感動して、自分もこういうのを描きたいというところから始まってます。でもSNSなどをやっていくと、だんだん、その、誰かの感動に影響を受けたのではとか、自分のこの感動は誰かの感動なのかもしれない、みたいにわからなくなってきたんです。
── ああ、なるほど。旅に行く前からいろんな情報をネットで集めすぎてしまうと、誰かの感動をなぞるだけになってしまうような。
三浦 はい。話題作が絶賛されていると、僕はこれを見たら絶対に感動するんだろうなとわかってしまって億劫になる。
── それ、つい最近、雑誌に高橋源一郎さんが書いていらっしゃいましたよ。いつの間にか我々はSNSのおかげで、感動する前に感動が約束させられ、誰かの評価が刷り込まれた状態で見ることが習慣となり、自分のオリジナルの感動を持ちづらいって。確かにそうだなあと思いました。
三浦 まさに同感です。だから感動するリハビリをしたいと今は思っています。心が動くのは疲れるけど、億劫だと避けるんじゃなく、10代のときのように、思わず体が動いてしまうような、そんな感動を味わう時間をもう1回取ろうって。
── 感動のリハビリに、小説は効きそうですね。
三浦 そうですね。文章を読んでいて、何に感動するかっていうと、期待や予測を裏切られる瞬間だと思うんです。その最たるものは詩ですよね。僕らは、ふだん無意識に想定している流れがあって、先を予測しながら読んでいる。そこが裏切られていく瞬間に満ちた作品は惹かれるし、心を動かされます。
── 小説や詩もそうですが、意外にエッセイも、裏切られるおもしろさってありますよね。短い分、小説以上に予測しやすく、起承転結の「起」を読んだら、おそらく「結」はこういくだろうみたいな。この対談でよく話すんですが、詩人の長田弘さんの詩集やエッセイにはそれが全く無い。思いがけない表現の連続で、裏切られるおもしろさ、言葉の美しさがあるんです。
三浦 読書の喜びってそこにあると思いますね。今は執筆期間なので、とくにそういう、予測できない美しい文章に触れたいというのがあります。凝り固まっているものをほぐすように。
この感情と一緒にどう生きていくか

三浦 コロナに入ってまもなく、たとえば僕はそれまでも死を作品で扱ってきたのですが、何もわかってなかったんじゃないか、自分は何も書けてなかったんじゃないか、と考えさせられる出来事がありました。そこから抱き続けている寂しさの質は、これまでと違う。もうちょっと前は、その寂しいというものを、距離を置いて見つめられていました。
── 4年前も、“自分の寂しいというのは、こういうかたちをしているんだな”というようなお話をされていました。
三浦 それが、今は近すぎて見えていない。自分との距離感がよくわからなくなっちゃったんです。
── 私は今、吃音の方のノンフィクションを書いているんですが、当事者のお話を聞いて、何もわかっちゃいなかったなと無力感を味わうことの連続です。社会を知ったような顔でいたけど、今まで私は何を書いてきたんだろうと。
三浦 大平さんもいろんな方にお話聞いてるから、そういう感覚があるんですね。僕は宮城の被災者の方にお話を聞いて作品を書いたことがあるのですが、あのとき僕は聞いてるつもりでいたけれど、本当に聞けたのかな。じつは何も聞けなかったんじゃないか。今になって自問自答している。その繰り返しです。
── この連載は三浦さんで11回目になりますが、今頃やっと寂しさにも切なさにも多様な濃淡がある。聞いているつもりで、時には答えをもらったようなつもりで書いてきたけど、そんな簡単に言葉で表せないもの。だから名指せない感情なんだし、だから尊くて苦しくてかけがえがないんだと、気づきはじめたようなありさまです。
三浦 なんていうか……、自分が経験したことに、自分が負けたくないっていう気持ちがあります。だから、どういうふうに、この経験を人に話せるようになるか。どんなふうに言葉にできるんだろうと考える。自分の課題ですね。

長い思考の旅になるのかもしれない。それは乗り越えるとか、前向きに頑張るというものでは決してない。
4年前と同じ人が口にした「寂しさ」「切なさ」は、全く違う質と温度で、私の前に提示された。
それらの感情と一緒にどう生きていくか。考えるのは疲れるし、億劫だ。でも、三浦さんからは一度も、「放り出す」「逃げる」という言葉は出ていない。
劇団ロロの芝居を観ると、人間ってめんどくさいし、世の中は生きづらいか生きづらくないかと言えばけっこう前者だけど、そんな毎日でもいつだっておかしいほど愛し愛されあって、人は生を支え合っているんだよなと、元気になれる。
失ったものがない人などいない。きっと、ほとんどの人が「ずっと寂しい」。
呑気でいたい、弱音のハードルを下げておきたいという彼の言葉に、小さく救われる人は少なくないだろうと思った。私のように。
次回公演
東京芸術祭 2023 直轄プログラム FTレーベル
ロロ『オムニバス・ストーリー ズ・プロジェクト(カタログ版)』
2023年10⽉7⽇(⼟)〜15⽇(⽇)
東京芸術劇場 シアターイースト
テキスト・演出:三浦直之(ロロ)
出演:大場みなみ 北尾亘(Baobab) 田中美希恵 端田新菜(ままごと) 福原冠(範宙遊泳) 松本亮
https://tokyo-festival.jp/2023/program/lo-lo/


長野県生まれ。編集プロダクションを経て1995年独立。著書に『男と女の台所』『ただしい暮らし、なんてなかった。』(平凡社)、『届かなかった手紙』(角川書店)、『あの人の宝物』(誠文堂新光社)、『新米母は各駅停車でだんだん本物の母になっていく』(大和書房)ほか。最新刊は『それでも食べて生きてゆく 東京の台所』(毎日新聞出版)。 インスタグラムは@oodaira1027
大平さんのHP「暮らしの柄」
https://kurashi-no-gara.com
撮影:丸尾和穂
協力:東京芸術劇場
感想を送る