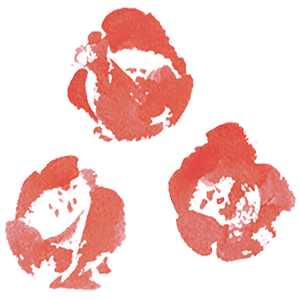朝のカーテンの隙間からこぼれる光、淹れたてのコーヒーを注ぐときの湯気、ふと目にとまった足元の木漏れ日。
忙しなく過ぎてしまう日々にも、あぁ好きだなと思う瞬間や、忘れてしまうのはもったいないと感じる景色があります。
日記や手帳に言葉として残すひともいれば、いまは手軽にスマートフォンのカメラで動画や写真を撮って記録するひとも多いかもしれません。

今回ご紹介するのは、世界最小・最軽量*のフルサイズミラーレスカメラ SIGMA fpです。
SIGMA fpは、プロからも高い支持を得る本格的な撮影機能を兼ね備えながら、気軽に持ち運べるサイズ感のカメラです。
*2024年4月現在。ドローン用機器を除く
(この記事は、SIGMAの提供でお届けする広告コンテンツです)
どんなふうに「今」を残したいんだろう
 ▲土門蘭さんの著書『死ぬまで生きる日記』は、「生きづらい」という気持ちを片隅で抱えてしまう、ままならない自身と向き合った2年間をあるがままに記録した一冊
▲土門蘭さんの著書『死ぬまで生きる日記』は、「生きづらい」という気持ちを片隅で抱えてしまう、ままならない自身と向き合った2年間をあるがままに記録した一冊
美しく、自分らしく写真を撮れたら素敵だなと憧れはあっても、プロ仕様の本格的なカメラと聞くと「初心者には操作が難しそう」という不安がよぎります。
そこで私たちと一緒に考えてくださったのは、当店でお届けしていた連載エッセイでもお馴染み、旅と本をテーマにしたドラマ『スーツケース・ジャーニー』の脚本も手がけた、京都在住の文筆家・土門蘭(どもん らん)さん。

「文章を書くことは、自分の心や記憶の一部を結晶化すること」という土門さんが、カメラを持って写真というかたちで今を残すとき、どんなふうに感じるのでしょうか。
SIGMA fpを実際に使ってありのままに感じたことを、特別にひとつのエッセイに綴っていただきました。
特別エッセイ
「私らしい世界のとらえ方」

ずっと写真を撮るのが苦手だった。
長男が生まれた時にコンパクトデジタルカメラを買ったが、思うように使いこなせなかった。次男が生まれて今度はフイルムカメラに挑戦したけれど、コンデジよりもずっと難しくて挫折した。結局、手軽なスマートフォンで撮影するに落ち着いて今に至る。
好きな写真集や、写真の上手な友人のSNSを見るたびに、「こんな素敵な写真が私にも撮れたらいいのになぁ」と思う。だけど実際に自分が撮ったものを見ると、あまりいい感じに撮れていなくて少しがっかりする。理想が高すぎるのかもしれない。
それでも目の前の人や光景の、美しい、愛しい一瞬を留めたくてシャッターを押す。その気持ちだけで十分なのだと半ば諦め、誰に見せるわけでも見返すわけでもない写真を撮り続けた。カメラロールに膨大に溜まっていく記録用のデータ。私にとって写真はそういった意味合いのものだった。
§
そんな私に先日、SIGMAのカメラを使ってみないかというお声がかかった。
一眼カメラなんて触ったことさえないのに大丈夫だろうかと心配になったが、写真に対する苦手意識を変えるチャンスかもしれないと考えて、喜んでお受けすることにした。
壊さないようにと気をつけながら、送られてきたカメラを首に提げる。手のひらに収まるサイズだけど、凛とした存在感があった。試しに構えると、子供たちが「かっこいい」と言った。一枚撮ってみたら、明らかにいつもより雰囲気のある写真になっていて、みんなで覗き込みながら「すごいね」「さすがやな」と驚いた。

週末、子供たちが近所の川に遊びに行きたいと言うので、「そうだ、カメラを持っていこう」と思って首に提げて出かけた。それだけで、まるで今から旅行に出かけるような気持ちになって、少しワクワクした。
いつもの道や川なのに、カメラを通して見るとどこか特別に感じられる。私は子供たちの前や後ろを歩きながら、シャッターチャンスを探し続けた。彼らの表情、彼らの動き、彼らの背景。
まるで、今まで閉じていた目がパッと開いたように、見過ごしていたものがいくつも視界に飛び込んできた。大きな空の雲の隙間から光が差し込んでいること。その光が川面で輝いていること。子供たちが子犬のように遊んでいること。


ああ、これはすごいなと思う。カメラを持って歩くだけで、こんなにも世界の見え方が変わるのか。カメラ越しに日常の風景を見つめながら、「今日はいい日になるんだろうな」という予感がした。なんだか今日は、たくさんのいい光景を見られそうな気がする。
一枚、また一枚とシャッターを押すたびに、予感は意志に変わっていった。いい光景を、ちゃんと見ようという意志。
「うん、いい写真」
そう言うと、カメラの向こうで子供たちが笑った。
§
その後も、打ち合わせや食事など、気の置けない人と会う時にはカメラを持っていくようにした。
首からカメラを提げてやってきた私を見ると、みんな「どうしたの」と驚く。「今日、写真撮ってもいいかな」と聞くとOKしてくれるのだが、カメラを構えると、なんとなくその場の空気が変わるのがわかった。少しの緊張と照れ臭さ。なんだかこちらまで照れ臭い。
私はシャッター音を消して、カメラ越しに友人たちの表情を見つめた。笑顔、はにかみ顔、真面目な顔、喋っている顔。それから一緒に食べているご飯や、飲んでいるお酒やお茶も。撮っているうちに、少しずつ緊張が和らいでくる。
ピントを合わせ、一瞬を捕まえる。いい表情が撮れると嬉しい。それは、スマートフォンで撮るのとは違う感覚だった。まるでカメラを下から支えるこの手で、一瞬一瞬の質量を慈しんでいるかのような。
撮った写真をその場で見せると、友人たちは「おっ、いいやん」とか「味があるね」とか口々に言ってくれた。
「そうでしょう?」
私は満足して答える。するとある友人が「嬉しそうだね」と笑った。
「うん、嬉しい」
写真に収めると、過ぎ去った一瞬が手元に形として残る。それを見返してようやく気づく。「今私は、大切な時間を過ごしているんだな」と。
その時間をちゃんと大切に扱えていることが、とても嬉しい。



§
家に帰って、撮った写真を友人たちに送った。
スマートフォンにデータを取り込んで、メッセージとともに送る。するとある友人から、こんな言葉が返ってきた。
「土門さんの写真は個性があるね。憂いと湿度があるっていうか」
憂いと湿度。そんなことは考えたこともなかったので驚いた。言われてみると、確かにそうかもしれない。
このカメラは明暗も色味も自由に設定できる。だから撮る時に液晶画面を見ながら、自分がしっくりくる見え方を模索しつつ設定を変えるのだが、いつも自然とこの色調になるのだった。
友人の言葉を読んで、「そうか、これが私の個性なのか」と思った。その時初めて、自分が「撮りたい写真」を撮れていることに気がついた。
今まで自分の写真を好きになれなかったのは、自分から見た世界と写真に映る世界が乖離していたからなのかもしれない。友人の言葉を借りれば、少しの「憂いと湿度」を、私は写真にずっと求めていたのかもしれないな、と。
「写真には、その人の世界の見え方が表れるのかもね」
そう返信して、もう一度自分の撮った写真を見た。
私には、世界がこう見えている。私らしい、美しさや愛しさの感じ方。
SIGMAのカメラが、そのことを私に改めて教えてくれた気がした。

文・写真 土門蘭
カメラを持つ先にいい光景、いい表情が待っている気がして
 ▲SIGMAのものづくりの拠点は、清廉な空気と水に恵まれた福島・会津。一つひとつの品質を追求するため、すべての部品を日本で製造しています*
▲SIGMAのものづくりの拠点は、清廉な空気と水に恵まれた福島・会津。一つひとつの品質を追求するため、すべての部品を日本で製造しています*
はじめて本格的なカメラを手にした土門さん。「どこかに出かける時、SIGMA fpを持つと、その先にいい光景、いい表情が待っているような気がして、なんだかすごく嬉しかった」といいます。
土門さん:
「マットな黒のシンプルな佇まい、すごくかっこいいですよね。『いいカメラを持っているな』という特別感が味わえる手触りというか、首から提げて持つだけでテンションが上がっちゃいました。
はじめての機械を操作するときって、わからなさゆえに怖いと感じてしまうときもあるのですが、SIGMA fpはボタンが少ないからか触りやすい。不思議と安心感を持って操作できました」
*安心して長くお使いいただくための、アフターサービスも充実。故障などの対応は、福島県の修理センターにて一つ一つ丁寧に行なっています。故障かどうかよくわからない場合でも、まずは窓口にメールすると相談にのってもらえます。
 ▲クラシカルで品のある雰囲気。持ち物としても側に置いておきたくなる佇まいです
▲クラシカルで品のある雰囲気。持ち物としても側に置いておきたくなる佇まいです
土門さん:
「SIGMA fpにはカラーモードという、撮影した瞬間から自分好みの色味にしてくれる機能があるんです。
とくにお気に入りは、『パウダーブルー』というモード。捉える光が柔らかくなって、淡い青みを帯びた、どことなく切なさを感じる写真になります」
 ▲液晶画面下のボタン「COLOR」から好きなカラーモードを選択。撮った瞬間から雰囲気のある一枚に
▲液晶画面下のボタン「COLOR」から好きなカラーモードを選択。撮った瞬間から雰囲気のある一枚に
 ▲スタンダードモード(写真左)、パウダーブルーモード(右)。SIGMA fpで土門さん撮影
▲スタンダードモード(写真左)、パウダーブルーモード(右)。SIGMA fpで土門さん撮影
土門さん:
「シャッター音の有無も自分で選べるので、たとえば友人や子どもたちと一緒にいるときなんかも何気なくシャッターを押せて、彼らの自然な表情を切り取ることができるのもいいなと思いました。
自分好みの設定を覚えてくれる機能もあって、毎回設定を確認して変更しなくてもいいのも便利です」

 ▲フォーカスの範囲や位置も液晶画面から簡単に変更できます
▲フォーカスの範囲や位置も液晶画面から簡単に変更できます
土門さん:
「SIGMAの担当者の方が『これは自分自身が描きたい世界を描けるツールなんですよ』とおっしゃっていて、その一言にすごくワクワクしました。まだまだ、SIGMA fpで撮りたいです」
そうお話しする土門さんの手にしっくりとカメラが馴染んでいるようにみえました。
【写真】井手勇貴(1-4枚目、13-18枚目)


土門蘭
1985年広島生まれ。文筆家。京都在住。小説、短歌、エッセイなどの文芸作品や、インタビュー記事を執筆する。著書に『100年後あなたもわたしもいない日に』(寺田マユミ氏との共著)、『経営者の孤独。』、『戦争と五人の女』、『そもそも交換日記』(桜林直子氏との共著)。最新刊として2023年春に『死ぬまで生きる日記』を上梓、第一回「生きる本大賞」を受賞。
感想を送る