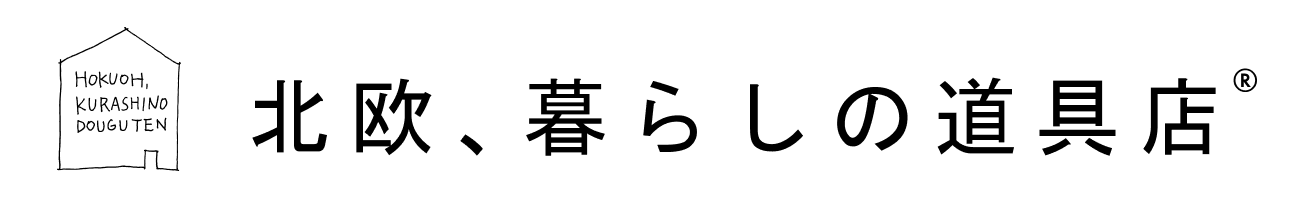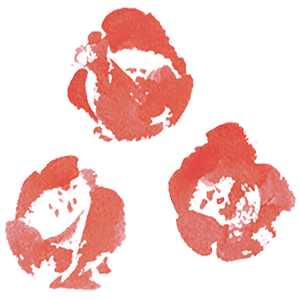新しい人との出会いや関わりが増えるこの季節。「句点。に気をつけろ」の著者であり、インタビュアー・作家の尹雄大さんを訪ね、新生活のコミュニケーションについて一緒に考える前後編をお届けしています。
前編でたどりついた、コミュニケーションのときの「イメージしていた自分とは『別の自分』にアクセスする怖さ」。後編では、これをもう少し噛み砕いて向き合うところから始めてみましょう。
はじめましての自己紹介で、自分をうまく伝えるには

突然ですが、ちょっと想像してみてください。はじめましての自己紹介の場面で、あなたが不安に思うのはどんなことでしょうか。
自己紹介ですから、無愛想な怖い人だと思われたくありません。スラスラ話したいし、好印象を残したい。サクッと短くまとめつつも、あわよくば少しの笑いを誘えたらなお良し。わたしなら、こんなところです。
けれども理想が膨らむほどに緊張は高まり、結果、気の利いたことは言えずに気持ちだけが空回り。「思い描く自分」とは別の自分があらわになり、そこから目を背けたくなるような経験を、これまで何度も繰り返してきました。

尹さん:
「よく見せたい、評価されたいと思うことは誰しもありますよね。でも、そこに真正面から向き合うと、ちょっと痛々しく辛いことになってしまいそうです。
ならば娯楽的に、エンターテイメントとして捉えるのはどうでしょう。自己紹介なら、かっこよさやウケを狙うのではなく、自分が楽しめたらいいな、という感じです。結果として、双方がうまく噛み合って楽しんでもらえたら最高ですが、そうでなくても、『楽しもう』としている様子の先に、その人柄は見えるとおもいませんか?
自己紹介は、自分のことを知ってもらうためのものですよね。楽しみたい、そしてできれば少しでも楽しんでもらいたいという人柄が見えれば、それは結果的に、自分を知ってもらうことになると思うんです」
繰り返しのグルーヴにこそ大切なことが詰まっている

さらに、「スラスラと話す=良いコミュニケーション」だと考える必要もないと尹さんは続けます。
尹さん:
「音楽では強めたい部分を何度も繰り返し、聴いている方もそのグルーヴに身を委ねて、体を揺らします。それなのに、どうして言葉になると冗長なおしゃべりや、何度も同じことを話すのは嫌がられたり、繰り返しをムダと捉えてカットしようとしたりするんでしょう。
むしろコミュニケーションの言葉も、繰り返し、つまりグルーヴ感のある部分にこそ大切なことが詰まっているとも考えられませんか?
みんな、意味を欲しがっている気がします。意味をつかまえることがコミュニケーションであり、伝えたらわかると思い込んでいる。端的に話そうとして『要するに……』とまとめたり、あるいは相手の話を『それってつまりこういうこと?』と、要約して返したり。けれども、これは傲慢なことではないかと考えるようになりました」
合理的な一本道より、道草の途中にその人らしさが見える

そう考える背景には、尹さんが主宰する「インタビューセッション」がありました。
「その人の話を “その人の話” として聞く」というセッションの場では、必要なのは、ただ話をすること。世の中の答えではなく、自分の答えを見つけるために話してもらい、ただ聞くという時間を多くの人たちと重ねてきたのです。
尹さん:
「あるとき、こちらが受け答えをする前に『要するに、こういうことだったんですよ』と、何度も言う方がいたんです。僕はそれに対して、『要するに、ではなく要さないで伝えてもらえませんか?』と伝えてみました。
そうすると、話のあちこちにディテールが見えてくるんですね。
たとえるならば、家から会社までの一本道が、『要するに』で聞いていた話。でも詳しく聞いていくと、その道端に転がっている石や、咲いている花の色やかたちが見えたり、道草する遠回りの景色が現れたりもします。
会社に行くことだけを目的にしていれば、そのディテールに意味はないかもしれません。でも、つい目を向けたくなるものがある。これこそが『その人らしさ』であり、ほんとうに伝えたいこと、あるいは大切にしたい感覚だと思うんです」
効率重視の時代だからこそ、会話に「ノイズ」を走らせる

伝え方が難しい、というシーンはほかにもたくさんあります。
たとえば職場に新しく入ってきた後輩に指導する立場になったとき。分からないことがあり困っているのなら、その「困っている」という事実を伝えてもらいたい。前編では尹さん自身が「言えなかった」エピソードを紹介しましたが、裏を返せば先輩にしてみれば「言ってもらわないと困る」場面だったともいえます。でもこれが、なかなか難しいのです。
尹さん:
「こちらとしてはどんな些細なことでもいいから、何につまずいているのか、つまずきそうなのか、それを話してもらいたいわけです。でもここで『何か困ってることある?』って聞くと、相手が萎縮しちゃうこともあります。
そういったことは、それこそ普段の会話で伝えてもらうのが一番です。かしこまった場より、ノリで話しているときにはその人の価値観や人柄が出ます。その人らしさが見えると、人は心が開くし、相手に『あ、話してみようかな』と思うようになります。
僕はそれを『ノイズを走らせる』と呼んでいるんです。たとえば『今朝、通勤電車でこんな人がいてね〜』と、なんでもない会話を振ってみるとか」

効率重視の社会からはみだした、いわゆる雑談、茶飲み話。そんな、さもない話の中に、その人らしさが垣間見えるのだといいます。
そういえば今回の取材も、玄関先での「はじめまして」から、レコーダーをオンにする「それでは」の間に、いくつもの小さな雑談がありました。鹿児島つながりの話からふいに飛び出した、「都内なら宮崎物産館のチキン南蛮がおいしいんですよ」という些細な会話。取材にはまったく関係ありませんが、そこで緊張がほぐれ、楽しく取材がはじまったのです。

尹さん:
「もし自分が先輩の立場で、後輩との接し方や、何を話せばいいのか分からず悩んでいるのなら、それを思い切ってオープンにしてみてはどうでしょうか。
困っている相手がいたら、助けたいし力になりたいと思いませんか? それなのに自分の困りごとはひとりで解決しようとするなんて、自分に対してちょっと厳し過ぎますよね。
僕も、講座やセミナーを始めたばかりの頃は『金返せ!』『つまんないぞ!』なんてヤジが飛んでくるんじゃないかと悪い想像をしては、ハラハラしていました。しゃべり方だって、ちっとも上手じゃないですし。
でも、そんな怖い人なんていませんから。みなさん、どんな話し方でもちゃんと聞こうとしてくれるんですよね。人はみな、わかりたいと思っている気がするんです」
言葉にならないモヤモヤは、まずは「音」にする

モヤモヤしているけれど、言葉にならない。伝えたいのに、うまく言葉がみつからない。そんなときにおすすめなのは言葉を「音」として捉えることだといいます。
尹さん:
「そのモヤモヤが、身体的にどういう感情なのか、それにふさわしい音があるならどんな音なのか、言葉になる前振りのようなものを考えてみるんです。『わー!』でも『ぐおー!』でも何でもいい。音、音階、調子。そんな言葉になる前の声を発してみてください。
実際にやってみると、それに引っ張られて言葉が出てくるようになることがあります。モヤモヤって頭ではなく、心で感じていることですよね。その心を音でキャッチするイメージです。
自分の中には感情、感覚、言語、それぞれを求める自分がいる。言語が優位で偉いわけではなく、それぞれを大切に扱うことでコミュニケーションは成り立つのだと思います」
英語を喋れるようになる瞬間は、頭の中に文法を並べる前に、自然と言葉が出るといいます。自転車も、右、左とペダルを漕ぐ理屈よりも、感覚的に体が覚えることで乗りこなせます。そう捉えれば、言葉が必ずしも解決とは限らないと思えませんか。
わたしたちには、相手を感じ取る力がある

尹さん:
「日本語には『ふるまい』『たたずまい』という表現があります。いい感じを与えるような言葉を意図的に発しているわけではないのに、なんとなく『いい感じ』を受け取りますよね。それなのに自分が発言するときには、『誰も聞いていないかもしれない』『スラスラ話せないと、印象が良くない』と思ってしまう。
相手のことは感じ取れる。感じ取ろうとしているのに、自分にはそんなことが絶対に起こらないと信じてしまうんです。
僕たちには、感じ取る力がある。そのことを、もっと信頼してみませんか?」

コミュニケーションというと、どう伝えるかというテクニックばかりに気を取られていたように思います。
ところが最後に辿り着いたのは、自分の心の中でした。自分の言葉を、最終的にどう受け取ってもらうかは相手が決めること。コントロールするのは、なかなか難しそうです。
でも、自分を開いて、信じることならできそうな気がします。スラスラと、あるいは論理的に考えをまとめるような「上手に話す」ばかりにとらわれず、まずは「にっこり」を目指してみようかな。きっとその先に、互いに気持ちよくいられるコミュニケーションがあると思うのです。
【写真】神ノ川智早
もくじ


尹雄大/Yoon WoongDae/ユン・ウンデ
インタビュアー、作家。1970年神戸市生まれ。政財界人やアスリート、研究者、芸能人など約1000人にインタビューを行ってきた。その経験を活かし、2017年から「その人の話を”その人の話”として聞く」というインタビューセッションや講座を開催している。主な著書に「さよなら、男社会」(亜紀書房)、「モヤモヤの正体」(ミシマ社)、「脇道にそれる」「やわらかな言葉と体のレッスン」(ともに春秋社)、「体の知性を取り戻す」(講談社現代新書)、「聞くこと、話すこと。」(大和書房)などがある。
公式サイト: https://nonsavoir.com/
X: @nonsavoir
感想を送る