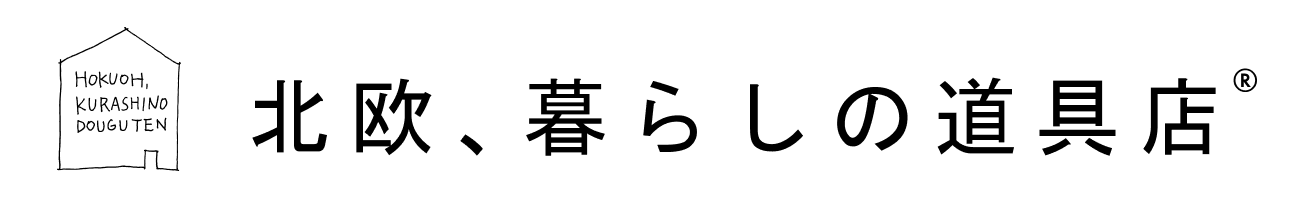誰かの何気ない一言に落ち込んだり、何かの出来事により孤独感を味わったり。そんな日常の「傷」について、精神科医でありトラウマ研究の第一人者でもある
宮地尚子
さんと一緒に考える特集。前編では、宮地さんがトラウマを研究するようになった経緯や、オンラインのコミュニケーションが浸透した現代ならではの “複雑な傷つき” について伺いました。
続く後編では、傷つくことをできるだけ減らしていくための考え方や方法について、それでも決してゼロにはできない「傷」とどう付き合っていくかについて伺います。
傷つきを減らすツールのひとつは「想像力」
メールをした相手からなかなか返事が来なかった、もしくは返事が素っ気なかった。親しい人にごく小さな頼み事をしたのに、断られた。そんな時、自分が大切にされていない気がして傷つくことがあるかもしれません。
宮地さん:
「でも、もしかするとメールをもらった相手は無視するつもりは全くなく、すごく忙しかっただけかもしれないですよね。あるいは自分の病気や家族の介護など、なかなか打ち明けられない事情があって、こちらとしては軽い頼み事のつもりでも、それを引き受けられないほどいっぱいいっぱいなのかもしれません」

宮地さん:
「そもそも人間って機械ではないので、波があって当然で、その時々で反応が違うのが普通。でも人はどこかで、自分にも他の人にも波があってはいけないと思っているところがあるのでは。
相手は自分と違う時間軸で生きていることや、自分とは違う背景や事情を抱えている。そうした相手への想像力を持つことは大事だと思います。
それによって受け止め方はかなり変わってくるのではないでしょうか」
部分的でもいいから、逃げてみる
この人と話すと毎回傷ついてしまう。そんな相手との関係に悩む場合もあります。自分の度量が狭いからかも、と思って努力をしてみても、どうしても同じことが繰り返されてしまう。そんな時は「逃げることも必要」と宮地さんはいいます。
宮地さん:
「自分の度量ではこの人とは関われない、だから今は距離を置こう。それでいいのだと思います。
とはいえ、関係を断ちづらい人もいますよね。職場の人の場合、そう簡単に仕事は変えられないでしょう。そういう場合は100%でなくても、部分的に逃げるのでもいいんです。その人と関わらない時間や場所を少しでも多く確保すると、少し気持ちが変わってくるかもしれません。
もちろん、その人から逃げたいという気持ちもありながら、同時にその人とつながっていたいという気持ちもある場合だってあるでしょう。同じ人に対して両方の気持ちを持っていてもいいのだと思います」
宮地さん:
「家族もまた “逃げる” ことが難しい関係です。でも、たとえば週末にひとりでどこかへ出かけるとか、数時間でもいいので外を散歩してくるとか、部分的に逃げることを考えるといいと思います。
家族ってひとつのパッケージのようにして考えてしまいがちですよね。食事も旅行も、何でも一緒にするもの、みたいに。でも時にはそのパッケージを小分けにして、たまに食事を別にする、旅行も日中は別行動にする、といったことをしてみてもいいのでは。”家族はこうあるべき” という思い込みを少し緩めるだけで、気持ちが楽になって傷つくことが減るかもしれません。
家族だけで問題を抱え込もうとすると煮詰まってしまうので、オンラインカウンセリングなども含めて第三者に相談するなど、外から風を入れることも大事だと思います。あるいは動物や植物の世話など、他に目を向けるもの、クッションとなるものがあるのもいいかもしれませんね」
傷ついている自分って未熟なの?
宮地さんが教えてくださったさまざまな処方箋は、確かに気持ちを楽にしてくれそうです。それでも毎日人と関わる中で、どうしても傷つくことはある気がします。
けれどそんな時、自分の傷つきは他人と比べたら大したことがないと思い、気持ちに蓋をすることも。傷ついている自分が未熟だと感じて落ち込むことも少なくありません。
宮地さん:
「以前より傷つきを口にしやすくなった一方で、ポジティブ思考という考え方が広まっていて『いつまでも引きずらないで乗り越えよう』『ネガティブをポジティブに変えていこう』という言葉が増えていますよね。それができない自分はダメな人間だと思ってしまう。
特に普段は家事や仕事をある程度こなしている人ほど、そのプレッシャーがあるのかなと思います。SNSなどでも、投稿されるのはポジティブなことがほとんどなので、それを目にしてよけいに落ち込む人もいるでしょう。
私もポジティブなことを語ることがないわけではありません。でも著書の『傷を愛せるか』に込めたかったメッセージは、 “傷は治る” ではなく “傷を抱えたままでもいいじゃない” ということです。
本にも書きましたが、 ” 傷を愛せない私を愛する” こと、つまり自分の弱さを受け入れることが大事なのかなと思います」
宮地さん:
「精神科医としても、患者さんの状態がよくなるように診療に取り組んでいますが、それは傷をなくすということとはちょっと違います。『今はその傷だけが全画面表示になってるけれど、実はほかの景色もありますよね』とか、『ちょっと見方を変えてみるとこう見えますよね』とか、そんなアドバイスをする感じです。
傷が癒えるまでの過程や方法は人によって本当にさまざま。医師としては、その人が何か新しいものを見つけていくのを信じて待つ感覚なんです」
自分の傷や弱さを認め、人に話してみる
自分の弱さを認め、傷を抱えながら、それでも少しずつ回復していく。そのために、人に話してみることはとても大事だと宮地さんはいいます。
宮地さん:
「人に話すと『こんなことを自分は考えていたんだ』って、思っても見なかったようなことが口をついて出てくることもあります。話すことで自分の気持ちを整理できる。傷に向き合い、それを認めることができるんです。
自分では認めたくない傷であっても、相手に『そんなことがあったら誰でも傷つくよ』と言われたら、自分の度量の問題ではなかったと思えて安心するでしょう。自分は孤独ではないと思えることは、回復するうえでも大事なことです。
『こんなことを話したら嫌がられるかな』と思うのであれば、『ちょっとつらいことがあったんだけど聞いてもらえるかな』などと前置きしてみるのはどうでしょう。
もしも素っ気なくされても、それはたまたま相手のタイミングが悪かっただけかも。あきらめず、『余裕がある時に時間をもらえるかな』などと言って別の時に話したり、別の人に話してみるといいかもしれません」
宮地さん:
「傷つくのが怖くて踏み込んだ人間関係を避けようとする人もいるけれど、私はやっぱり人と人がリアルでつながるのは大事だと思います。人と直接言葉を交わすだけでも気持ちが変わるし、新しく世界が開けることもある。その際、失敗やトラブルがあった時のほうがむしろ人とつながりやすい気がするんです。
自慢話よりも悩みや失敗談のほうが、案外相手も聞いてくれるもの。それに、実はみんな悩んでいるし傷ついているんだとお互いに知ることができますよね。
お互いに見栄を張って、いいことばかり話すのではなく、情けないことやみっともないことをシェアできるようになれば、世の中はだいぶ楽になるのではないでしょうか。
もしも傷つくことがあった時は、『このことを誰かに相談してみよう』というふうに、人とつながるきっかけのひとつだと思ってみるのも手かもしれません」
生きていくうえで傷つきは避けられないものだから
宮地さん:
「傷つくのはとてもつらいことですし、もちろん不必要な傷つきは減らすべき。とはいえ、違う人同士が一緒に生きていく以上、傷つきは避けられないものでもあります。
でも明るいだけの、効率がいい人生より寂しさや苦しさ、迷いを経験しつつ生きていくほうが豊かなのではないでしょうか。傷を抱えつつ、周囲の人たちと生きていくということが、その人の深みにつながっていくのだと思います」
同じ人に対して、逃げたい気持ちとつながっていたい気持ちの両方があってもいい。傷を傷と認めて、抱えたまま過ごしてもいい。そんな宮地さんのお話を聞くうち、自分の中の割り切れない気持ちをそのままにしておいてもいいのかもしれないと、肩の力が少し抜けた気がしました。
傷は痛く、なかなか癒えない時もあるけれど、その痛みや弱さで人とつながれるという希望は失わずにいたいと思います。
【写真】井手勇貴
もくじ


宮地尚子
一橋大学大学院社会学研究科特任教授。1986年京都府立医科大学卒業。1993年同大学院修了。専門は文化精神医学・医療人類学・トラウマとジェンダー。精神科の医師として臨床を行いつつ、研究を続けている。著書に『トラウマ』(岩波新書)、『ははがうまれる』(福音館書店)、『環状島= トラウマの地政学』(みすず書房)、『傷を愛せるか』(ちくま文庫)、『傷つきのこころ学』(NHK出版)など。
感想を送る