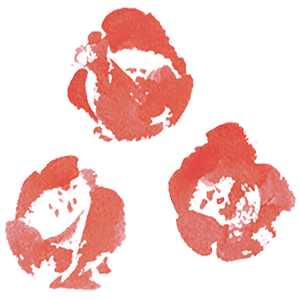自分が何者なのか、どんな仕事がしたいのか、何が心地いいのか……。正解がわからずに、とにかくがむしゃらに走り続ける20〜30代。
そして、ふと足を止めるのが40歳という年齢なのかもしれません。私って、今まで何をしてきたのだろう? 何のために働いているのだろう? そうやって、やっと自分を俯瞰で眺められるようになった時、次の一歩をどうやって出したらいいか、突然迷子になってしまったような気分を味わいます。
連載『40歳の、前とあと』では、今キラキラと輝いて活躍している女性に、その境目となる「40歳」という年齢をどう迎えたか、40歳以前と、40歳以降に、何がどう変わったのか、お話を伺ってみることにしました。
第8回でお話を伺ったのは、料理家のサルボ恭子さんです。
「どっちに進めばいいかわからない」。将来が見えていなかった20代

「え?サルボさん? 日本の方? どうしてサルボさん?」
初めてそのお名前を聞いた時、たくさんのクエスチョンマークが、頭の中に浮かびました。共通の知人の紹介で、お会いしたのは7年ほど前。『暮らしのおへそvol.13』(主婦と生活社)で取材をさせていただきました。
フランス人のご主人サルボ・セルジュさんと結婚したのは、33歳のとき。実は、セルジュさんは再婚で、サルボさんは、結婚と同時に当時小学校2年生のミカエルくんと、幼稚園児のレイラちゃんのお母さんになったと聞いて驚きました。
そんなサルボさんに「40歳の頃は何をしていましたか?」と聞いてみると……。「子育てと料理の仕事を、両方マックスの力でやっていましたね」と笑いながら教えてくださいました。
フランスの料理専門学校「ル・コルドンブルー」で学んだのち、一流ホテル「ホテル・ド・クリヨン」で働いた経験を持ち、正統派フレンチの技を確かに身につけた方なのに、時には『夜9時からの飲めるちょいメシ』(家の光協会)を紹介したり、土鍋料理の本を出されたりと、その料理の幅広いこと!

でも、料理を仕事にしようと決心するまで、随分と時間がかかったのだといいます。そこで、まずは今の仕事を見つけるまでのお話を伺ってみました。
中学時代から英語が好きで、高校生になるとカナダに留学。大学卒業後は、好きな英語が活かせるようにと、大手メーカーの海外部に就職しました。
サルボさん:
「仕事は、上司にも恵まれてすごく楽しかったんです。でも、古い体質の会社だったので、本社の女性は25〜26歳で寿退社する、というのが当たり前のルートでした。自分がその年齢に差し掛かった頃『なんとなく流されて就職したけれど、ここから飛び出したら一体何があるんだろう?』と、初めて立ち止まって考えたんです」
立ち止まった時、自分の内側を見つめてみた

でも、「だったら何をする?」といくら考えても答えは見えてきません。考えに考えて、やっと見つけたのが「食べることが好き」ということでした。
自分にとってやりがいのある仕事って何なのか? それを見つけることは、なかなか難しいものです。
何も見つからなかった時、「世の中にはどんな仕事があるか」だったり、「自分のスキルだったら、どんな場所で働けるか?」と「外」を見るのではなく、「私は何が好きだったっけ?」と手の中にあるものを見つめたのが、サルボさんのすごいところ。
実は、サルボさんは栃木県にある老舗旅館の娘さん。
サルボさん:
「日光の自宅は、旅館とは別の場所にあって、私たちは板前さんが作った料理を食べる、ということはなく、家族揃って食卓を囲み、母が作ってくれたものを食べて育ちました。みんなが揃っての食事の時間をとても大切にする両親のもとで育ち、祖母も母もすごく料理上手だったんです。
幼い頃から、外食にもよく連れて行ってもらいました。ホテルのフレンチレストランに行ったり、和食だったらお寿司や天ぷら、うなぎなど……。田舎で周りにレストランなどもなかったので、きちんとしたところに食べに行くか、自宅で母の料理を食べるか、どちらかでした。
外食に行くと緊張するけれど、ちょっと背伸びして、一人前に扱ってもらえるのが嬉しかったですね。両親や祖父母は、私たちに料理を自分でオーダーさせました。それは『責任を持って、感謝して食べなさい』という意味。だからお腹がいっぱいになって食べられなかったりすると、すごく怒られましたね」
「料理の中に何かがあるかも」。無理して結論を出さなくても進んでいける?
 ▲母方のおじいさま、おばあさま。ご実家の前で。おばあさまは料理が得意で大きな影響を受けたそう。
▲母方のおじいさま、おばあさま。ご実家の前で。おばあさまは料理が得意で大きな影響を受けたそう。
そんな環境の中で育ち、自然に料理に興味を持つようになったそうです。
大学生になると、叔母さまが主宰していた料理教室に通うようになりました。25歳でふと足を止めた時、頭に浮かんだのが「料理」だったのは、自然な流れだったのかもしれません。
そしてサルボさんは会社を辞め、叔母さまに相談し、料理教室のアシスタントとして働き始めます。
サルボさん:
「その先にどんな仕事があるかなんて、全く見えていませんでした。どうなるかわからないけれど、ただ『料理』というキーワードを頼りに、とにかくやらせてもらう、という感じでしたね」
「教室を卒業して、料理家になろう!」と計画されていたのかと思いきや、当時は、全くのノープラン。ただただ「料理」の中に何かがあるかも……。そんな思いだけで突き進んだといいますから、サルボさんにとって、「料理」がどれほど大切だったかがわかります。
ところが……。叔母さまはとにかく厳しい方だったそうです。

サルボさん:
「生徒さんがいる前でも、容赦なく怒られました。叔母が次のことをやる前に、必要なものを察してスッと差し出さなくてはいけない……。そのタイミングが合わないときっと睨まれたり(苦笑)。
料理教室って、生徒さんにキッチンが全部見えてしまうんですよね。だから美しく下ごしらえをしなくてはいけないんです。
これは叔母だけでなく、祖母も母も言っていたことですが、料理をみんなで食べる時には、洗い物が終わっていないといけない。そして作り始めた時よりもきれいになっていなければいけない。毎回、叔母のところへ行くたびに本当に緊張していました」
どんな仕事も続けていれば、スキルアップを実感できる

3年間ほどアシスタントを続けると、だんだん仕事が楽しくなってきました。
サルボさん:
「言われる前に、必要なものをスッと渡せると快感でしたね。料理人って体育会系なんですよ!(笑)でも、毎日同じことをやっていても、継続すればするほど時間が短縮できるようになるんです」
やっと慣れてきたとき、今度は今まで手元しか見られなかった視線を、ふと「未来」へとあげてみたのだと言います。
サルボさん:
「フランス料理から、今度は『フランス』を見るようになっていました。フランス料理をやっているのに、私はフランスに行ったこともない……。本場を知らないなと思ったら、行きたくなっちゃったんです」
やっと、自分の夢を見ることができるようになったサルボさん。そのワクワク感がどれほどだったことでしょう!
次回は、フランスに旅立ったサルボさんの日々についてご紹介します。
(つづく)
【写真】木村文平
もくじ


サルボ恭子
1971年生まれ。料理家の叔母に師事したのち渡仏。ル・コルドンブルーなどの料理学校を経て、「ホテル・ド・クリヨン」調理場へ。当時2つ星のメインダイニングのキッチンとパティスリーに勤務。帰国後、料理研究家のアシスタントを経て独立。フランス人の夫、2人の子供と暮らす。(長男は留学中)現在は料理教室を主宰。素材と向き合いその持ち味を生かす料理を得意とする。facebook:@kyokosalbotofficeial インスタグラム:@kyokosalbot

ライター 一田憲子
編集者、ライター フリーライターとして女性誌や単行本の執筆などで活躍。「暮らしのおへそ」「大人になったら着たい服」(共に主婦と生活社)では企画から編集、執筆までを手がける。全国を飛び回り、著名人から一般人まで、多くの取材を行っている。ウェブサイト「外の音、内の香」http://ichidanoriko.com/
感想を送る