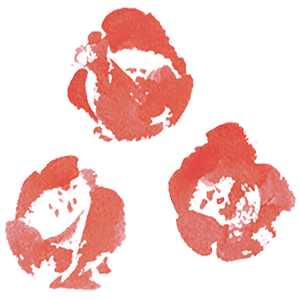不定期連載「フィットするしごと」、本日は旅するパティシエ鈴木文さんです。クラシコムジャーナルで2020年4月に公開された川内イオさんの記事を編集してお届けします。
***
ピンク、グリーン、イエロー、オレンジ……カラフルでコロンとした見た目がかわいい焼き菓子、マカロン。ここ数年、日本でも人気の洋菓子のひとつだけど、発祥の歴史は意外と知られていない。
日本では、フランス発のパティスリーが取り扱っていることが多いから、フランスからきたお菓子だと思っている人も少なくないだろう。でも実は、イタリア生まれ。
16世紀、イタリアのメディチ家に生まれ、政略結婚でフランス国王アンリ2世に嫁いだカトリーヌ・ド・メディシスは、イタリアの菓子職人や料理人を伴ってフランスにやってきた。その時に持ち込まれたのが、アーモンドを使った素朴な焼き菓子「アマレッティ」。フランスのパティシエがこれに手を加えて、現在のマカロンに姿を変えたそうだ。
2013年から3年間、会員制の高級レストランでシェフパティシエを務めていた鈴木文さんは、デザートのメニューを考えてきたときに調べ物をしていて、たまたまマカロンの歴史を知った。その瞬間、「見た目や味のことばかり考えて、こういうことを知らないってどうなんだろう?」と、自分の仕事ぶりを振り返って反省した。
これをきっかけに、なじみのお菓子の由来や背景を調べ始めると、自分が知らないお菓子が山のようにあることに気づいた。
「世界のお菓子を学びたい」
好奇心がふわふわのホイップクリームのように膨れ上がった鈴木さんは仕事を辞め、2016年1月、夫と一緒に成田空港に向かった。「世界の郷土菓子をつくる旅」が、始まった。
数えきれないほど焼いたチーズケーキ
 ▲ヌガーの原型となった中東生まれの「ハルヴァ」をアレンジしたお菓子。
▲ヌガーの原型となった中東生まれの「ハルヴァ」をアレンジしたお菓子。
鈴木さんがお菓子を作り始めたのは、立教大学の英米文学科の1年生の時。特にお菓子が好きだったわけでもなく、実験するような気分だった。
鈴木さん
「もともと理系で、特に理科の実験が好きでした。お菓子作りも、素材を混ぜたり、焼いたら膨らんだりして、そういう科学的な変化が楽しかったんですよね」
学生時代、一番はまったのは、ベイクドチーズケーキ作り。作ったケーキはひとりで食べきれないので家族や友人に配った。みんなが「おいしい!」と言ってくれたけど、あまり自分に自信を持てない性格だったから、「作った本人にまずいっていう人はいないよな。本当においしいと思ってるのかな」と疑念が募り、「もっとおいしいものを」と研究に励んだ。数えきれないほどのベイクドチーズケーキを焼き、周囲に振る舞い続けた。
ただ、お菓子作りはあくまで趣味だったので、仕事は一般企業を志望。就職活動をするなかで、顧客やコラボレーションする作家との丁寧なコミュニケーションを重視するアメリカの高級老舗百貨店「バーニーズ・ニューヨーク」の姿勢に惹かれ、2007年、日本支社に就職した。
若手社員の仕事は、店舗での販売。鈴木さんはにこやかで人当たりがいいので、「けっこう売りそうですね?」と尋ねたら、「私ですか? ぜんぜんですよ」と笑った。
鈴木さん
「接客は大好きだったんですけど、自分でもびっくりするくらい売れなくて。お客さんはたくさんいたのに、みんな私と話だけして帰っちゃうんですよ。それがずっと続いて、なんで売れないんだろうねって上司と話をして気づいたのは、お客さんに書く手紙にしても、お店での会話にしても、セールスと真逆のことをしていたこと。私自身が消費するより物を大切にして長く使うほうがいいと思っていて、それが言葉や態度に出ていたんです」
アポなしアタックナンバー1

……という正直すぎる接客で、営業成績はサッパリ。一方、プライベートでは趣味のお菓子作りが続いていて、職場の人たちにも「おいしい!」と言われていた。それでも「気を使って褒めてるだけ」という疑いは晴れない。身近な人にどれだけ食べてもらっても正直な感想が得られないともどかしく思っていた鈴木さんは、ある日、ふと思った。
「みんながおいしいって言う私のお菓子は、いくらで売れるんだろう?」
お金を払って買う人がいたなら、そのお菓子には価値があるということになる。自分のお菓子に値が付くのか知りたい! という思いが頭から離れなくなった鈴木さんは、大胆な行動をとった。作ったケーキを持ってカフェを訪ね、「私のケーキを売ってくれませんか?」とアポなし営業を始めたのだ。
当然のごとく、は? あなた誰? という冷たい反応が返ってきたが、それでもめげず、休日がくるたびにカフェを巡った。その数は、10軒を超えた。すると、そのうちの2軒、「うちに置いてあげるよ」というカフェが出てきた。1軒は友人の紹介先で、もう1軒は縁もゆかりもないカフェだった。ついた価格は、一切れ500円。ひとつ売れると、そのうちの数パーセントが鈴木さんに支払われる。
職場は10時出社だったので、退社後にケーキを焼き、朝、カフェに届けてから仕事に行くというサイクルになった。
鈴木さん
「私のケーキにお金を払ってくれるお店があって、ケーキが売れるとお店の売り上げにもなるということがすごく嬉しかったですね。もっとおいしいケーキを作りたいと思って、仕事以外の時間をほとんど使って、プロ向けの本を読み漁って、研究していました」
パティシエとして塩味の船出

この時に読んだ書籍には、見たことがない単語や作り方がいくつも載っていて、もっと詳しく知りたいという気持ちが沸き上がった。同時に、気づいた。隙間時間にひとりで作業していても、上達するには限界がある。
2010年、バーニーズ・ニューヨークを辞めて、パティシエを目指すことに決めた鈴木さんは、転職活動を始めた。そもそもパティシエは求人自体が少なく、どこも即戦力を求めているので、未経験者を現場に受け入れる店はほぼない。
それでも鈴木さんは、遠回りはしたくないという思いから、「入社初日から厨房に立たせてくれるお店」にこだわった。当然のように軒並み断られるなか、まさに当たって砕けろで問い合わせを続けると、1軒だけ、当時、広尾にあったラ・プレシューズというパティスリーが「そんなに頑張るって言うならいいよ」と採用してくれた。
パティシエ・鈴木文としての歩みはまったく甘いものでなく、むしろ塩味だった。パティシエを目指す場合、製菓の専門学校を卒業して、ひと通りの知識と技術を身に着けてから働き始めるのが一般的なところ、鈴木さんはゼラチンの溶かし方すらわからない。年下の同僚たちに教えてもらおうとしても、役に立たない素人に時間を割いてくれる人は少なく、技術は「見て盗む」しかなかった。
仕事は朝5時から始まり、終わるのは夜。帰宅してから、その日に学んだことの復習をしようにも、憶えることが多すぎて、まとまらない。どうしてもわからないことは、唯一の休日だった日曜日、シェフに電話をして教えを請い、それから自宅で練習した。
なにもできない自分がふがいなく、悔しくて、家に帰ってからよくひとりで泣いた。朝になっても気が晴れず、乗換駅の日比谷で一度下車し、早朝の日比谷公園で気持ちを落ち着けてから出勤したのも一度や二度ではなかった。
パティスリーとホテルの違い

それでも挫けず仕事を続けているうちに、だんだんと要領をつかめるようになってきた。気持ちと時間に余裕ができると、少しでも刺激やヒントを得ようと、ホテルのレストランを巡ってデザートを食べるようになった。
パティスリーで作るケーキは、一枚の小さなプレートの上で完結するパティシエの作品である。一方、ホテルのレストランのデザートは、食事との相性を考えたうえで、締めの一品としてシェフの世界観を伝える役割も担う。
レストランのデザートに表現としての広がりを感じた鈴木さんの胸中に、また「学びたい」という欲が湧いてきた。このスイッチが入ったら、もう後戻りはできない。
鈴木さん
「パティスリーで2年半働いて、基礎は学んだ。今度はホテルのレストランで働きたい」
新たな働き口を探し始めてすぐに、簡単にはいかなそうだと気づいた。「レストランで勤務経験のない場合、ほぼ未経験とみなす」というところが大半だったのだ。そんなことを気にするタイプではない鈴木さんは、気になるホテルに次々と履歴書を送った。
そのなかで唯一、「ケーキ屋さんでやってきたなら頑張れるかもしれない」とキャリアを認めてくれたのが、5つ星ホテル、ザ・ペニンシュラ東京のフレンチレストランだった。そこで、フランス人の料理長と日本人のシェフパティシエのもとで、働くことになった。
活気に満ちた厨房

迎えた初日、同じパティシエでありながら、パティスリーとは似て非なる仕事を目の当たりにして、「またゼロからスタートだな」と気合を入れなおした。
鈴木さん
「レストランでは3つ以上のものを同時に口に入れたときのバランス、歯応え、香りを総合的に考えなきゃいけないんです。そのうえで、お客さんの目線や食べやすさなども意識する必要があるので、視野を広く持たないといけません。お皿の上で表現するっていうことが、ひとつのお菓子に向き合うパティスリーといかに違うのか、実感しましたね」
職場の雰囲気も、まるで違った。広尾のパティスリーの静かでストイックな雰囲気とは似ても似つかないほど、活気に満ちていた。
フランス人の料理長は、突然姿を消して皇居にランニングにいくような自由人で、気分がいいときは歌いながら料理をする。その料理長からなにか指示が出ると「ウィ ムッシュ!」と全員が返事をする。メインの料理が出たよ! と言われたら、そこから逆算して一皿ずつデザートを盛り付ける。そこには、チームとしての連帯感があった。
形が崩れたり、提供するのが遅れたりするのはもってのほかという緊張感のなかで、デザートを美しく仕上げていくことにも、やりがいを感じた。料理から学ぶことも多かったと振り返る。
鈴木さん
「チャレンジがよしとされた職場で、おいしいかわからないけど試してみようということで、いろいろ新しいデザートを作りました。料理人しか使わない食材ってたくさんあって、ハーブの使い方も教わりましたし、お醤油とかお味噌みたいな調味料からお菓子を作れることも学びました。楽しかったな」
シェフパティシエを目指して

ここで働いているうちに、今度は「自分でデザートのメニューを考えたい」と思うようになった。それができるのは、シェフパティシエのみ。ザ・ペニンシュラ東京でそのチャンスが巡ってくるのを待つよりも、自分で動き、チャンスを掴めばいい。
とはいえ、レストランのシェフパティシエの求人は珍しい。誰かがそのポストに就いていないとレストランを運営できないし、レストランではシェフパティシエ以上のポジションはないから、そうそう空きは出ないのだ。
それでも根気よく探していると、ある高級フレンチレストラン(会員制につき店名非公表)がシェフパティシエを募集しているのを発見。応募をしてみたら、見事に合格した。
シェフパティシエの仕事は、1年に数回変わる食事のメニューに合わせてデザートを考えることと、それをレシピにしてスタッフたちが作れるようにすること。もちろん、自分も厨房に立って、最前線で手を動かす。そこに、スタッフの労務管理も加わる。
厨房でデザートをひたすら作っていたザ・ペニンシュラ東京時代よりも仕事は複雑でよりハードになったが、自分のアイデアがメニューに載り、お客さんが楽しんでくれることに、喜びとやりがいを感じていた。
それでも、「もっと知りたい」「もっと学びたい」という思いを抑えられないのが、鈴木さんらしい。冒頭にも記したように、マカロンがイタリア発祥だと知ったのを機に、好奇心に火が付いた彼女は、休日を利用しては海外へ出かけ、現地のお菓子を学び、そこで作ることをライフワークとするようになった。そうして訪ねた国は、20カ国以上にのぼる。
そのうちに、休日を利用した数日間では物足りないと感じるようになった。もっと時間をかけて海外を巡りながら、お菓子の文化を学びたいという思いが募る。そしてついには、ほとんどのパティシエが目指すであろう、高級フレンチのシェフパティシエという地位に未練もなく、夫と一緒に「世界の郷土菓子をつくる旅」に出た。この時、ちょうど30歳だった。
(つづく)
【写真】鍵岡龍門
もくじ
前編
わたしのお菓子はいくらで売れるの?溢れる好奇心で漕ぎ出した「旅するパティシエ」の船出
後編
人生はすべてつながっていく。世界37ヵ国で郷土菓子を学び見つけた、新たな冒険


鈴木文
パティシエ
立教大学卒業後、株式会社バーニーズジャパン入社。アパレル業界を経て、パティシエに転身。ザ・ぺニンシュラホテルのフレンチレストランやパティスリーなどで修行を積んだ後、会員制レストランでシェフパティシエに就任。退職後は約1年にわたり、世界各地でお菓子を作る旅へ。これまで50カ国以上を訪れ、500種類以上の世界のお菓子を学んだ経験をもとに、お菓子ブランド「世界のおやつ」を主宰。 企業や自治体、大使館などの商品ブランドのプロモーション・レシピ開発・WS講師・お菓子ケータリングなどの事業を展開しながら、創作菓子とともに、旅とお菓子のストーリーを届けている。

ライター 川内イオ
1979年生まれ。大学卒業後の2002年、新卒で広告代理店に就職するも9ヶ月で退職し、03年よりフリーライターとして活動開始。06年にバルセロナに移住し、主にスペインサッカーを取材。10年に帰国後、デジタルサッカー誌、ビジネス誌の編集部を経て現在フリーランスエディター&ライター&イベントコーディネーター。ジャンルを問わず「規格外の稀な人」を追う稀人ハンターとして活動している。稀人を取材することで仕事や生き方の多様性を世に伝えることをテーマとする。
感想を送る