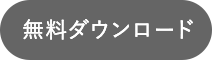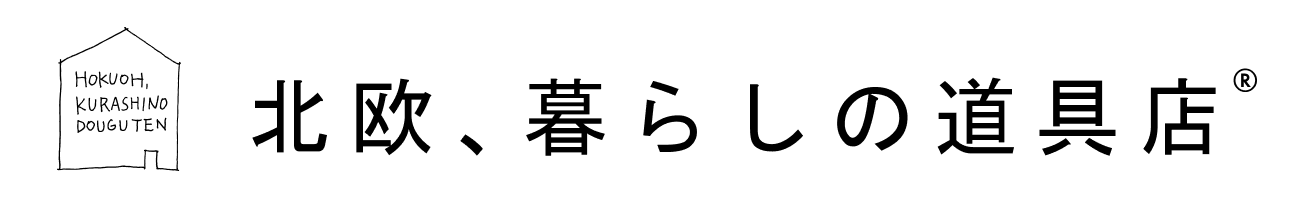ふだんはせわしなく、仕事と向き合うクラシコムのスタッフたち。ゆっくり、じっくりと、お互いのこれまでを振り返って話す時間は……実はそれほど多くありません。
でも、あらためて話してみると、人となりがもっとわかったり、新鮮な発見が得られたりするもの。そこで、スタッフ同士でインタビュー(というより、おしゃべり?)してみる機会を持ってみることにしました。
今回は、クラシコムにまつわるデザインの全てを統括しているコーポレートクリエイティブ室の佐藤と、ドキュメンタリー映像作品の制作などに携わるコンテンツ開発グループの田中が登場。
二人には、自身の仕事に加えて「マネージャー」としてメンバーと向き合う共通点もあります。もともと独立を考えていた佐藤は、クラシコム代表の青木からの誘いで入社。一方で、広告制作の現場でプレイヤーとして邁進していた田中は、マネジメントも担う立場に。
一人で働くこと、チームで働くこと。それぞれの経験から見えてくるものとは……。後編は主に佐藤が聞き役となって、田中に色々と質問してみました。
前編を読む
ドキドキの新人を、温かく育ててくれた場所でした

佐藤:映像制作はいつから始めたんですか?
田中:もともと広告や映像はすごく好きだったんです。たとえば、印象に強く残っているのは、リリー・フランキーさんと深津絵里さんが出演されていた住宅メーカーのCM。夫婦それぞれのモノローグで展開されていき、最後に二人が家に着いて、言葉にしていないのに通じ合っている。そういう温かみのある映像にすごく惹かれていました。
でも、学生時代に自分で作るような経験は全くなくて。新卒で広告系の映像制作会社に入社して、雑務から始めて少しずつ編集ソフトも使えるようになり、テレビCMやウェブCMといった映像制作の仕事に携わりました。その会社で5年くらい働いて、2018年にクラシコムへ入りました。

佐藤:未経験からのスタートだと、苦労も多かったのでは?
田中:イメージ通りに厳しい部分もありつつ(笑)、ありがたいことに、一人ひとりのキャラクターが強くて、愛に溢れた「家族感」のある会社でした。「社会とは怖いものだ、どうにか役に立たなきゃ」とプレッシャーを抱いていた私を、温かく育ててくれた場所でした。
「制作進行」という役割で、制作の段取りが主な仕事でした。みなさんの意見を詰めて、うまく進むように全部取りまとめたり。
佐藤:あぁ、僕はとても苦手そうだ(笑)。それができるの、すごいですよ。
田中:社会人になったばかりで、全然知らない大人たちに囲まれて、ドキドキでした。でも、若い時の方が何もわかってないので、良い意味で無責任に頼れたんでしょうね。
読みものから、なんだか「いい匂い」がして……

佐藤:よい会社に巡り会えたけれど、転職を考える理由は何でしたか?
田中:新卒から3年ほど経って、基本は最低限できると思えるところまでは来たんです。でも、「これをずっと続けていくのかな」という悩みが出てきて。
佐藤:やれちゃうけど、やり続けていいのかな、みたいな。
田中:そうなんです。「このままだと仕事をやりすぎてしまう」という感じもしたんです。
ただ、一番のきっかけは、プライベートで触れ合う家族や友人との時間が取れなくなったことです。体力も尽きて、自分自身を大切にできていないことにも気づいて。もっと、大切にしたい人と向き合える自分でいられる仕事に変えよう、と転職を決めました。

佐藤:クラシコムは前から知っていたんですか?
田中:たぶん悩み始めた頃に、たまたま「北欧、暮らしの道具店」の読みものに触れる機会があったんですね。発信されている価値観が好きだな、と感じました。
私は抽象的に物事を考えるのが好きなので、読みものから伝わることが自分の幸せに繋がりそう、という感覚を持ったんです。「こういう生き方や働き方もある、そういうふうに選んでも良いのかな」と。当時は一つの働き方しか知らなかったので、世界が開けた気がしました。「ここから、いい匂いがするなぁ」なんて思っていたら、採用募集を見かけたんです。
うまくなくてもいいから、自分で撮ってみたら?

佐藤:2018年入社だと、映像作品なら『青葉家のテーブル』が出た年ですよね。1年目はどんな仕事をしていましたか?
田中:YouTubeの動画企画で「モーニングルーティン『わたしの朝習慣』」や「暮らしの本音『うんともすんとも日和』」を立ち上げたりしていました。今の自分を作っているのは、この入社1年目の経験が半分くらいを占めているんじゃないかなって、よく思います。
それこそ入社して1ヶ月くらいで「『青葉家のテーブル』の2話目を作るよ!」と言われて、とりあえず現場に行きました。クラシコムとしては初のドラマ映像制作で、周りは言ってしまえば「映像のプロではない人」ばかり。私はたった5年くらいだけれど、一応は経験がある。外部の方たちも交えて、そんなチームで一緒に作っていくことになったんです。
すると現場では外部パートナーに対して「映像制作の常識通りではなく、全く違うやり方で工夫できないか」という相談や、「ドラマのセオリーに反していたとしても、守りたい在り方がある」と感じられるフィードバックやコミュニケーションのやりとりを目の当たりにして。

佐藤:自分の活かせそうな経験が通じない、というのは難しいですよね。
田中:当時は葛藤もしました。知っている方法でやれるなら自分としては楽ですし、不自由さを覚えた瞬間もあります。でも、今思えば……フォーマットやセオリー通りに作ると、それっぽいものはできるけれど、クラシコムが大事にしたいエッセンスは、ちょっと脇に置かれちゃうんだろうな、と。やらなくて良かったのかも、って思えるようになりました。
あと、前職では各分野のプロを集めて仕事をしていたことが多いのもあって、自分のスキルが足りない部分もありました。それについても「手探りで始めていいよ」という体制で迎えてくれたことは、私にとってもありがたかったです。「自分で撮ってみたら? うまくなくてもいいじゃない」みたいな。ここでも、温かく育てていただいたな、という感じです。
「昨日決めたこと」よりも、その時々のベターやベストを

佐藤:クラシコムで働いてきて「自分が変わったこと」といえば何が浮かびますか?
田中:一番大きいのは、囚われなくなったことです。
青木さんや佐藤さんって……昨日決めて帰ったことも、朝になると「やっぱりもっとこうしよう」と話すタイミングがあるなぁ、と感じていて(笑)。たぶん、フィードバックしてからも考え続けて、より良いことが掴めたんでしょうね。
そういう出来事を何度か積み重ねたら、「自分で昨日決めたことですら、疑いながらやっても大丈夫なんだ」「時々のベターやベストを選び続ける方が、決まった通りにやるよりも大事なんだ」と思うようになって。ただこれは、青木さんや佐藤さんだけでなく、クラシコムのメンバーにもよく共通しているように思うんです。
それはきっと、周りを信じているから。躊躇せず意見を伝えられるんですよね。私も、動画制作のために準備していたことが、仮に無駄になったとしても、「今の段階で必要なくなったわけだから、潔く捨ててしまおう」と。

佐藤:変わることを前提でいるし、きっと、結果にフォーカスしているのでしょうね。
田中:そうなんです。もっと言うと「結果にフォーカスした姿勢であれば大丈夫」という感じです。私の本性は「怖がり」なので、日常もあまり変化をしないように生きているんです。でも、クラシコムでは常に変化し続ける仕事をしなきゃ、って思っていますね。
以前に青木さんが、何かを試してみた時には成功か失敗か、成果が出たかだけではなくて、「わかったことがあるか」という評価で振り返るのも大切と話していて。たとえば、「試したけれど良くなかった」とわかったのも、結果の一つです。
失敗をするために試すわけではないですが、「何かがわかれば十分」みたいな考えは、以前になかったので、私にとっては新鮮な学びになりました。だから何でもやってみて、どっちに転んでも大丈夫だな、みたいな感覚に慣れてきているのかもしれません。
誰のせいにもしたくないから、私自身も理解してから作りたい

佐藤:チームではなく、「自分のやりたいもの」を作りたくなるときはありませんか?
田中:ゼロではないですけど、作り切れるほどのニーズが自分の中にはない感じです。でも、誰かから「こういうものが見てみたいんだよね」と言われたら、「作って見せてみたい」という欲求はあるんです。誰かが水を向けてくれるからこそ作れるのかな、という感じです。
でも、言われたまま作る、というのも違うんです。「トークドキュメンタリー『あさってのモノサシ』」も、50代以降の「人生後半への不安」がテーマ。最初は「自分にとってそんなに先のことなんて、分からないなぁ」と思っていて、時間をかけて佐藤さんとも話を重ねました。
私の少ない経験の中から「言われた通り」に作ってしまうと、つまらないものになるし、お客さまにも喜ばれない気がして。そうなったら誰のせいにしていいかわからない……というか、誰のせいにもしたくないんです。だから、自分自身も「これなら良さそう」と思えるところまでは理解したい。そのための時間が必要だったんだなと後から気づきました。
佐藤:そう、チームで仕事をするからこそできていくものがあるし、それを信じられる態勢にあるんでしょうね。

田中:それで思い出したのですが、大学生の頃、インターンで参加した広告代理店でアートディレクターさんに質問できる機会があったんです。クライアントワークである広告の仕事では「発注側からのフィードバック」と「自分がやりたいクリエイティブ」をどう調整していますか、と。
その方が話していたことが、すごく納得できました。「意固地にならなくても、言われて直したものでさえ、絶対に自分の色はクリエイティブに残るから、それで十分じゃないか」。佐藤さんが「NORMALLY」を立ち上げた話を聞いていても、似たような感じを受けました。作り手として、自分の色を無理に込めようとしなくてもいいんだって。
佐藤:確かに通じるところがあるかもしれない。僕はこのお店で、男性だけれど、女性向けの商品を最初からずっと見てきているじゃないですか。だから、「そのままの自分を出せる場」もなかった。でも、それであっても「僕らしいもの」は出ているという思考でやってきていますから。
田中:そうですね。あと、私は「直すこと」にも抵抗がなくて。作っている間は自分でいろんなことを考えて形にしますよね。でも、その意図が伝わっていない感じでフィードバックが返ってきたら……「それまでだったな」という諦めがあるというか。
佐藤:納得できるものって、もう圧倒的に「わかり」ますよね。
田中:そうそう!「いや、これには意図があって、こういう表現になっているんです」と説明もできますけど、相手が見た段階でそれを感じ取れていなかったなら、もう違う。もらった感想が結果の全て。そう捉えるのが正解だと、心のどこかで信じているんでしょうね。
佐藤:そうやって表現できたものを出さない限りは……。
田中:ダメだよね、って自分に言い聞かせています。

(おわり)
【写真】川村恵理
感想を送る