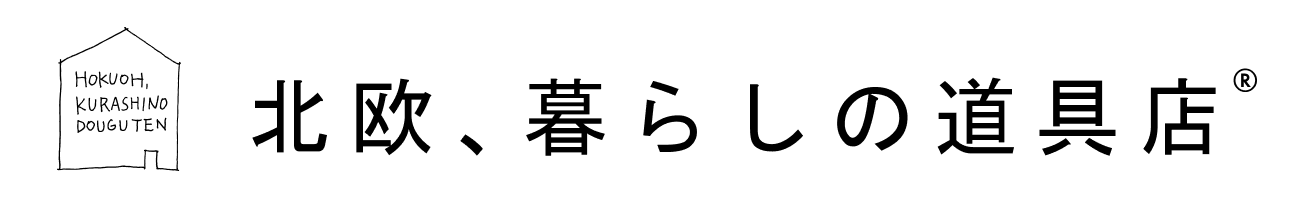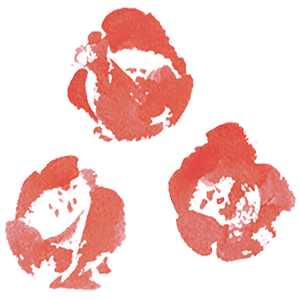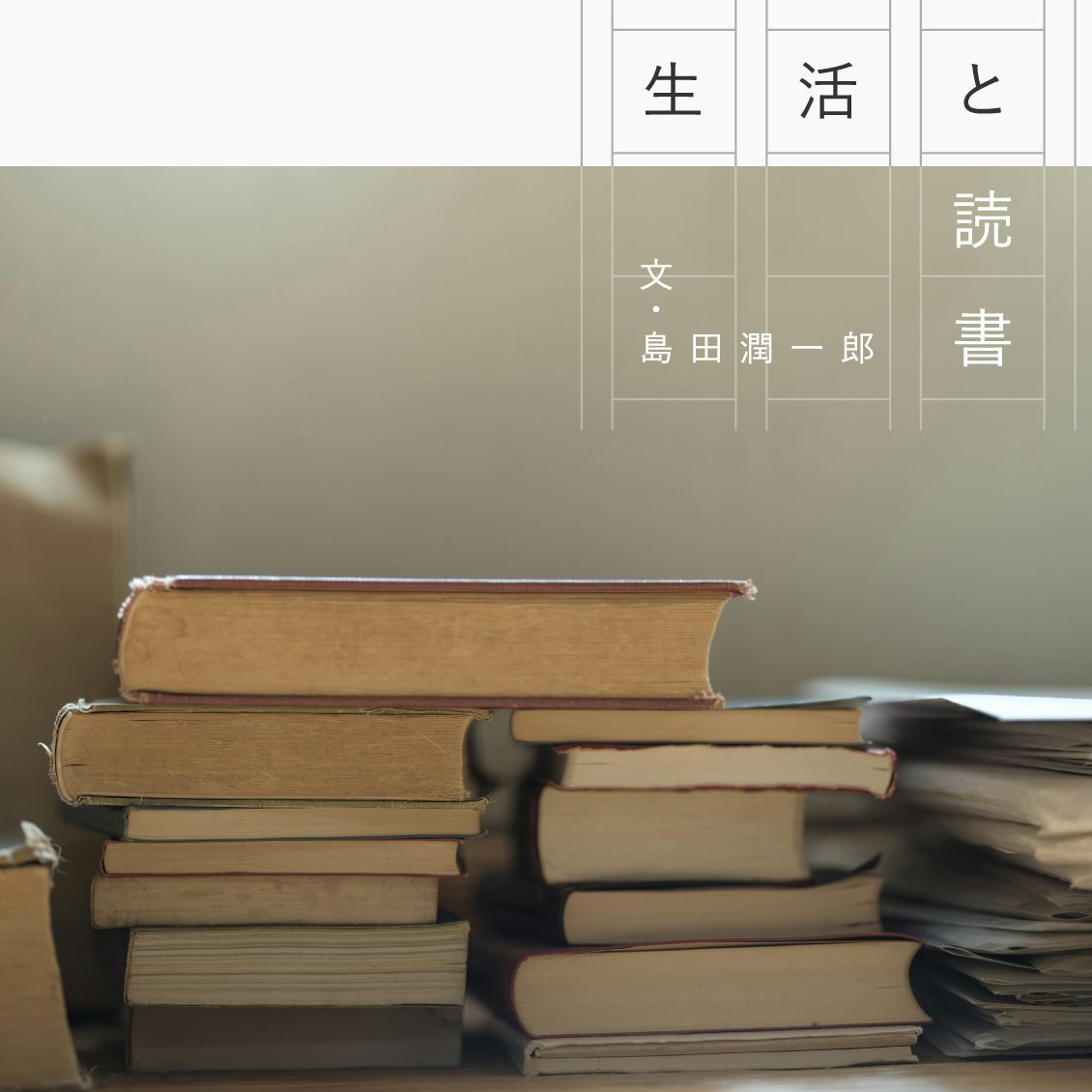夏葉社・島田潤一郎さんによる、「読書」がテーマのエッセイ。ページをめくるたび、自由や静けさ、ここではない別の世界を感じたり、もしくは物語の断片に人生を重ねたり、忘れられない記憶を呼び起こしたり。そんなたいせつな本や、言葉について綴ります。月一更新でお届け予定です
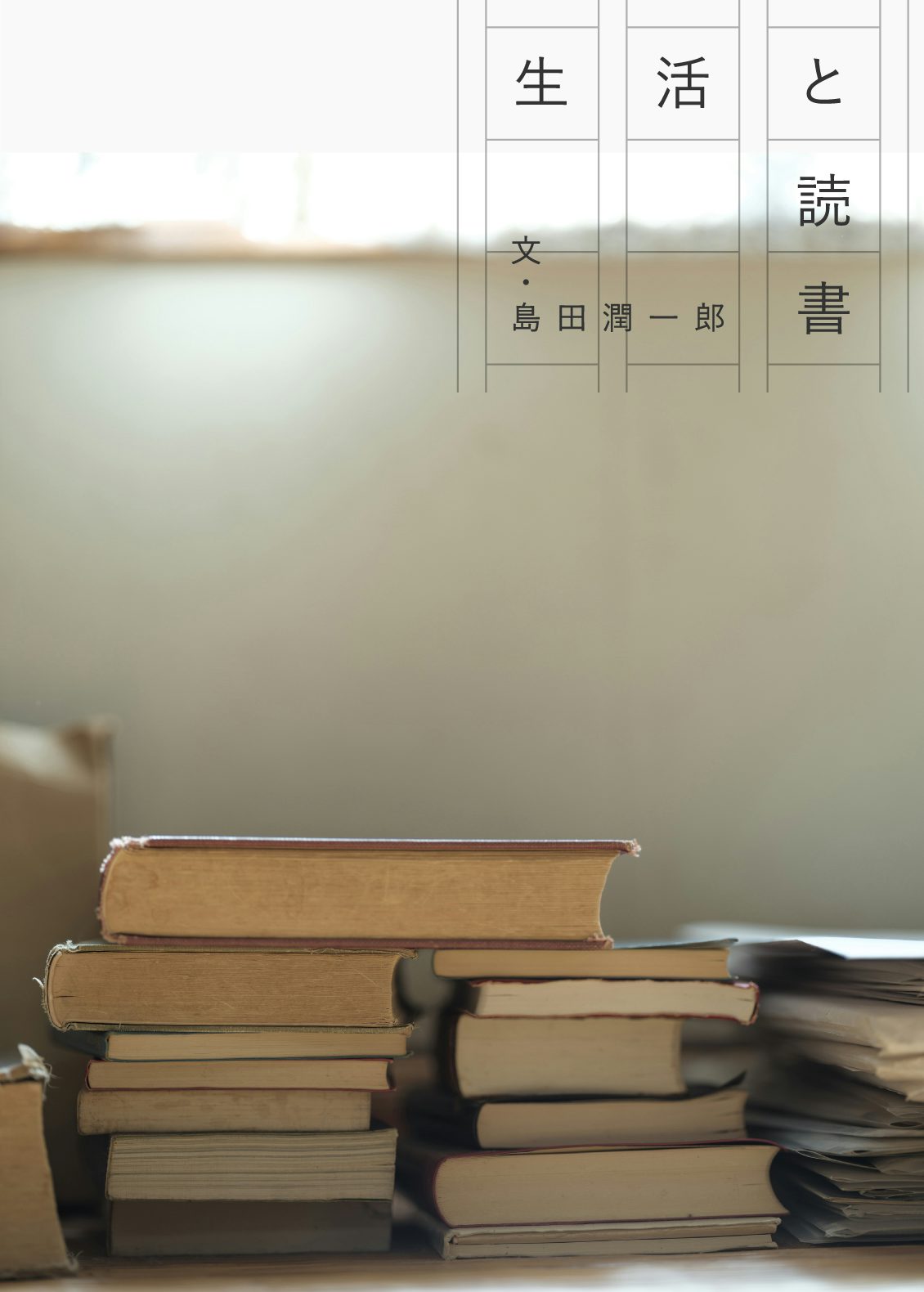
はたして、本は読んだほうがいいのでしょうか?
いまでも、ときどき、そのことについて考えます。
ぼくはなぜか、ずっと本を買い、本を読んできました。20歳ぐらいのころから、ずっと。
近所の本屋さん、古本屋さん。新宿の紀伊國屋書店本店。いまはなき、渋谷の6フロアで構成されていたブックファースト渋谷店、池袋のリブロ本店、町田のセイユーの上にあったリブロ町田店。
好きなジャンルは文学。とくに、古典といわれているような海外文学が興味の対象で、新潮文庫や岩波文庫、ちくま文庫や福武文庫(なつかしい)のラインナップに入っているような、50年前、100年前の海外文学を好んで買い、アリが餌を運び込むように、せっせせっせと、自分の部屋に運び込んでいました。
ただ、問題がひとつありました。それはぼくが読書が苦手だということです。
5ページとはいいませんが、10ページも読むと退屈してしまって、ちがうことを考えはじめます。100年以上も前のパリやサンクトペテルブルクのことよりも、部屋に落ちているほこりのことが気になりますし、友人のこと、学校のこと、あるいはアルバイトのことのほうが気になります。
たいていは文庫本を放りだし、携帯電話を見たり、この便利な通信機器がなかったころはテレビを見たり、CDを聴いたりしていました。もっと気分が落ち着く夜にでも読もう、とこころのなかで言い訳をしながら。
でも決まって、夜も読まないのです。疲れているし、眠いし、夜は昼間よりもおもしろそうなテレビ番組が多かったから。
それでも、本にこだわり、読もう、と思い続けたのはなぜなのでしょう?
賢くなりたかったから?
そういう面は否定しません。
立派な人間になりたかったから?
それも間違いなくモチベーションのひとつでした。ぼくが尊敬するひとたちはみな本を読んでいましたし、彼らのように思慮深い、落ち着いた人間になりたいとずっと願っていました。
でも、そのふたつの理由より、もっと決定的な理由があります。それは年をとり、50歳近くになってようやく気づいたことです。
うまくいえるかわかりませんが、なんとかその理由について書いてみましょう。
§
いちばん最初に言葉を覚えたころのことを覚えているひとはほとんどいないように思います。
赤ん坊のころは父や母、兄や姉がいるひとは彼らもまた熱心な先生になって、私たちに言葉をおしえてくれたのだと思います。
幼稚園にあがると、お友だち、先生からも言葉を習います。
あと、毎日見るテレビ。文字が読めるようになると、こども雑誌や、絵本からも習うでしょう。
小学校に入学すると、そこから社会人になるまでは、たくさんのひとたちから浴びるように、言葉を習い、その言葉のつかい方を習います。
重要なのは、言葉の種類ではなく、そのつかい方のほうです。
どのように言葉をつかえば大人らしくて、どんなことをいえば男性らしく、女性らしく、あるいは父親らしく、母親らしく見えるのか。
私たちは無意識にだれかの言葉を模倣し、習い、その社会的役割にふさわしい言葉遣いをしようしているように思います。
もちろん、そうした役割から徹頭徹尾自由なひともいると思いますが、真面目で、どちらかというとルールを守ることによろこびを感じるぼくみたいな人間は、組織のなかでは(自由を謳歌すべき、大学のサークルのなかでさえも)その役割にふさわしい発言をし、メールを書こうと日々努力をするのです。
そんな生活を何年も送っていると、ときどき、だれとも話したくなくなるくらいに、疲れることがあります。
親とも、友人とも、会社のひとたちともしゃべりたくない。
そういうとき、ぼくは熱心に音楽を聴き、本を読みました。
ぼくが好きな作家たちは、ふだんぼくがつかう言葉とはことなる、言葉遣いで、物語を紡ぎ、随筆を書き、詩を書きました。
冒頭に書いたように、ぼくはその世界に何時間も入り込むタイプの読者ではなかったのですが、たまに本を読むと、自由を感じました。
その束の間の自由が、ぼくにゆっくり息を吐き、息を吸うくらいの休息を与えてくれたのです。

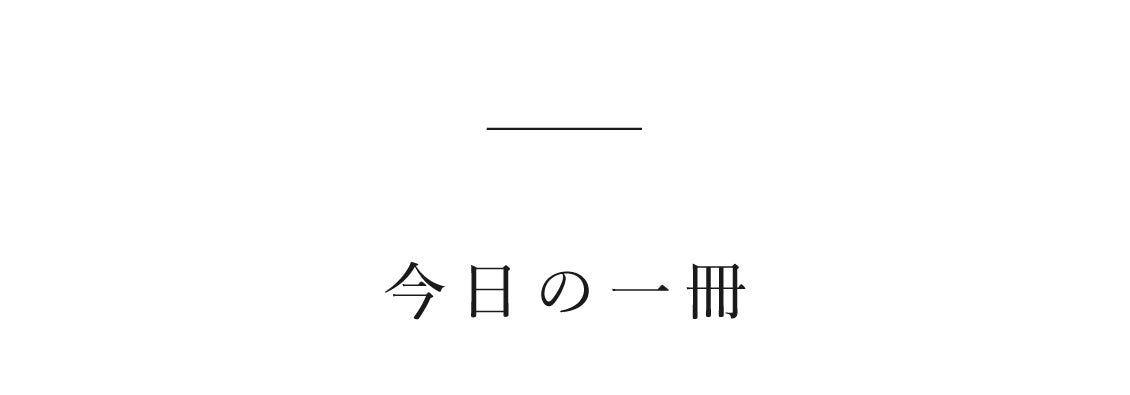
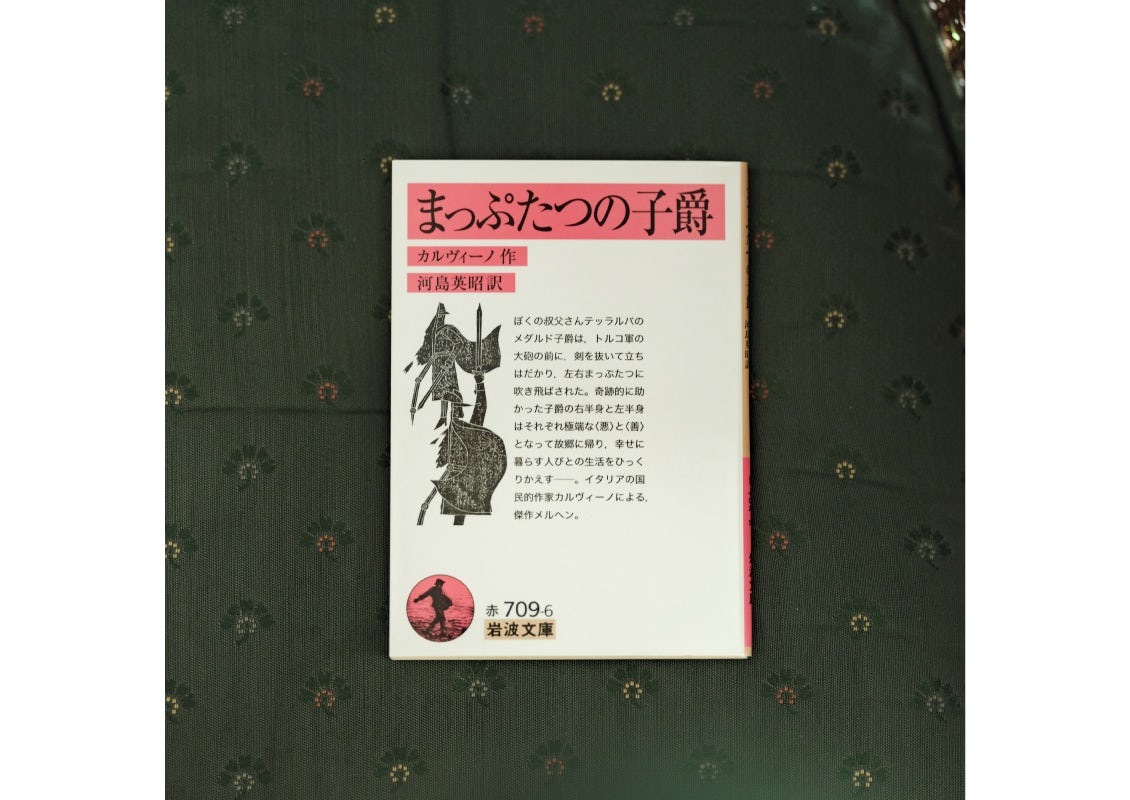
『まっぷたつの子爵』
カルヴィーノ(著) 河島 英昭 (訳) 岩波文庫
海外文学をほとんど読まないひとに、なにかおすすめはないですか? と聞かれると、サリンジャーの『ライ麦畑でつかまえて』と、カルヴィーノの『まっぷたつの子爵』の二冊がいつも頭に浮かびます。で、「サリンジャーは好き嫌いがわかれるし……」と思い至って、毎回カルヴィーノを推薦するのです。やさしい言葉で書かれたすごい本です。
文/島田潤一郎
1976年、高知県生まれ。東京育ち。日本大学商学部会計学科卒業。アルバイトや派遣社員をしながら小説家を目指していたが、2009年に出版社「夏葉社」をひとりで設立。著書に『あしたから出版社』(ちくま文庫)、『古くてあたらしい仕事』(新潮文庫)、『父と子の絆』(アルテスパブリッシング)、『電車のなかで本を読む』(青春出版社)、『長い読書』(みすず書房)など
https://natsuhasha.com
写真/鍵岡龍門
2006年よりフリーフォトグラファー活動を開始。印象に寄り添うような写真を得意とし、雑誌や広告をはじめ、多数の媒体で活躍。場所とひと、物とひとを主題として撮影をする。
感想を送る