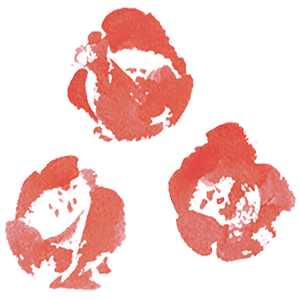連載「40歳の、前とあと」第8回は、料理家のサルボ恭子さんにお話を伺っています。
第1話では、仕事を辞めて、立ち止まった時、やっと「料理」という扉を見つけたお話を伺いました。
フランス家庭料理を教える叔母さまの元で、3年間アシスタントとして働いたのち、サルボさんは、本場のフランスへ行こうと決意します。まずはお金を貯めるために、昼間は派遣社員として働き、夜や週末のみ料理教室のアシスタントを続けることに。
サルボさん:
「忙しかったけれど、目的があったし、若かったので頑張れましたね。1年半ぐらいでお金を貯めて、足らない分は金融公庫で借りました」
さらに、並行してフランス語の勉強も始めました。この時通い始めた近所の教室で、ご主人と出会ったという訳です。(このお話はまた後ほど)
こうして、いよいよ渡仏! ただし、単にフランスに料理の勉強に行くだけで満足しなかったのがサルボさんらしさです。
サルボさん:
「私には『現場で働く』という目標があったんです。叔母に十分技術を叩き込まれていましたから、料理の学校はもういいかなと考えました。ただ、いきなり働くのは難しいし語学もできないので、料理学校から紹介をしてもらうというルートを選びました」
「フランスに行く」ことよりも大事な「何を学びたいか」

実際にクラスが始まると、サルボさんの技術は確かなもので、飛び級をして卒業。その間に現地のレストランを巡って食べ歩きをしていたのだと言います。
「私が日本で食べていたのは、母が作ってくれた洋食と、ホテルのカチッとした高級フランス料理でした。当時は今のようにビストロ風のレストランがなかったんです。そして、フランスに行ってみると、フランス料理ってもっと気軽なものなんだ!と知りました。飾り気がなくてストレートで、すごくおいしいなって思いましたね。
フランスは、元々は小国の集まりなので、それぞれの地方の味がとても際立っているんです。地方ごとの料理は昔のまま残っていて、それがきちんと守られ、受け継がれている。それ全体をフランス料理と言うんだと知りました」
 ▲フランス留学時代、友達とあちこちのレストランやビストロに食べ歩きに行っていた。
▲フランス留学時代、友達とあちこちのレストランやビストロに食べ歩きに行っていた。
卒業後、サルボさんが働きたいと思ったのが、一番格式が高いとされていた「ホテル・クリオン」のレストランでした。「ル・コルドンブルー」からのルートはなかったので、サルボさんは知り合いのつてを頼り、「ホテル・クリオン」のシェフを紹介してもらって、逆指名してもらったと言いますから、その熱意には驚くばかり!
「私、猪突猛進なんです!」と笑います。
そして、ホテルで働いた時間はとても楽しかったのだとか。
サルボさん:
「小さい頃に見せてもらったフランス料理を、最高峰の場所で内側から体験できました。トップのシェフは一人だけで、その下にセカンドが4人ぐらいいます。オーダーが入るとセカンドが読み上げて、みんなが演奏するように動き出す。本当にみんなで一つの音楽を奏でるような現場で、そこにいられることがすごく居心地が良かったですね」
遠い未来でなく、自分の足元を見れば、一歩一歩進んでいける
 ▲フランスにお母さまが遊びにきてくれた時の写真
▲フランスにお母さまが遊びにきてくれた時の写真
ただし、最初から厨房で仕事ができたわけではありません。
サルボさん:
「女性で、東洋人で、語学が完璧でもなさそう(笑)だったので、最初は違う場所に回されて、そこで下ごしらえを担当させられました。『とりあえず、このじゃがいも30個剥いておいて』みたいな。
それが悔しくて、すっごく早く剥いて『次はないですか?』って聞きにいくことでしか、自分をアピールする方法はありませんでしたね。
でもだんだん『こいつは使えそうだな』と思ってもらえて、前菜やメインを手がけるシェフの下につかせてもらえるようになりました」

こうしてビザが切れるギリギリまで働いて帰国。帰国後、どんな仕事をしようと思っていたのですか?と聞いてみました。
サルボさん:
「それが、考えても全く答えが出なかったんです。私、いつもすご〜く先でなく、足元の一歩一歩でしか進めないんですよね。あとは勘を頼りにしています。
結局、叔母のアシスタントの仕事に戻りました。ただ戻るのでは意味がないので、叔母から『何か自分でレシピを提案しなさい』と言われました。でも、私の考えたレシピは、毎回ダメ出しばかりで全く通らなかったんです。
唯一通ったのが、月代わりでお菓子を焼いて生徒さんに販売すること。一応本場のお菓子も学んできたからやってみたら?と言われて。それを1年間やりましたね。料理のように楽しみは見出せなかったけれど、力にはなったと思います」
ただ、こうして働きながらも、なんとなく悶々としていた、というサルボさん。そんなとき、帰国後フランス語を忘れないようにとレッスンを開始して、そこでセルジュさんと再会。結婚することになりました。
サルボさん:
「ここで一度家庭に入ろうかなと思って」
レストランで料理を作ることも、家族のために料理を作ることも同じだった
 ▲結婚した当時の子供達。「ママ」ではなく「恭子ちゃん」と呼ばれるように。
▲結婚した当時の子供達。「ママ」ではなく「恭子ちゃん」と呼ばれるように。
ただ、普通の結婚とちょっと違ったのは、セルジュさんは再婚で、2人のお子さんがいた、ということ。
つまり、サルボさんは、結婚と同時に二人の子供の母となることになったのでした。
迷いはなかったのですか?と聞いてみました。
サルボさん:
「それはなかったですね。なぜなら、サルボの方針で、私はパートナーにはなるけれど、子供達のママっていうのは一人しかいない。だから私はママではない、というスタンスだったから。私もフランスでそういう人たちを見ていたので、そんなに抵抗はなかったですね。
ご飯を作るとか、彼らをお風呂に入れたり寝かせたり、洗濯物を洗ったり、というのは苦でなかったんです。でも正直言うと、子供たちがママの家に行く時には、寂しさはありましたね。私って一体なんなんだろう?と思う時はありました」
そんな想いは、サルボさんが子供達に愛情を感じていたからこそ。
サルボさん:
「とにかく初めて会った時から、『なんてかわいい子供達なんだ!』って思っていたんです。すごく素直でピュア。サルボに『恭子ちゃんは、パパの奧さんになります』って紹介してもらいました」
料理一色だった暮らしから、いきなり専業主婦になって、戸惑いはなかったのでしょうか?
サルボさん:
「それが楽しかったんです。私は母や祖母のような専業主婦にも憧れがあったので。仕事ではなく、家族のために体を動かすということもやりたかったんですよね」
過剰に未来を心配したり、不安がらずに一歩前へ

普通なら、フランスまで行って料理を学んだのなら、なんとかそれを生かしたい、と考えがち。でも、サルボさんは「それはそれ、今は今」ときっぱり!
叔母さまのところで働き始めた時にも、フランスに行った時にも、そして結婚する時にも、サルボさんは迷ったり、悶々とはするけれど、いつも「今できるベストなこと」を見つけていました。
そして過剰に不安がらない。始まってみないとわからないことまで心配しない。考えてもわからないことは考えない。そんな潔さこそが、この後のサルボさんの道を開いていったよう。
次回は、いよいよ料理家への道を歩き始めたお話を伺います。
(つづく)
【写真】木村文平
もくじ


サルボ恭子
1971年生まれ。料理家の叔母に師事したのち渡仏。ル・コルドンブルーなどの料理学校を経て、「ホテル・ド・クリヨン」調理場へ。当時2つ星のメインダイニングのキッチンとパティスリーに勤務。帰国後、料理研究家のアシスタントを経て独立。フランス人の夫、2人の子供と暮らす。(長男は留学中)現在は料理教室を主宰。素材と向き合いその持ち味を生かす料理を得意とする。facebook:@kyokosalbotofficeial インスタグラム:@kyokosalbot

ライター 一田憲子
編集者、ライター フリーライターとして女性誌や単行本の執筆などで活躍。「暮らしのおへそ」「大人になったら着たい服」(共に主婦と生活社)では企画から編集、執筆までを手がける。全国を飛び回り、著名人から一般人まで、多くの取材を行っている。ウェブサイト「外の音、内の香」http://ichidanoriko.com/
感想を送る