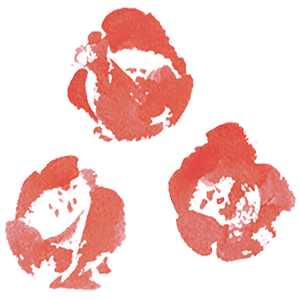第九話:かき氷機で氷をかくのを忘れる
長年気になっていた収納棚をやっと整理した。やろうやろうと思いながら、気づいたら3年経っていた。玄関前にある大型収納で、裁縫道具、古新聞、日用品のストックなどとともに、梅ジュースを漬ける瓶や味噌作りの道具など、季節の道具もしまってある。
とりわけ私がなんとかしたいと思っていたのは、キャラクターマークのはいったかき氷機だ。ハンドルをぐるぐる回すと、かき氷ができるシンプルなプラスチック製で、ひと抱えもあり、とにかく場所をとる。
最後に使ったのは数年前だろうか。扉を開けると目に飛び込む大きなそれを見るたび、もう使わないし、誰かに譲ろうかと一瞬考えるのだが、なんとなく「まあいいか」とそのままにしていた。
夏になると、子どもから「今年はかき氷やろうね」「いちごとメロンのシロップ買っといてね」といわれるのに、氷を用意したりするのがめんどうくさくて、いつしかやらずじまいになっていた。
かき氷専用の花弁型のガラスの器は、結婚祝いにもらったものだ。「いつかお子さんが生まれたら使ってくださいね」というメッセージとともに。
新婚の自分には、子どもなどぴんとこなかったが、意外にその時は早く来た。だが、使わなくなるのもまた早かった。かき氷よりおいしいものはいくらでもあるし、がりがりと氷をかくのは手間がかかる。
しかし、いざ手放そうと思うと、子どもたちの笑顔ばかりが浮かんでくる。手の甲に顎を乗せ、その手をテーブルに置いて、淡雪のように器に降り積もる氷を覗き込む嬉しそうな顔は、驚くほど記憶の中で鮮明だ。
もうかき氷はしてくれないだろうと半分わかっているのに、子どもたちは夏がくると「今年はやろうね」とお約束のようにねだり、目を輝かせる。キャラクターのかき氷機には、薄まった期待に、もう一度夢を託す魔法の力が宿っていたのかもしれない。
ぐるぐるハンドルを回して少しずつ出来上がる淡雪の山。あの頃は面倒でしかなかったが、今思うと、かき氷は、でき上がるまでの時間がワクワク楽しい。ぎりぎりこぼれないような大きな山をつくり、赤いシロップを垂らすと、淡雪が沈む。あ〜へこんじゃった〜と言いながら、好きなだけかける。なんでもないあの瞬間が、我が家の小さな夏の祭りだったのだなあと思う。
二度と帰ってこない時間。遠い夏の日。だから愛おしくて、記憶まで手放したくなくて譲れずにいるのだ。
「いっそ、あの子らに子どもができるまで持ってようか」
そう言うと、夫は「そんなのいつだよ」と笑った。案外遠くない気がするのだ。家族の歳月とは、そういうものだから。


文筆家 大平一枝
長野県生まれ。編集プロダクションを経て、1995年ライターとして独立。失われつつある、失ってはいけないもの・こと・価値観をテーマに、女性誌、書籍を中心に各紙に執筆。『天然生活』『dancyu』『Discover Japan』『東京人』等。近著に『届かなかった手紙』(角川書店)、『男と女の台所』(平凡社)、『あの人の宝物』『紙さまの話』(誠文堂新光社)などがある。朝日新聞デジタル&Wに、『東京の台所』(写真・文)連載中。プライベートでは長男(22歳)と長女(18歳)、二児の母。
▼大平さんの週末エッセイvol.1
「新米母は各駅停車で、だんだん本物の母になっていく。」
連載のご感想や、みなさんの「忘れもの」について、どうぞお便りをお寄せください。
感想を送る