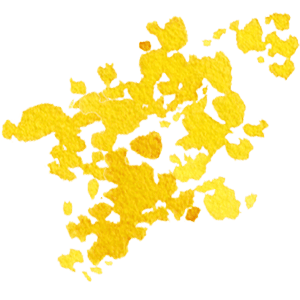第三話:残された種
Written by kim(UHNELLYS)/ Bouquet by ŒUVRE
「行ってくるね」「行ってらっしゃい」玄関で妻に見送られ、僕は新しい仕事に向かう。結婚して6年、お互いを見失いそうになりながらも、僕たちは最近やっと家族として一つになれた。
あっという間に大きくなっていく子供の成長を、ことごとく見逃していた僕は、今は仕事を変えて家族との時間を作れる人生にシフトした。
初めて自転車に乗って走り回るあの子の嬉しそうな姿は、前の仕事のままではきっと見ることができなかっただろう。毎日毎日大事な瞬間が訪れていることを、僕はまるで知らなかった。
新しい自分にやっと体が慣れ出した頃のこと。いつも歩く路地の横の庭に、老婦人が立ち尽くしていることに気づいた。手には水が出たままのホース。泣いているのか、体は小刻みに震えていた。
以前だったら立ち止まることはなかった。そもそも視界にさえ入らなかったかもしれない。でも、今の僕には通り過ぎることができなかった。
「おはようございます、あの、どうかしましたか?」と、驚かせないように静かに声をかけた。
僕に何かを言おうとするが、なかなか涙がおさまらず言葉にならない。どうせ仕事には間に合いそうにないし、僕は彼女が話せるようになるまで待つことにした。
彼女は「ふう」と深く息を吐いてから「お花が、盗まれたようなの」と細い声で言った。
花壇を見ると、乱暴に掘り返されたような跡があるだけで、花は1本も無い。
「ひどいな」僕は思わず口にした。「あの人が大事にしてた花壇なの。ここだけは自分で育てるって無理言って。どうせ盗むなら私の花壇にして欲しかった」とつぶやき、彼女はまた泣きはじめてしまった。
彼女の夫は半年前に亡くなったという。
「定年退職して時間が余ったんでしょうね、毎日私のあとにくっついて回るうちに、お花が好きになったみたい」。花壇がよく見える縁側で、彼女はポツリポツリと話し出した。
「カラフルなお花より、野に咲くようなお花が好きだと言って、自分の花壇を作ったの。育て方なんて何も知らないくせにね」。彼女は主のいない花壇を見つめながら丁寧に話してくれた。
整理整頓された室内には、小さい花束を持った子供の写真が飾ってある。お孫さんだろうか。ちょうど娘と同じくらいの子だ。
「孫にはいつも、庭のお花で作った花束をあげるの。枯れたらまたここに遊びにきてねって気持ちで」。写真を眺める僕に気づいた彼女は、涙をぬぐいながら教えてくれた。
数日後、娘のピアノ発表会からの帰り道。久しぶりのスーツに窮屈さを感じながら、ふと思い立って、妻と娘を誘い彼女の家を訪れた。
僕は花束を、妻と手を繋いだ娘にはいくつかの花の種を持たせて。入口の花壇には、まだ何も植えられていない。
玄関の前に立ち、呼び鈴を鳴らす。いきなりで驚かせてしまうかな。なんだか僕は緊張していた。でもそんな必要はなかった。ドアが開いた瞬間、彼女の笑顔が見れたから。


(つづく)
 【ダウンロード方法】
【ダウンロード方法】
1. 上の画像をクリックし、壁紙用の画像を表示します。
2. 壁紙用の画像をスマートフォンに保存します。
3. 保存した画像を、壁紙に設定してください。
※画像の保存方法や壁紙の設定方法は、お使いのスマートフォンの説明書等をご覧ください。
※壁紙のサイズは750px×1334pxになります。
もくじ