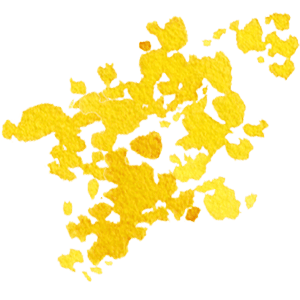夏葉社・島田潤一郎さんによる、「読書」がテーマのエッセイ。ページをめくるたび、自由や静けさ、ここではない別の世界を感じたり、もしくは物語の断片に人生を重ねたり、忘れられない記憶を呼び起こしたり。そんなたいせつな本や、言葉について綴ります。月1更新でお届けした連載は、今回が最終回です。ご愛読いただき、またご感想のお便りをお寄せいただき、ありがとうございました。

すくなくないひとは、本を読むと知識が増えるといいます。
それは嘘ではないでしょう。でも、いまはむかしと違って、スマートフォン一台で、驚くほど手軽にいろんなことを調べることができます。
本を好んで読むひとは、それでも本のほうがたくさんの知識を得ることができると考えて、本屋さんに行ったり、図書館に通ったりしているのでしょうか?
たとえば、「雑学」というジャンルがあります。ぼくらの世代でいうとなんといっても「トリビアの泉」ですが、この深夜に放送されていたテレビ番組は、30分という限られた時間のなかで、さまざまな「生きていく上で何の役にも立たない無駄な知識、しかし、つい人に教えたくなってしまうようなトリビア(雑学・知識)」を紹介し、2000年代前半に一世を風靡しました。
こうした「雑学」が人気があるのは、2026年のいまもあのころとそんなに変わらないように思います。だれもが知らない多種多様な知識をもっていれば、話の種に困るということはなさそうですし、なにより、利口そうに見えます。
では、そうした雑学を身につけるために、本を好きなひとびとは読書をしているのかというと、それはたぶん、ちがうと思います。
本を読むという行為は、いうなれば、知識と知識を結びつけるためのものです。あるいは、その知識と読み手である私とを結びつけるためのものです。
思い出すのは、もう30年以上も前の受験勉強のときのことです。18歳だったぼくは睡眠時間を削って、たくさんの英単語を覚え、日本史の出来事と人名、そして年号を覚えました。いま考えてみても、よくもあんな短期間で、あんなにも覚えることができたな、と驚くぐらいの量です。
しかし、それから数ヶ月後、大学でも必修だった英語はまだしも、入試のとき以来いっさい学ぶことのなかった日本史にかんしては、用語も、人名も、年号も、ぼくの頭からきれいさっぱり消え去ってしまいました。
記憶力が人一倍すぐれたひとは英単語も、日本史の用語も、年号もずっと覚えているのでしょうか?
もちろん、記憶しているひともいるでしょう。ぼくの友人のなかでももっとも勉強のできるMさんは、「ごくまれに教科書を一回読んだだけで全部そこに書いてあることを理解し、記憶するようなひとがいるんだ。そういうひとがスルッと東大なんかに行くんだ」といっていました。
「では、そうした能力のない人間はどうすればいいんでしょう?」
ぼくがそうたずねると、Mさんは「理屈で覚えるほかないよね」といいました。
ぼくは日本史も世界史も得意ではありませんでしたが、例外的に幕末のことだけはよく覚えています。
それはぼくが高知県で生まれ、身近な場所に史跡があったからというのもありますが、それよりも、多感だった中学生のころに、司馬遼太郎の小説を貪るように読んだからです。
物語を読むことで、知識はただの知識ではなくなります。人名としての坂本龍馬ではなく、生きた人間としての龍馬が読み手の頭のなかに長くとどまります。
本のなかで、幕末の志士たちはお互いに議論し合い、友情を交わし、ときに剣を交わします。
その世界に心奪われた読者にとって、彼らの名前や、彼らが活躍する場所の名前、時代背景は「雑学」などというものではなく、もっと親しみのある「なにか」に変わっています。
ぼくはどちらかというと勉強に苦労してきたタイプで、さらにいえば読書という行為がいまも苦手です。時間を忘れて本を読んだという経験は、社会人になってからはたったの一度しかありません(それは忘れもしません、宮部みゆきの『模倣犯』という小説です)。
勉強のため、あるいは知識を増やすためだけだったら、こんなにも本に、読書にあこがれ、こだわることはなかったように思います。
本はおもしろいから読んでいるんです。
そんなふうに言い切れたらどれだけいいかと思いますが、ぼくの場合はそうではありません。
強いていえば、魅力的な人間になりたいから、わずかな時間を見つけて本を開いているのだと思います。

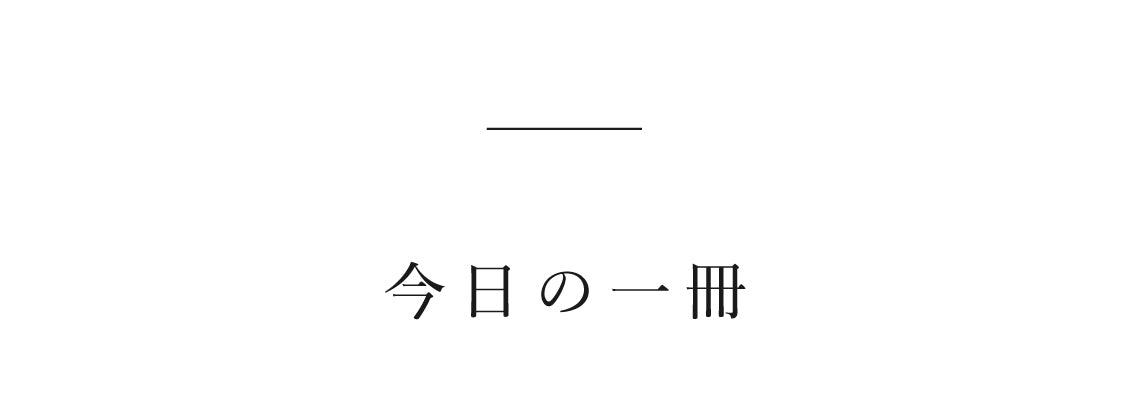

『櫛挽道守』
木内 昇 (著) 集英社文庫
物語の力というものについて考えたとき、最初に思いついたのは木内昇さんの『櫛挽道守(くしひきちもり)』です。櫛づくりに夢中になった女性の人生を描いた小説です。時代は幕末。舞台は木曽の宿場町。自分の人生とはかけ離れた、物語のなかのひとのこころがいつまでも生き続ける、その不思議さこそが、小説の魅力といっていいのかもしれません。
文/島田潤一郎
1976年、高知県生まれ。東京育ち。日本大学商学部会計学科卒業。アルバイトや派遣社員をしながら小説家を目指していたが、2009年に出版社「夏葉社」をひとりで設立。著書に『あしたから出版社』(ちくま文庫)、『古くてあたらしい仕事』(新潮文庫)、『父と子の絆』(アルテスパブリッシング)、『電車のなかで本を読む』(青春出版社)、『長い読書』(みすず書房)など
https://natsuhasha.com
写真/鍵岡龍門
2006年よりフリーフォトグラファー活動を開始。印象に寄り添うような写真を得意とし、雑誌や広告をはじめ、多数の媒体で活躍。場所とひと、物とひとを主題として撮影をする。
こちらからお読みいただけます
感想を送る