
この連載が、今回で100話目を迎えた。
100本のエッセイを書いたのだと思うと、自分でも「そんなに書いたんだ」とびっくりする。
コツコツと書き続けてきたけれど、その間ずっと順調だったわけではもちろんない。
するすると書ける日もあれば、全然書けない日もあって、そういうときはよく締め切りを延ばしてもらった。現にこのエッセイも、「100話目ということで気負ってしまって書けません」と編集の津田さんに泣きついて、締め切りを延長してもらったところだ。
そんなふうに前に進んだり立ち止まったりしながらも、このエッセイを書き続けた。
ここまで書かせていただいて、読んでいただけて、とてもありがたい。
§
文章を書く仕事をしている身ではあるけれど、書けなくなることが時々ある。
パソコンに向かっても、キーボードに指を置いても、何にも言葉が出てこない。もやもやとした煙のようなものだけが、自分の中で燻っている感じ。こういうときは参ってしまう。文字通り、仕事にならない。
そんなときはまず、ひとりで「あー」とか「うー」とか声を出してみる。ストレッチしたり、コーヒーや紅茶を飲んだり、ハンドクリームで手をマッサージしたり。体を動かすことで、なんとかならないだろうかと足掻いてみる。
それでも書けなかったら、本を読む。
エッセイを書いているならエッセイの、小説を書いているなら小説の、短歌を詠んでいるなら短歌の本を読む。著者や内容はあまり関係がない。なんでもいいから、手当たり次第に読むのだ。手に取ってばっと開いたページに書かれているものを、ひたすら読む。
なので、私のデスクの背中側には本棚があって本がずらりと並んでいる。振り向いたら、いつでも本に手が伸ばせるように。書けない日には、私のデスクの両側に、うずたかく本が積まれている。
§
ある写真家さんにその話をしたら、とても驚かれた。
「僕はスランプに陥っているとき、絶対に人の写真は見ないですね。だって余計自信を無くしそうじゃないですか」
と言う。
それなので彼は、音楽とか絵画とか、自分とは異なる表現形式の作品に触れるようにしているらしい。そのほうが、思いも寄らない刺激を受け取ることがあるのだ、と。
なるほど、そういう考え方もあるだろう。
ただ私の場合、やっぱり文章を書くには文章を読むのが一番だ、と思うのだ。読むことで、書けるようになる。そう心から実感している。
それは、真似をするとか手本にするとかいうのとはまた違う。
単純に、楽しそうに踊っている人を見ていると自分も踊りたくなるような、気持ちよく泳いでいる人を見ていると自分も泳ぎたくなるような感覚だ。
文章を書いている人を見ると、自分も書きたくなってうずうずしてくる。私はその瞬間を、いろんな本を開いて読みながら、ずっと待っている。
§
本を読み続けていると、実にいろんな書き手がいて、いろんな文体や文章があることがわかる。似ているものはひとつとしてない。そのことにいつも感動する。
例えば今手元にある、向田邦子のエッセイ集『父の詫び状』をパッと開いてみよう。
「ごはん」というタイトルのエッセイの冒頭には、こんな言葉が書かれている。
「歩行者天国というのが苦手である」
「ごはん」というタイトルなのに、「歩行者天国」。どういうことだと思いながら読んでいくと、ひとつの単語があれよあれよと彼女の記憶を呼び起こし、なめらかにシーンが切り替えられていく。そして最後にはまさしく「ごはん」のエッセイになっていて、私を涙ぐませる。
もう一冊、内田百閒の『百鬼園随筆』を適当なところで開いてみよう。そのページにある「髭」というエッセイは、こんなふうに始まる。
「私が文科大学の学生の当時、髭を生やすことが流行ったから、私も髭を生やした」
ふうん、という感じだ。ものすごく普通のことだ。でも、なぜだかするすると続きを読んでしまう。髭を生やして、それからどうした、と。そしてくすくすと何度も笑いながら、私は満足してそのエッセイを読み終えるのだ。
こんなふうに本をつまみ食いしながら読んでいると、世の中にはおもしろいエッセイがたくさんあるなぁ、と思う。
そこで私が落ち込むかというと、落ち込まない。むしろ清々しい気持ちだ。
ああ、エッセイっておもしろい。私も何か書いてみたい。純粋に、そう思う。
はっきり言って、技術や知識ではかなうはずがない。私より良い文章を書く人はごまんといるし、そこに挑もうとすれば、そのときこそ私は書けなくなるだろう。
そうではなく、私は踊るように書いていたい。泳ぐように書いていたい。ちょっとくらいフォームが乱れてもいいし、体の癖が出てもいい。一番なんて、とれなくていい。
どんなに背伸びしたところで、私には今の私に書けるものしか書けない。だから、それを精一杯できたらいい。
でも、だからこそ、「書く」行為はいつだって私にオリジナルなものを授けてくれる。
私にしか書けなかったものを最後に残してくれる。私にはそれが、一番のプレゼントのように感じる。
そのようにして、ほら、今回も1本のエッセイが書けた。
向田邦子と内田百閒のおかげだ。
本に残った、彼らの心の自由な軌跡が、今を生きる私の心を気持ち良く動かしていく。

“ 暗闇をおよぐ蛍の残像につられて光り始める瞬間 ”
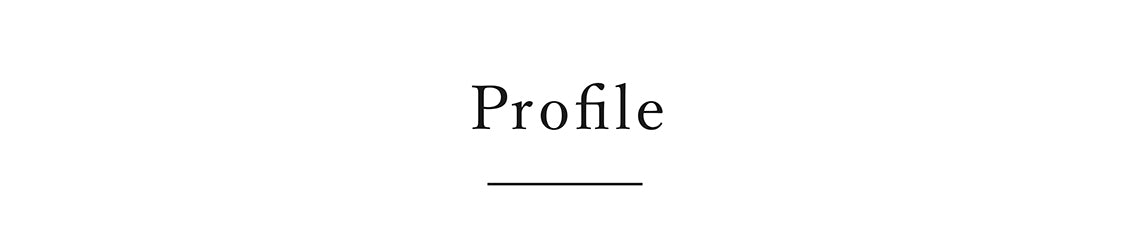
 1985年広島生まれ。文筆家。京都在住。小説、短歌、エッセイなどの文芸作品や、インタビュー記事を執筆する。著書に歌画集『100年後あなたもわたしもいない日に』、インタビュー集『経営者の孤独。』、小説『戦争と五人の女』がある。
1985年広島生まれ。文筆家。京都在住。小説、短歌、エッセイなどの文芸作品や、インタビュー記事を執筆する。著書に歌画集『100年後あなたもわたしもいない日に』、インタビュー集『経営者の孤独。』、小説『戦争と五人の女』がある。
 1981年神奈川県生まれ。東京造形大学卒。千葉県在住。35歳の時、グラフィックデザイナーから写真家へ転身。日常や旅先で写真撮影をする傍ら、雑誌や広告などの撮影を行う。
1981年神奈川県生まれ。東京造形大学卒。千葉県在住。35歳の時、グラフィックデザイナーから写真家へ転身。日常や旅先で写真撮影をする傍ら、雑誌や広告などの撮影を行う。
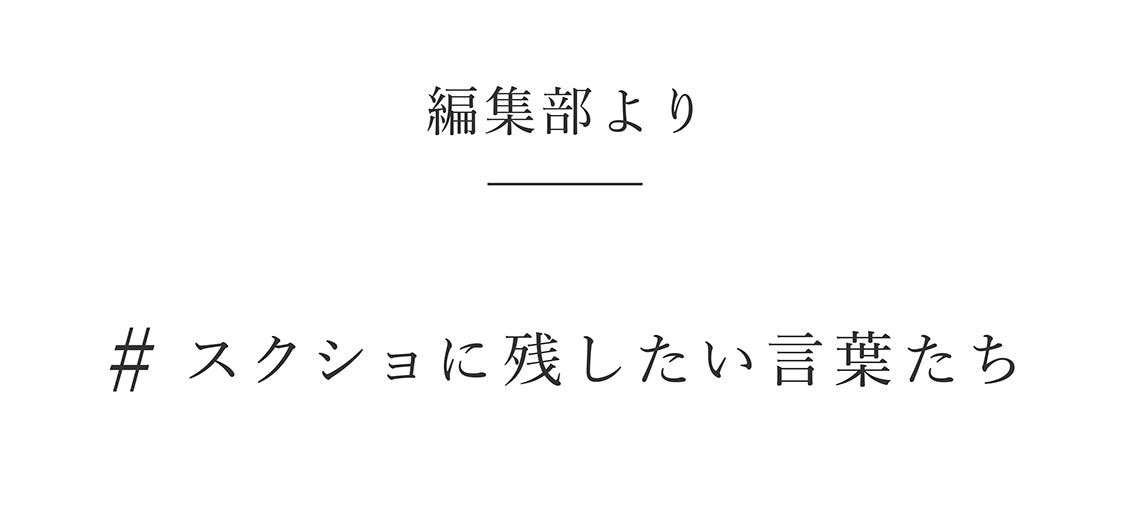
私たちの日々には、どんな言葉が溢れているでしょう。美しい景色をそっとカメラにおさめるように。ハッとする言葉を手帳に書き留めるように。この連載で「大切な言葉」に出会えたら、それをスマホのスクリーンショットに残してみませんか。
感想を送る













