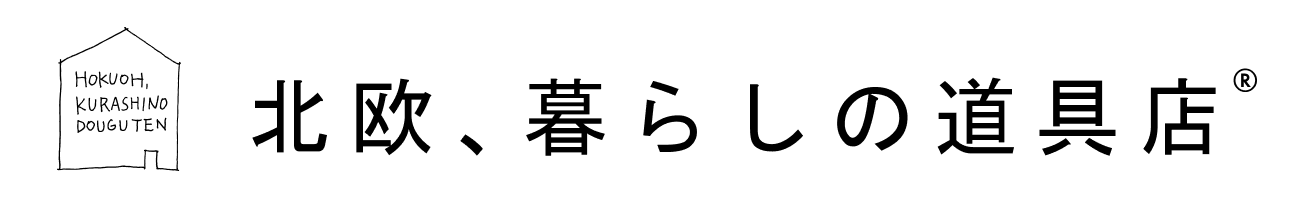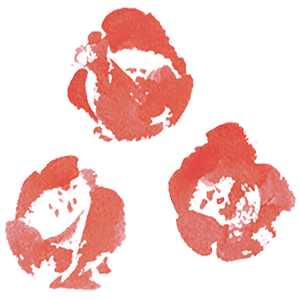年に4回、立春・立夏・立秋・立冬の前にある土用の期間は、季節の変わり目の18日間です。今回は夏の土用について、風習の意味や体調との関係を紐解く連載です。
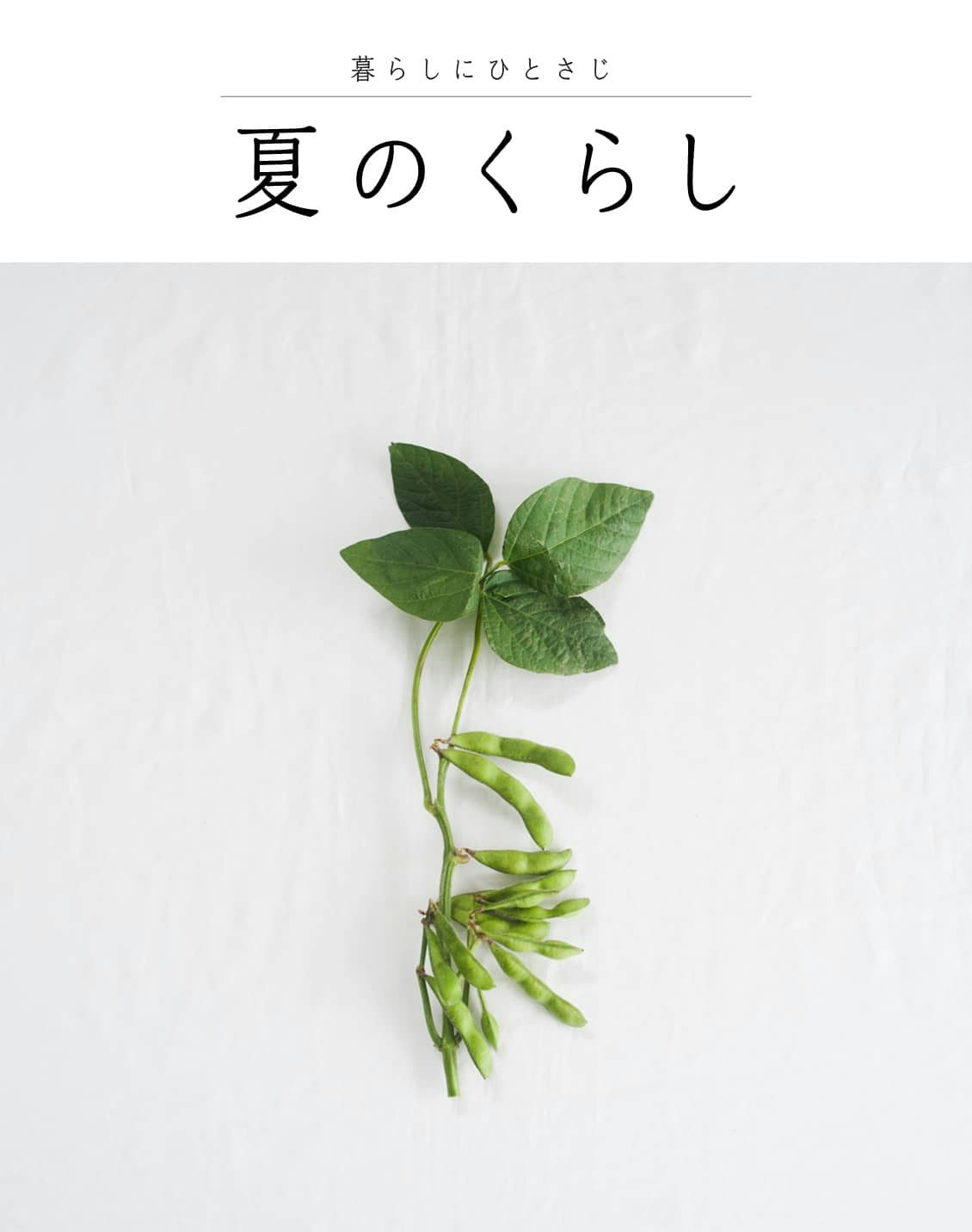
衣食住のなかで、いま私たちが知りたい日々の暮らしに役立つ、小さなアイデアをお届けする「暮らしにひとさじ」のシリーズ。この記事は、当店の編集チームが気になるトピックについて、専門知識をお持ちの方にお話を聞いて連載します。
「夏の土用」とは?風習の意味や過ごし方
テーマは「夏の土用」。2018年では7月20日から8月6日までの期間が土用にあたります。
和文化研究家・三浦康子(みうら やすこ)さんに監修していただき、夏の土用の過ごし方について、昔から伝わる風習の意味や、今の暮らしに取り入れるコツなどを伺ってきました。
夏の土用の風習を紐解いていく5回の連載は、以下の通りです。
01. 梅雨明けは、体調を崩しやすい?
梅雨明けから、8月7日の立秋までの土用の期間の季節のこと、体調との関係などをくわしく説明しています。また、この時期に食べるとよいとされるものについても紹介しています!
→詳しくはこちらから
02. 丑の日に、スーパーのうなぎを美味しく食べるコツ
夏の土用の期間に訪れる、丑の日。この日に食べるとよいうなぎを、家でも手軽においしく仕上げるコツをご紹介しています。
→詳しくはこちらから
03. 旬の「枝豆」、きほんの茹で方
旬の野菜をとることも、体の養生の方法のひとつ。知っているようで知らない枝豆の基本の茹で方を、料理家の方に教わりました。
→詳しくはこちらから
04. 暑中見舞い・残暑見舞いを送る時期
暑中見舞いって、なぜ送るの?という素朴な疑問を解消。送る時期のマナーなどをくわしく説明しています。
→詳しくはこちらから
05. 土用に行うといい「虫干し」って?
梅雨でたまった家の湿気をとるための「虫干し」についてご紹介しています。いまの暮らしに取り入れるなら、どんな湿気取り方法があるかも探ってみました。
→詳しくはこちらから
****
年に4回、立春・立夏・立秋・立冬の前にある土用の期間は、季節の変わり目の18日間です。
なかでも、夏の土用は、一番体に負担のかかる暑い時期。だからこそ、スーパーにうなぎが並び、その時期に食べると良いとされていたり、その季節だからこそ暮らしに取り入れたい習慣があったりと、体調を整えて猛暑を乗り切る知恵が昔からあるようです。
【写真】松元絵里子
感想を送る