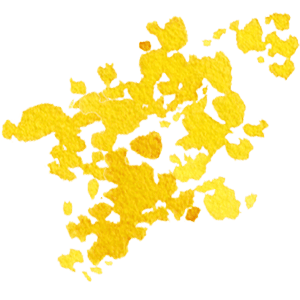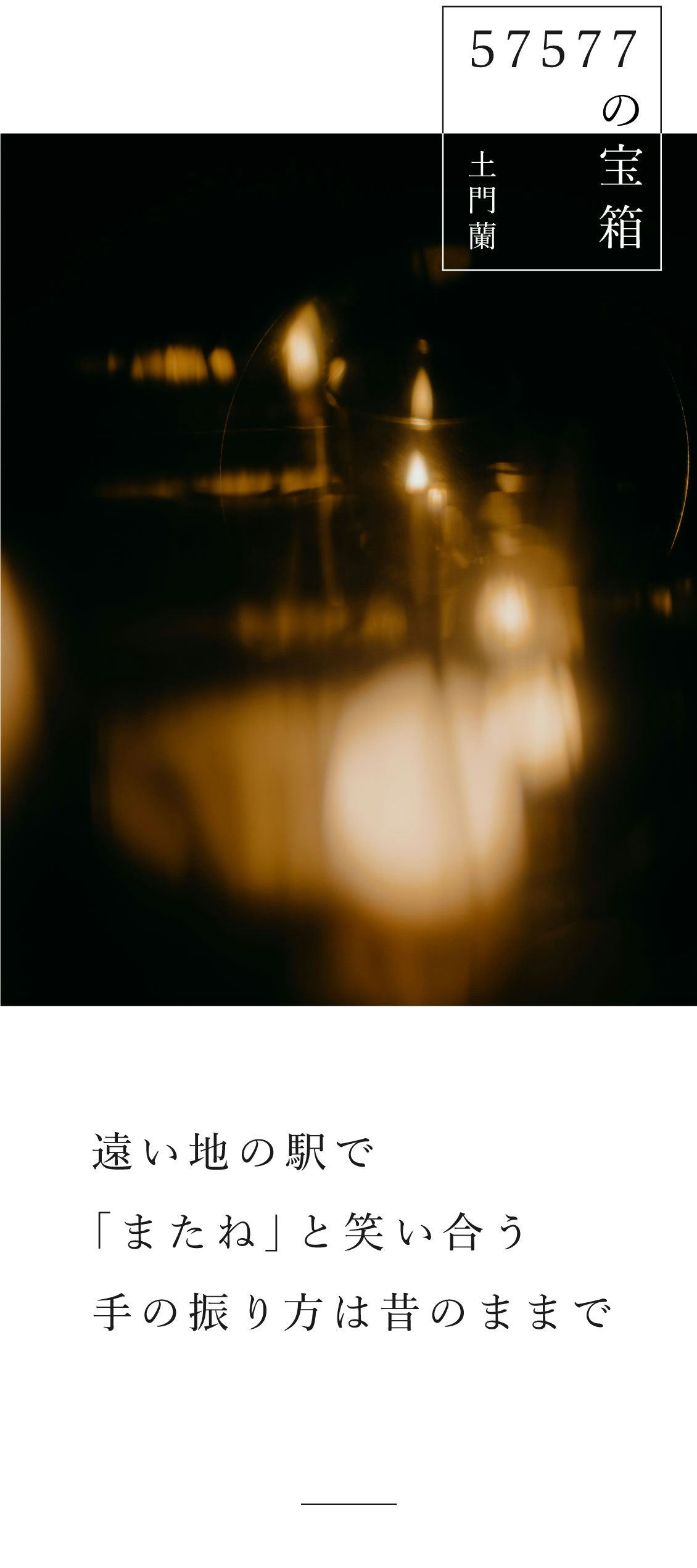
先日、仕事で熊本へ行った。
熊本には行ったことがないので、ご飯がおいしいということ以外は、どんな街なのか詳しく知らない。ひとつだけ頭に浮かんだのは、高校時代の友人の顔だった。熊本といえば、あの子が住んでいる街だ。
彼女は今、熊本で動物病院を営んでいる。二人の子育てもしているので、忙しい日々を送っているだろう。それでも「会いたいな」と思った。前に会ったのは高校を卒業してすぐの時だったから、15年以上会っていない。熊本から京都に帰る前に、久しぶりに顔を見て話がしたいと思った。
それでこんなメッセージを送った。
「今度の土曜日の午前、会えたりしない?」
すると彼女はすぐに予定を調整して、快諾してくれた。楽しみだと言い合って、私たちは当日、熊本駅で待ち合わせた。
§
彼女は、高校で初めて友達になった人だ。
出席番号がひとつ違いで、私が彼女の前の席。笑顔が朗らかで、読書が好きで、字をきれいに書く子だった。その頃から動物や虫が好きだと言っていた。
私は不真面目な生徒だったので、苦手な科目の授業中にはよく、教科書で隠しながらプリントの裏に散文を書きつけていた。板書に関係なくずっと何かを書き続けているので、後ろの席の彼女は疑問に思ったのだろう。
「蘭ちゃんは授業中、何を書いているの?」
と聞かれたことがあった。
私は少し照れながら、「小説みたいなもの」と答えた。
「みたいなもの」と言ったのは、自分でもこれが何かよくわからなかったからだ。小説を書こうという気持ちでもなかったし、誰かに読ませようという気もなかった。ただなんとなく、小説みたいなものを書いていた。
だから、彼女が目を輝かせて「できあがったら読ませてほしい」と言ったときには戸惑った。そんなに大したものじゃないと慌てたけれど、人から「読ませてほしい」と言われたのは初めてだったので、私は頷き、頑張って完成させることを約束した。
できあがった短編小説には『蝉』というタイトルをつけた。
二人の女の子の話だったのは覚えているが、手元に残っていないので詳しいあらすじは覚えていない。プリントの裏に手書きで言葉を書き連ねた、今考えればすごく読みにくい文章だったと思うが、彼女はそれを熱心に読んでくれた。そして、感想の手紙まで書いて渡してくれた。私が書きたかったであろうテーマに対してツメの甘いところ、影響を受けているのがわかる作家など、なかなか手厳しい内容だったけれど、その手紙はこんな言葉で締めくくられていた。
「私は蘭ちゃんのファンです。これからもずっと書き続けてね」
それが私の初めて書いた小説であり、初めて人に読まれる体験だった。
以降も、彼女は私の書いたものを読み続けてくれていて、数年に一度、手紙やメールをくれる。
§
久しぶりに会った彼女は、学生時代と全然変わっていなかった。
もう15年以上会っていないなんて考えられないほど、久しぶりという感覚がなく、私たちは「どこ行く?」と自然に並んで歩き始めた。
スターバックスでコーヒーを飲みながら、いろんな話をした。
仕事や家族、子育ての話。高校時代とは話題がずいぶん違っているのに、まるであの頃の感じと変わっていなくて、教室の中でおしゃべりの続きをしているようだ、と思う。
「今、高校の制服を着せても全然違和感ないと思うな」
と言うと、彼女は笑った。だけどそんなことはありえないのもわかっていた。私たちはちゃんと大人になっていて、心身ともにちゃんと歳を重ねている。
「蘭ちゃんが私に小説を読ませてくれたとき、何て言ったか覚えてる?」
彼女にそう尋ねられ、私は首を振った。
「蘭ちゃん、あのとき、『この小説は女子高生の私が書いたものとして読んでほしい』って言ったんだよ」
私はそれを聞いてなんだか恥ずかしくなった。多分、あなたが普段読んでいる作家と比べるなと言いたかったのだろう。よほど自分の作品に自信がなかったんだな、と思う。
「よく覚えてるなぁ」
「自分の話した言葉は忘れているけど、人の話したことはよく覚えてるもんだよね」
それから彼女が「蘭ちゃんは何かを思い出すとき、どんな風に思い出す?」と聞いてきた。
「映像で思い出す? それとも音声?」
「うーん。映像とか、匂いとかと一緒に思い出すかなぁ」
と、考えながら答える。
「例えばあなたに小説の感想の手紙をもらった時のことは、1年1組の校舎の光景を思い出すよ。木造でボロくて、踏むとギシギシいった廊下とか、自分の白いスニーカーのつま先とか、埃っぽい匂いとかさ」
すると彼女は「うん、私もそう」と笑った。
その瞬間、熊本のスターバックスに、あの校舎の匂いが漂った気がした。土埃を吸った古い木が放つ、かすかに甘く重たい匂い。
その校舎はとっくに取り壊されて、今はない。だけど、私たちの体の中にまだ息づいているんだと思った。「女子高生の土門蘭」も「女子高生の彼女」も、あの小説も、あの手紙も。
§
新幹線の時間が近づいて席を立とうとした時、彼女が私に小さな箱をくれた。
「これ、プレゼント」
と言う。
箱を開けてみると、中にはガラスでできたキャンドルホルダーが入っていた。
「これからも、人の心に灯りをともすような文章を書き続けてね」
そう言った彼女は、大人のようにも子供のようにも見えた。
私は頷いて、「また小説を書くから読んでよ」と言う。
彼女は「もちろん」と笑った。
そう言葉を交わしたのは、「女子高生の私たち」だったのかもしれない。
熊本駅で、私たちは「またね」と手を振り合った。
背を向けて歩きながら、自分の顔が少しずつ大人の顔に戻るのを感じる。
私たちは日々変化しているけれど、一緒に過ごした時間はずっと消えない。
彼女からもらったプレゼントの重みを感じながら、私はゆっくり改札口へと向かった。

“ 遠い地の駅で「またね」と笑い合う手の振り方は昔のままで ”
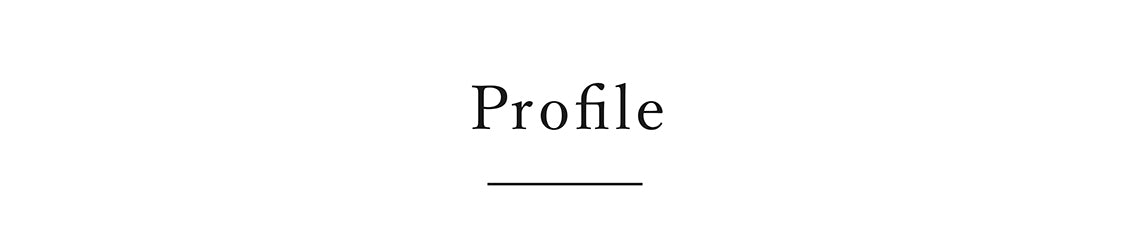
 1985年広島生まれ。文筆家。京都在住。小説、短歌、エッセイなどの文芸作品や、インタビュー記事を執筆する。著書に歌画集『100年後あなたもわたしもいない日に』、インタビュー集『経営者の孤独。』、小説『戦争と五人の女』がある。
1985年広島生まれ。文筆家。京都在住。小説、短歌、エッセイなどの文芸作品や、インタビュー記事を執筆する。著書に歌画集『100年後あなたもわたしもいない日に』、インタビュー集『経営者の孤独。』、小説『戦争と五人の女』がある。
 1981年神奈川県生まれ。東京造形大学卒。千葉県在住。35歳の時、グラフィックデザイナーから写真家へ転身。日常や旅先で写真撮影をする傍ら、雑誌や広告などの撮影を行う。
1981年神奈川県生まれ。東京造形大学卒。千葉県在住。35歳の時、グラフィックデザイナーから写真家へ転身。日常や旅先で写真撮影をする傍ら、雑誌や広告などの撮影を行う。
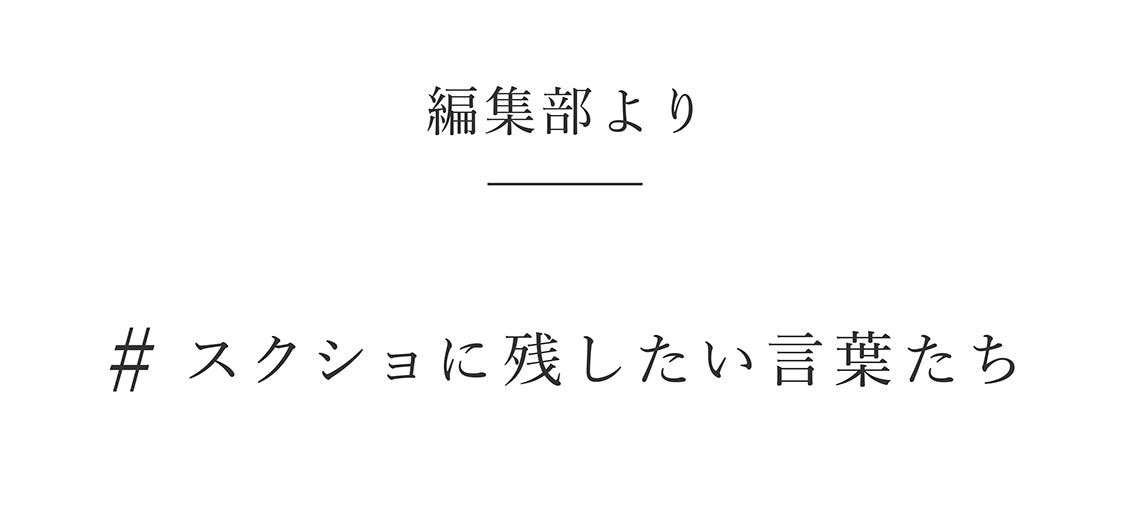
私たちの日々には、どんな言葉が溢れているでしょう。美しい景色をそっとカメラにおさめるように。ハッとする言葉を手帳に書き留めるように。この連載で「大切な言葉」に出会えたら、それをスマホのスクリーンショットに残してみませんか。
感想を送る