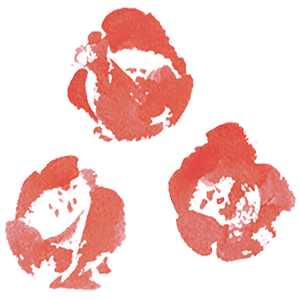詩人の長田弘は、かつて「世界はうつくしいと」という詩を書きました。
きらめく川辺の光、おおきな樹のある街の通り、なにげない挨拶、さらりと老いてゆく人の姿など、「うつくしいものの話をしよう」「あざやかな毎日こそ、私たちの価値だ」と、静かに語りかける短い詩です。
私たちは、毎日ただ過ごしているだけでも、うつくしいもの、快いもの、そうじゃないものを、感じ取りながら生きています。
日々の暮らしを支える活動やモノを通じて、美を捉える「日常美学」は、哲学の一分野である美学の中でもとりわけ新しい領域。そこには「暮らし」を見つめ直す、大切なヒントがあるかもしれません。
私たちの生活のなかでの感性のはたらきについて哲学的研究を行っている、美学者の青田麻未(あおた まみ)さんにお会いして、おだやかに晴れた冬の日、じっくりお話を聞いてきました。
家よりも、学校のほうがくつろげる子どもでした。

まずは青田さんが「日常美学」という道を選んだ原点を伺います。
小さい頃から家や暮らしが好きだったのかと思いきや、意外にも「10代は、家という場所に窮屈さを感じていた」と話します。
青田さん:
「実家は、郊外のマンションでした。妹と二人部屋だったので、ずっと一人部屋に憧れていましたね。
こんな家に住みたいと妄想したり、シルバニアファミリーで遊ぶときも、人形同士を会話させるより、ひたすら家具を並べるのが好きで、ベストな配置になったら遊びはおしまい。
豪邸に住んでいるという設定で、近所の大きな県立公園を『庭』に見立てて散歩したり、怪盗セイント・テールというアニメの公式ブックに載っていた『主人公の1日のルーティン』が好きで、ずっと読んだりしていました。理想の暮らしを考えることは、結果的に多かったのかもしれません。
中学生くらいのとき、クラスで一人部屋を持っていないのは片手で数えられるくらいだと、ひょんなことで明らかになり、妹との相部屋がどうしても嫌になってしまって。部活がない日もすぐには帰らず、学校や図書館にいるほうがくつろげていた記憶です」
"絶対的な正しさ" はないと知る。

学校が好きで、いつか自分の理想の学校「青田学園」を作りたいと、大学では教育学を専攻しようと考えていました。しかし既存の教育システムを学ぶうち、もっと根本的なものの見方に関心は向かっていきます。
青田さん:
「きっかけは、抽選で決まった必修科目で『科学革命の構造』(トーマス・クーン著)を読む授業に出たことでした。
『絶対的な正しさがある』と思われている科学でさえ、時代背景や価値観によって全く異なる見方がある、大前提だと思っていた『ものの見方』そのものが、実は相対的なものだと知って、そういうことか!と思いました。
すごく面白くて、こういう哲学とか思想的なことをもっと深めたいな、と感じました」
『科学革命の構造』を研究するゼミを見つけたものの、そこには成績が足りず……。
色々と探していたときに美学芸術学という分野に出合い、「お歯黒から漫画まで、何でも研究対象にできる」という懐の広さに惹かれて、美学の研究へ進むことにしました。
言葉にできないモヤモヤを、言葉にしようと試みること。

美学というと、絵画やクラシック音楽、現代アートの作品など、自分の生活とはすこし距離がありそうですが、青田さんにとって、美学を研究する面白さは、どんなところにあったのでしょう。
青田さん:
「美学者としての根本にあるのはずっと、自分に関わることを丁寧に考えたい、という欲求なのかもしれません。
美学は、哲学の一種ですが、とりわけ言葉にしにくいものを扱う学問です。
たとえば、何かを見たり聴いたりして『美しい』と感じることは、きっと皆さん経験したことがあると思います。だけど、じゃあ『なぜ美しいのか?』と問われると、うまく言葉にできなかったりします。
美学が扱おうとしてるのはここです。
ある対象に出合ったときの感覚、モヤモヤっとした言葉にならないもの、感性に訴えかけてくるものを、できる限り言葉にしようと頑張ってみる。このプロセスが、すごく面白いなと思いました」
「ふつうの暮らし」を美学する。

卒業論文では、「自然美とはなにか」について理論的に研究しました。その後、研究者としてキャリアを重ね、『「ふつうの暮らし」を美学する 家から考える「日常美学」入門』(光文社新書、2024年11月)を出版します。
自然の美から、より身近な家の中へ。執筆したのはコロナ禍でした。
青田さん:
「美学の論文って、自分の経験に言及しないで書ききることが難しいんです。
コロナの頃は、当初自分はステイホームが苦にならないと思っていたし、子どもと暮らし始めるという喜びの多い時期でしたが、なぜか次第に、生活そのものが縮んでしまったように感じて、寂しさや不安も感じるようになって……。
遠くの自然や環境よりも、ままならない日常の中、目の前にある『家』という場所を、美学の視点から見つめ直してみたら、自分なりの論文や著書が書けるのではないかと考えました」

青田さん:
「日常美学では、不快なものに気づくことも『感性のはたらき』だと考えます。
たとえば、カビを見つけて『嫌だな』と思い、それをゴシゴシ落として綺麗になったとき、最初から綺麗だったのとは違う、独特の心地よさを感じます。
あるいは、器が割れてしまったとき、新品を買ったほうが早いかもしれないけど、金継ぎをすることで、自分とものとのストーリーが生まれ、なんとも言えない癒しを感じられます。
不快なものに気づき、そこにアプローチして、自らの手で新しい状態を作り出す。この繰り返しによって、私たちは、自分の生活をつくっていく。そういう『ふつうの暮らし』における感性のはたらきを、丁寧に考えてみたいと思いました」
生活とは、いかに自分がコントロールできないものを扱うか。

青田さん:
「いま、4歳の息子がトミカに夢中なんです。すぐにリビングが散らかってしまうから、使わなくなったものは一緒に整理するようにしています。
あるとき、その中に『スーパーアンビュランス』という救急車を見つけて。息子に聞くと、ふつうの救急車とは違うから両方とも残したいと。これって、私の世界には絶対になかった視点だなと。
こういった他者がもたらす予期せぬものを、どう受け入れて、どう共存していくか。
生活をつくるというのは、すべてを完璧にコントロールすることではなく、社会や他者からのノイズをどう選別し、応答していくかの試行錯誤そのものだと思うんです。
それを自分の世界を広げてくれる『ノイズ』として受け入れてみることで、私たちの生活は変わっていきます。日常美学は、そういったところでの『感性のはたらき』にも、注目しています」
私たちの感性が、世界をつくっている。

青田さんのお話を聞いていると、家の中のことから自分の快・不快を丁寧に考えることは、いつの間にか、他者や社会にも続いていると気づかされます。
青田さん:
「日常美学は、その視点をとても大事にしています。
たとえば、プラスチックは便利だけれど、それによる環境負荷を『感覚として嫌だ』と思えること。私たちの感じ方のレベルで何かが変わらないと、社会の仕組みは変わっていきません。
これは1960年代ごろ、行きすぎた資本主義、大量生産・大量消費社会への批評を含めた学問として、環境美学(日常美学の前身)が成り立った背景にあるものです。
こういう話をすると、日常美学って、ロマンティックだとか理想主義だとか言われてしまうのですが……」

青田さん:
「我が家も散らかったままで、自分のごはんは適当にすませるしかない日も多いです。そのことを、心のどこかで仕方ない、と受け入れてしまっている部分もあって(苦笑)
だからこそ、不快なものに気づいたり、ノイズを受け入れたりしながらも、理想をもつことの切実さを感じます」
「世界をつくっているのは、私たち一人ひとりの感性です」と青田さん。よりよく生きるために、感性をどのように磨いていくことができるのか。後編に続きます。
【写真】馬場わかな
もくじ
第1話(2月3日)
根本にあるのはずっと、自分に関わることを丁寧に考えたいということ。(美学者・青田麻未さん)
第2話(2月4日)
ふつうに暮らしているつもりでも、私たちの「感性」ははたらいている。(美学者・青田麻未さん)


青田 麻未(あおた・まみ)
1989年、神奈川県生まれ。2017年、東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(文学)。上智大学文学部哲学科助教。専門は環境美学・日常美学。私たちの生活のなかでの感性のはたらきについて哲学的研究を行っている。日常美学の入門書として、『「ふつうの暮らし」を美学する 家から考える「日常美学」入門』(光文社新書、2024年)を出版。
感想を送る