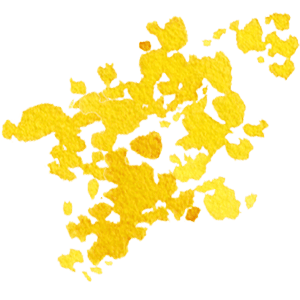「もし本が好きになったら──私たちがその人たちを見つけて、めいっぱい大切にしよう。世界中のたくさんの本を翻訳して、朗読して、笑ったり泣いたりしよう」
ロシア文学者・翻訳家の 奈倉有里 さんは、著書『文化の脱走兵』にこう書いています。
過去の思い出と現在を行き来しながらロシアの詩や小説の魅力に触れる『文化の脱走兵』や、ロシアの大学で文学を学んだ日々について綴った『夕暮れに夜明けの歌を』。奈倉さんの著書を読み、そのまっすぐで情感豊かな文章に胸を打たれただけでなく、それまで遠く感じていたロシア文学への扉を開けてもらった気がしました。
何より心に残ったのは、奈倉さんの「本が好き」という強い気持ち。世界を取り巻く状況がめまぐるしく変化し、ときには不安も感じるなか、文学と言葉への信頼や希望を失わないその姿勢に惹かれたのです。
奈倉さんはどのようにして本や言葉と向き合ってきたのか。本を読むこと、言語を学ぶことの意味はどんなものなのか。じっくり伺ったお話を全3話でお届けします。
自分がロビン・フッドになって、森の中にいる感覚に
奈倉さんは2000年代にロシアに留学後、日本の大学院を経て、現在はロシア文学研究者、翻訳家、そしてエッセイストとしても活動中です。幼い頃から本好きだったのでしょうか。まずは子ども時代について聞いてみました。
奈倉さん:
「両親と、3歳下の弟との4人家族です。小学2年生のときまで所沢の団地に住んでいて、その後横浜に移りました。
幼稚園の頃から絵本は好きでしたが、家に児童書や絵本がたくさんあったわけではなく、ごく普通の環境でした。ただ、本が山のようにあったらどんなにいいだろうと思っていて、そういう夢をよく見ていましたね。父が日本史の研究者だったので、父の本はありましたが、子どもには全然読めなくて。『お父さんの本ばかりでずるい』って思ってました。
家にテレビはあるにはあったけれど、親が興味がなかったからか、点いていることはほとんどなくて、せいぜい天気予報くらい。だから私、テレビっていうのは天気予報が映る箱だと思っていたんです。そういう環境もあって、本をよく読んでいたのかもしれません」
奈倉さん:
「文字ばかりの本で最初に夢中になったのは、小学3年生の頃に読んだ『ロビン・フッドの冒険』です。熱を出して学校を休んでいた時、父が自分の子ども時代に読んだ古い児童文学全集を貸してくれて、その中にあった1冊でした。
読んでいる間、現実を忘れるくらい本の世界に入り込んでいく、そういう体験を初めてしたんです。全く知らない世界のはずなのに、自分自身がロビン・フッドとして森の中にいて、弓矢を上手に使っている、そんな感覚でした。
その後もいろいろな本を読みました。日本の作品にある “自分に近い” と感じるような面白さと、海外文学の “全く違う世界に行ける楽しさ” 、両方とも捨てがたかったです。
学校の図書室でもよく本を借りていました。図書室から屋上へと続く階段があって、途中の踊り場の暗いところに本棚があったんです。そこにはみんなが借りなくなった古い世界名作全集が置いてありました。こんな暗いところに誰も借りない本があるなんて、私しか知らない宝物みたいな気がして、ワクワクしたことを覚えています」
遠く感じていた世界が、実は身近なものだと気づく瞬間
子ども時代からずっと、さまざまな本を読んできた奈倉さん。今はどんなジャンルが好きなのかを聞いてみました。
奈倉さん:
「現代の作品も読みますが、放っておくとつい読んでしまうのはシェイクスピアとかゲーテとか、いわゆる古典と呼ばれる作品です。といっても、偉大な名作だからとか、普遍的だからということではないんです。
古典は、長い年月をかけて読み継がれてきていますよね。それぞれの時代にさまざまな場所で読んだ人たちの注釈も一緒に読むと、その人たちが解釈してきた歴史みたいなものが分かって、面白さが重層的になるんです。みんな自分たちの当時の悩みに引きつけて読んでいたんだなと分かったり。
だから古典は、本そのものはもちろん、世界中で読んできたいろんな人たちと通じ合えるような楽しさがあるんですよね」
奈倉さんは翻訳家としても活躍中。さまざまなロシア語の文学作品を翻訳し、日本に紹介してくれています。
正直に言って、ロシア文学には「重く難しいテーマが多く、理解しづらい」イメージがあって、これまで敬遠しがちだったのですが……。
奈倉さん:
「たとえば、去年日本で出た新刊のことを考えてみましょう。印象に残っているのは金原ひとみさんの『YABUNONAKA』や朝井リョウさんの『イン・ザ・メガチャーチ』。どちらも現代日本の社会問題を描いていて、十分に “重く” て “難しい” テーマを扱った作品です。ですが、自分たちも同じ現代日本という文脈の中で生きているので、もちろん理解することはできます。
でも、こういう作品を、たとえば100年後のイタリアで読んだら『日本文学って重いし、暗いし、分からない』となるかもしれません。それは日本文学が分からないんじゃなくて、文脈が失われてしまうから分からないんですよね」

奈倉さん:
「そうした分からなさを一つひとつ解決していけば、すごく遠いと思っていたものが分かったり、自分の感情に身近なものだと気づいたりする。その瞬間はいつだって感動的です。翻訳はそのための手助けをしなくてはいけないと思います。
現実を忘れるほど作品の世界に入り込む読書ってすごく面白いですよね。そうなったら楽しいなと思いながら読むのと、最初から『難しい』と敬遠しながら読むのとでは、作品への入りやすさは違ってくると思うんです。だから、あまり身構えずに読むのがいいのかなと思います。
ちなみにロシア文学の一般的なイメージって、きっとドストエフスキーの長編など、ほんの数冊の本から作り出された思い込みなのかもしれません。ロシア文学に限らず、どの国の文学にもいえることですが、あまり構えずに読んでみると、すごく面白い作品も、何度読んでも泣いてしまうような切ない作品も、心温まる作品も、何でもありますよ」
物語を知っていればいるほど、人生の支えになる
奈倉さん:
「物語って人間の精神的な動力みたいなもの。どんな時でも、たとえばどこかへ出かける時だって、人間はひとつの物語を作っているんです。
生きていく中で、自分が想定していた物語が頓挫してしまったりすると、絶望してしまいがちです。でも、物語をたくさん知っていると『こっちがダメでも、こっちがある』といった具合に物語のストックの中からたぐりよせて、違う物語を作っていける。辛いことがあった時でも『あの本の、あの時の主人公みたいに考えれば、違う方向に発展していけるのでは』などと気づくことができるんです。
物語をたくさん知っていればいるほど、精神的に強くなると思います。文学なんて何の役に立つのかと思う人もいるかもしれませんが、実は人生を根本的なところで支えてくれるんですよ」
時代も場所もさまざまな物語が、自分の人生を支えてくれる確かな力になる。そんな話を聞くと、難しそうと敬遠していた本に挑戦する意欲も湧いてきます。第2話では奈倉さんのロシア語との出会いやロシアに留学したいきさつ、さらには言葉を学ぶ喜びについても聞いていきます。
【写真】井手勇貴
もくじ


奈倉有里
1982年生まれ、ロシア文学研究者、翻訳家。2002年からペテルブルグの語学学校でロシア語を学び、その後ロシア国立ゴーリキー文学大学に入学、2008年に日本人として初めて卒業。東京大学大学院修士課程を経て博士課程満期退学。博士(文学)。著暑『夕暮れに夜明けの歌を』(イースト・プレス)で第 32 回紫式部文学賞受賞、『アレクサンドル・ブローク詩学と生涯』(未知谷)などで第 44 回サントリー学芸賞受賞。他の著書に『文化の脱走兵』(講談社)、『ことばの白地図を歩く』(創元社)、訳書に『赤い十字』(サーシャ・フィリペンコ著、集英社)ほか多数。3月17日に最新エッセイ『背表紙の学校』が刊行予定。
感想を送る